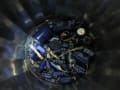RC-717のつづきです。各部を見ていきます。

まずは正面から。シンメトリカルなデザインです。

カセット部。「フルオートストップ」ではなく「オートストップ」なので、早送りや巻き戻しではストップしません。。。。余談ですが、今の若い人は「巻き戻し」って言葉、ピンとこないみたいですね。テープ文化復興を願います。

上面中央。カセット操作はピアノキー式です。ファンクションSWの「スリープ」は、深夜放送録音の強い味方。ラジオ録音時にスリープをオンにすれば、テープ終了とともに電源も落ちる仕組み。寝入ってしまってもだいじょうブイ!!(←24年前の流行語)。

上面左。音量は左右独立、トーンは高音・低音兼用なので使い勝手は悪いです。モード/メーターSWの「ワイド」とは、音の拡がりが増す機能。

上面右。端っこにある溝は、オプションマイクやショルダーベルトを差し込むところだったようです。

旧ビクターロゴ。ピンボケですが、ニッパー君の下に「HIS MASTER'S VOICE」とあります。レコードに記録された、亡くなった飼い主の声を聴いているという図です。「HIS MASTER'S VOICE」略してHMVは、大手CDショップの名前の由来ですね。


このラジカセの売りのひとつであるフレキシブルマイク。写真のように90度向きを変えられます。生録がブームだった当時ならではの機能です。

左側面。ラインイン・アウトをきちっと装備。

右側面。ACジャックのほかにDC9Vのジャックもあります。

背面。左側にある端子はアンテナとグランド。電池は単一を6本。
今から40年近く前の1977年に発売されたこのモデル、最初のオーナーは購入時、さぞや嬉しかったでしょうねえ。ラジオの深夜放送をこのラジカセで聴いたのかなあ。。。オールナイトニッポン、パックインミュージック、セイ!ヤング。。。。青春のトキメキを感じさせる、そんなラジカセでございました。

まずは正面から。シンメトリカルなデザインです。

カセット部。「フルオートストップ」ではなく「オートストップ」なので、早送りや巻き戻しではストップしません。。。。余談ですが、今の若い人は「巻き戻し」って言葉、ピンとこないみたいですね。テープ文化復興を願います。

上面中央。カセット操作はピアノキー式です。ファンクションSWの「スリープ」は、深夜放送録音の強い味方。ラジオ録音時にスリープをオンにすれば、テープ終了とともに電源も落ちる仕組み。寝入ってしまってもだいじょうブイ!!(←24年前の流行語)。

上面左。音量は左右独立、トーンは高音・低音兼用なので使い勝手は悪いです。モード/メーターSWの「ワイド」とは、音の拡がりが増す機能。

上面右。端っこにある溝は、オプションマイクやショルダーベルトを差し込むところだったようです。

旧ビクターロゴ。ピンボケですが、ニッパー君の下に「HIS MASTER'S VOICE」とあります。レコードに記録された、亡くなった飼い主の声を聴いているという図です。「HIS MASTER'S VOICE」略してHMVは、大手CDショップの名前の由来ですね。


このラジカセの売りのひとつであるフレキシブルマイク。写真のように90度向きを変えられます。生録がブームだった当時ならではの機能です。

左側面。ラインイン・アウトをきちっと装備。

右側面。ACジャックのほかにDC9Vのジャックもあります。

背面。左側にある端子はアンテナとグランド。電池は単一を6本。
今から40年近く前の1977年に発売されたこのモデル、最初のオーナーは購入時、さぞや嬉しかったでしょうねえ。ラジオの深夜放送をこのラジカセで聴いたのかなあ。。。オールナイトニッポン、パックインミュージック、セイ!ヤング。。。。青春のトキメキを感じさせる、そんなラジカセでございました。