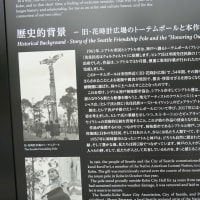2013年5月22日の朝日新聞に次のような記事がありました。
見出し「魔法瓶の名、勘違い? 教授の思い込み独り歩きか」
飲み物を保温できる「魔法瓶(まほうびん)」。その名の由来は長くはっきり
しなかったが、明治時代に東京帝大教授が名付けた可能性が高いことが最近
わかった。英語では「真空瓶」と呼ばれているのに、なぜ日本で魔法がかかった
のか。調べたのは、魔法瓶を社名にしている象印マホービン(大阪市)OBの
粟津重光さんもともと魔法瓶専業だった同社の1階にある「まほうびん記念館」
の前館長で魔法瓶の資料を集めていた。・・・・・以下略
粟津重光さんが見つけたのは明治40年(1907)10月22日付けの東京朝日新聞
の記事でここには魔法瓶の命名者、東京帝大教授で著名な動物学者&魚類学者で
飯島 魁(いいじま いさお)氏がイソップ物語の中に「魔法瓶」の話があり
何でもほしいものが出てくるという内容のものである。
そこでイソップ物語を調べて見たがイソップ物語に「魔法瓶」の話は無い。
似た物語を探し「宝島」で知られる英国のR.スティーブンソンの「瓶の子鬼」
と混同したと推定した。
これが粟津重光さんの結論で上記の朝日新聞に書かれています。
関連サイト
まほうびん記念館/象印マホービン株式会社 訪問記 By 大河原 克行
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20090608_212454.html
大阪市北区天満1丁目 まほうびん記念館
http://www.zojirushi.co.jp/corp/kinenkan/index.html
記念館は入場無料 見学には予約が必要
真空二重構造で熱を遮る魔法瓶の原型はドイツで生まれ1904年の独のサーモス社
が製品化。日本でテルモスと呼ばれたこの商品を飯島 魁氏が入手していた。
見出し「魔法瓶の名、勘違い? 教授の思い込み独り歩きか」
飲み物を保温できる「魔法瓶(まほうびん)」。その名の由来は長くはっきり
しなかったが、明治時代に東京帝大教授が名付けた可能性が高いことが最近
わかった。英語では「真空瓶」と呼ばれているのに、なぜ日本で魔法がかかった
のか。調べたのは、魔法瓶を社名にしている象印マホービン(大阪市)OBの
粟津重光さんもともと魔法瓶専業だった同社の1階にある「まほうびん記念館」
の前館長で魔法瓶の資料を集めていた。・・・・・以下略
粟津重光さんが見つけたのは明治40年(1907)10月22日付けの東京朝日新聞
の記事でここには魔法瓶の命名者、東京帝大教授で著名な動物学者&魚類学者で
飯島 魁(いいじま いさお)氏がイソップ物語の中に「魔法瓶」の話があり
何でもほしいものが出てくるという内容のものである。
そこでイソップ物語を調べて見たがイソップ物語に「魔法瓶」の話は無い。
似た物語を探し「宝島」で知られる英国のR.スティーブンソンの「瓶の子鬼」
と混同したと推定した。
これが粟津重光さんの結論で上記の朝日新聞に書かれています。
関連サイト
まほうびん記念館/象印マホービン株式会社 訪問記 By 大河原 克行
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20090608_212454.html
大阪市北区天満1丁目 まほうびん記念館
http://www.zojirushi.co.jp/corp/kinenkan/index.html
記念館は入場無料 見学には予約が必要
真空二重構造で熱を遮る魔法瓶の原型はドイツで生まれ1904年の独のサーモス社
が製品化。日本でテルモスと呼ばれたこの商品を飯島 魁氏が入手していた。