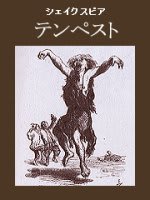「最短2年で司法試験に合格」というキャッチフレーズは、バーディーが大学に合格した際に、司法試験予備校からもらったパンフレットで見たものである。同じキャッチフレーズを、アメリカから帰ってきた直後、今度は新聞記事として目にすることになろうとは……。
さて、ロースクール制度については、このところ、厳しい批判が相次いでいる。中には廃止論もあるが、それはさすがに無責任というもの。今この瞬間も法曹養成のための努力を怠ってはならないのである。私個人としては、ロースクール制度自体は維持すべきだが、解体的出直しが必要と考える。現状を見る限り、これが理想の法曹養成機関とは言い難いからである。その原因は、学生と大学の双方にあると考える。そこで今日は、さしあたり、学生の現状を簡単に素描することとしたい。なお、以下は仮想の事例である。
(事例その1~Aさん)
一流大学の出身。大学時代、講義に出るのが面倒なため、講義録を丸暗記して試験を受け、首尾よく単位を取得してきた。ロースクール入学後も、朝起きるのがつらいので、1限目は必修科目でも2週間に1回しか出席しない。大好きなコンサートのチケットやプレステのソフトを買うために、教科書や教材にかかるお金を何とかして節約しようといつも苦心している。試験の後やつまらない授業の時には、自習室の自分のパソコンでゲームに熱中し、勉強の憂さ晴らしをする。
法曹の「社会的ステータス」や「リッチで自由なライフスタイル」に憧れており、内心では法律及び勉強一般が好きではないものの、必要悪と割り切って勉強している。
(事例その2~Bさん)
受験歴が長く、既に相当量の教材を持っている上、新しい教材が発売されると知るや、手に入れないと気がすまなくなる。一生懸命法律を勉強してきたという自負を抱いているせいか、司法試験に合格していない教官や自分より受験歴の短い学生のことを内心軽蔑している。授業の課題講評や自主勉強会などで自分の答案の問題点を指摘されると、ついついカッとなって声を荒げてしまい、相手が引き下がるまで反論する。ところが、実際にBさんの答案を読んでみると、日本語として意味の通じないところや文法的におかしいところがたくさんある。
「法律」「裁判官」「司法試験合格」などの「権威」に憧れて必死に勉強してきた。
(つづく)
さて、ロースクール制度については、このところ、厳しい批判が相次いでいる。中には廃止論もあるが、それはさすがに無責任というもの。今この瞬間も法曹養成のための努力を怠ってはならないのである。私個人としては、ロースクール制度自体は維持すべきだが、解体的出直しが必要と考える。現状を見る限り、これが理想の法曹養成機関とは言い難いからである。その原因は、学生と大学の双方にあると考える。そこで今日は、さしあたり、学生の現状を簡単に素描することとしたい。なお、以下は仮想の事例である。
(事例その1~Aさん)
一流大学の出身。大学時代、講義に出るのが面倒なため、講義録を丸暗記して試験を受け、首尾よく単位を取得してきた。ロースクール入学後も、朝起きるのがつらいので、1限目は必修科目でも2週間に1回しか出席しない。大好きなコンサートのチケットやプレステのソフトを買うために、教科書や教材にかかるお金を何とかして節約しようといつも苦心している。試験の後やつまらない授業の時には、自習室の自分のパソコンでゲームに熱中し、勉強の憂さ晴らしをする。
法曹の「社会的ステータス」や「リッチで自由なライフスタイル」に憧れており、内心では法律及び勉強一般が好きではないものの、必要悪と割り切って勉強している。
(事例その2~Bさん)
受験歴が長く、既に相当量の教材を持っている上、新しい教材が発売されると知るや、手に入れないと気がすまなくなる。一生懸命法律を勉強してきたという自負を抱いているせいか、司法試験に合格していない教官や自分より受験歴の短い学生のことを内心軽蔑している。授業の課題講評や自主勉強会などで自分の答案の問題点を指摘されると、ついついカッとなって声を荒げてしまい、相手が引き下がるまで反論する。ところが、実際にBさんの答案を読んでみると、日本語として意味の通じないところや文法的におかしいところがたくさんある。
「法律」「裁判官」「司法試験合格」などの「権威」に憧れて必死に勉強してきた。
(つづく)