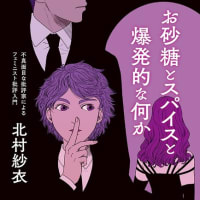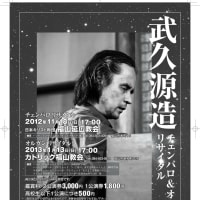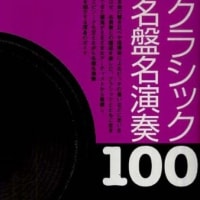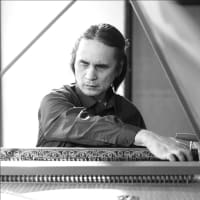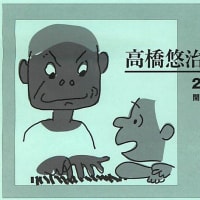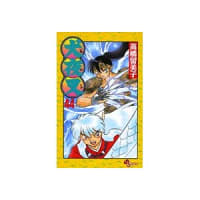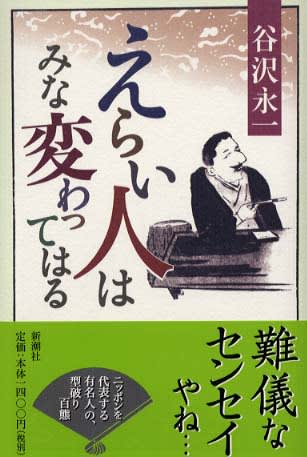
●〔39〕谷沢永一『えらい人はみな変わってはる』新潮社 2002 (2006.05.29読了)
市民図書館で借りました。
この三十数年、私の著作はコラムで充たされている。ただひとつの心残りは、私が蒐めた資料を生かして、明治大正の耳寄りな故事来歴を、コラム仕立てにまとめる仕事に、着手するに及んでいない焦りであった。それがこのたび機会を与えられ、書き連ねるよう仕向けられた。当事者の方々に厚く感謝の意を表する。(p.11)ということで、趣向は面白いのですが、出てくる人が古すぎて私にはいまひとつ、ピンときませんでした。
全体は文士篇、大学人篇、実業・出版人篇からなっていますが、やはり面白かったのは大学人篇でした。
『日本古典文学大系』の企画が岩波書店で浮上したのは、昭和二十年代の終り頃であったか。東大を出た新進気鋭の板坂元と、岩波書店の古参編集者玉井乾介とが、有名な岩波箱根別荘に籠って、全六十六巻の案を練った。学界地位の高い耄碌爺いには引っ込んで貰おうと、ピチピチした実力本位で行こうぜ、二人は意気投合して、空前の新鮮な執筆予定者一覧が遂に出来た。
しかし岩波は権威主義だから東大へ行ってボス教授の諒承を得なければならん。まず人事権を握っている麻生磯次に表を見せた。東大教養学部長、文学部長、学習院大学文学部長と学長、と切れ目なく公用車に乗っているこの男は、表を見るも見ないも頭から、執筆者は全員東大出身者に統一しなさい、と大原則を叩きつけるだけで細かい指図はしなかった。
そこで次なる大ボス久松潜一のご機嫌を伺うと、こちらは大勢の弟子を抱えているだけに細かくしつこい。気に入らぬ名前はバッサバッサと削ってゆき、空いたところへ直系の弟子をグイグイ押し込んでゆく。無能学者が蔓延って様変わりの人名表を見て、板坂元は涙をこぼしたという。
久松に引き立てられる人を、久松の特急列車と称する。そのひとりである神戸商船大学教授釜田喜三郎は、蓄財家として聞えるが研究などそっちのけである。それが『太平記』を宛がわれたのだが校注の方法がわからない。最も良質の写本を底本に選ぶ学力がない。そこで有り合わせの『参考太平記』を本文として、頭注の送稿を始めた。岩波の校閲部がオカシイと気付いて調べると、言葉の解釈は『広辞苑』を写しただけである。あまりのことに文句を言うと、内容見本に、辞書無しで読める、と宣伝しているから、それに従ったのだと答えた。
もうひとり特急に乗ったのは、『風来山人集』つまり平賀源内を担当した、北海道大学助教授の野田寿雄である。これもまた、難しい源内を読み解くための資料を蒐めていない。しかし岩波からは督促の電話がしきりである。困じ果てた野田は、只今三十枚、進んで五十枚、百枚と、賭けていない原稿枚数を口先で増やして行った。しかし相手はひねくれた執筆者を扱い慣れた熟練の編集者である。或る日の早朝に予告なしで、札幌の野田家を急襲し、さあ、原稿を見せて下さい。もちろん野田は一切を白状した。やむをえない。この仕事から降りていただきます。しかし、配本日は近づいている。九州大学の中村幸彦は、突然の依頼を、豊富な資料に拠って、短期間に仕上げた。(「古典大系愚景珍景」pp.153~154)
「腹を痛めた我が子」と書いたのを、「股を痛めた我が子」と誤植されて、「あんな恥かしい思いをしたことはなかった」と与謝野晶子が嘆いた話は、校正史上に有名である。(校正おそるべし!」p.221)
知事が内務省の任命であった昔、某氏が新潟県知事に赴任したので、土地の新聞が恒例により提灯持ちの記事を書き、その一節に「夫人が性交が巧みで」と書いた。社交の誤植である。夫人は知事の在任中、一度も新潟に足を踏み入れなかったと伝えられる。(校正おそるべし!」p.221)
谷沢永一もこれでしばらく打ち止めにするつもりです。