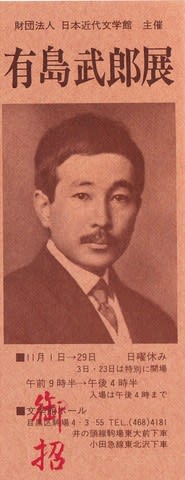(日本経済新聞 2003/10/11)
(日本経済新聞 2003/10/11)
7月30日は 歌人・小説家
伊藤左千夫 が亡くなった
「左千夫忌」
伊藤左千夫は
1864(元治元)年
千葉県成東町生れ
1881(明治14)年
政治家を志して上京し
明治法律学校(明大)に
入学するが 眼病のため帰郷
1885(明治18)年
再び上京して
牛乳店で働いたのち
1889(明治22)年
独立して東京・本所で
牛乳搾取業を営む。
1900(明治33)年
正岡子規の根岸短歌会に
加わり 写実的手法を学ぶ
1903(明治36)年
子規死後
根岸短歌会の機関誌
「馬酔木」を源流として
同年10月創刊の「アララギ」に協力
1909(明治42)年
編集兼発行者として
「アララギ」の基盤を作り
後進の育成に当たった
1913(大正2)年 死去 享年49
主な作品
「野菊の墓」(1906)
「春の潮」 (1908)
特に「野菊の墓」は
いとこ同士で幼なじみの
少年少女の純愛を
描いて代表作になる。
(web資料から)
1955(昭和30)年
木下恵介監督
「野菊の如き君なりき」
として映画化された。
小説では千葉県内の農村が
舞台であるが
ロケは 北信州で行われて
風光明媚な千曲川周辺の
情景を背景に
清純な少年少女の心情を
描いている。
*2019年 台風19号による
千曲川氾濫で被災した
地域になるのか?
この作品は
日本映画ベスト150では
第38位になっている。
特に 回想シーンには
白い楕円形のぼかしの
縁取りを入れ
明治の時代を浮かび上がらせて
話題になった。