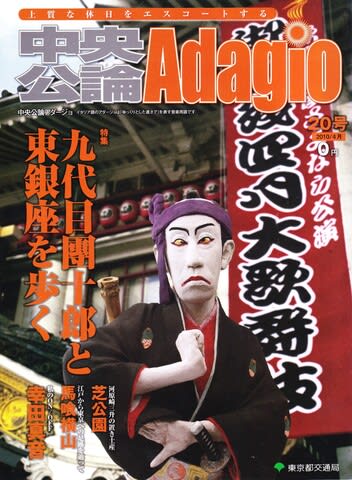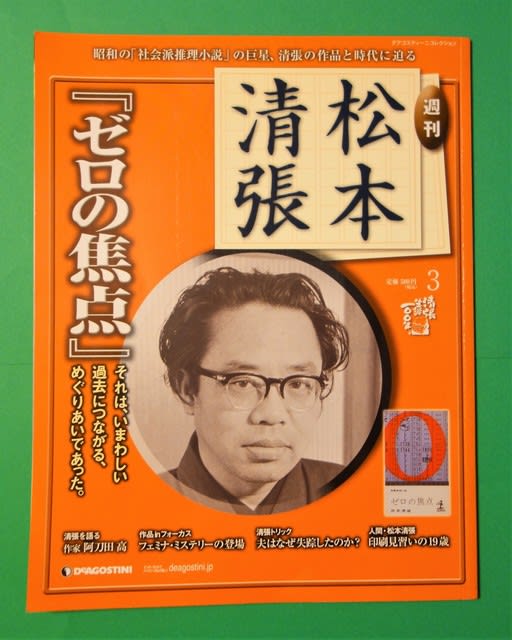NHKTV「100分de名著」(2018/05放映)から
10月22日は
精神科医師 神谷美恵子が
亡くなった日。
神谷美恵子は
1914(大正3)年1月12日
岡山県に、前田多門・房子の
長女として生まれる。
ジュネーブの
ジャンジャック・ルソー
教育研究所付属小学校、
ジュネーブ国際学校 、自由学園、
成城高等女学校に学ぶ。
1935(昭和10)年
津田英学塾卒業 学生時代に
多摩全生園聖書研究会に
オルガン奏者として関わり
ハンセン病患者のために
働くことを志す。
その後 コロンビア大学の
医学進学課程に進む。
1944(昭和19)年
東京女子医学専門学校卒業
インターン時代に長島愛生園で実習を経験
東京帝国大学医学部精神科医局で研究
1952(昭和27)年
大阪大学医学部精神科入局
1960(昭和35)年
「らいに関する精神医学的研究」により医学博士
1957(昭和32)年
長島愛生園精神科医師(非常勤)
1960(昭和35)年
神戸女学院大学教授
1963(昭和38)年
津田塾大学教授
1972(昭和47)年
長島愛生園精神科医師を辞める。
1976(昭和51)年
津田塾大学退職
1979(昭和54)年
10月22日死去 享年65
上皇后美智子様が
皇太子妃のころにも
相談役なっている。

NHKTV「100分de名著」
当方もそれなりの歳を重ねて
「生きがい」について
あらためて思いめぐらすが
チコちゃんに叱れるの
“ボーっと生きてんじゃねーよ!”
の口ですね
でも “日々是好日”でいければと・・・