| 列車消失 | ||
|---|---|---|
 |
読 了 日 | 2013/07/30 |
| 著 者 | 阿井渉介 | |
| 出 版 社 | 講談社 | |
| 形 態 | 新書 | |
| ページ数 | 302 | |
| 発 行 日 | 2007/10/04 | |
| I S B N | 978-4-06-182556-7 | |
 い先ごろ読んだ西村京太郎氏の「ミステリー列車が消えた」が頭に残っていたので、似たようなストーリーがないかと思っていたら、情報の出所はちょっと度忘れしたが、本書のタイトルを知ってアマゾンの古書店で入手した。
い先ごろ読んだ西村京太郎氏の「ミステリー列車が消えた」が頭に残っていたので、似たようなストーリーがないかと思っていたら、情報の出所はちょっと度忘れしたが、本書のタイトルを知ってアマゾンの古書店で入手した。
この新書は綾辻行人、有栖川有栖両氏の復刊セレクションと言う企画で、文字通り復刊されたようだ。だから、本書の発行日は2007年だが作品が書かれたのは1990年と、だいぶ古い作品でカバー折り返しの著者のことばとして、復刊に際して著者自身も犯人が誰かさえ思い出せなかった、とある。
そこで、そういうこともあるのだから、僕が読み終わった本の内容を忘れるのも、むべなるかな、と自分の物忘れを肯定する。
しかし、本書のことを知って、探せばまだ他にも同様のテーマを持った隠れた作品があるのかもしれないと思った。推理作家は常に独創的な作品の構想を考えるのと同時に、ほかの作家がどんなテーマで書いているのかということも知るため、たくさんの読書をするのだろう。(たまに作家のインタビューを聞いたりしてると、他の作家の作品は出来るだけ読まないという人もいるが)同じようなシチュエーションを作らないために。
しかし、逆に同じテーマを自分ならもっと奇抜に、あるいはスマートに、また違うトリックを使って、もっといい作品にする自信がある、ということもあるだろう。

古来、数え切れないほどの密室事件が登場するのはそうしたことではないか?
読者としても同じテーマであっても、いろいろと毛色の変わった作品が出てくるのは大歓迎だ。そんな作品を読み比べることが出来るのも、ミステリー読書の醍醐味である。
現在のようにミステリーの氾濫時代には、氾濫時代などと言うのはちょっと嫌な言い方だが、出版不況時代といいながら、次々と書店にミステリーの新刊が並び、あるいは主要な出版社では必ずといって良いほどのミステリー文学賞を主宰しているし、そこから毎年新人作家とその作品が輩出される。
そんな環境の中では、ミステリーの機械的なトリックというものに対する読者の反応は、当然といって良いほど芳しくはない。
僕もミステリーを読み始めた頃は、機械的なトリックによる密室の創造などといった、ストーリーを好んだ時期があった。しかし、いつの間にかそうしたトリックに魅力を感じなくなっていた。

 が、今頃になってまた、機械的なからくりを施したトリックに、興味がわいてきたのはどうしてだろう?
が、今頃になってまた、機械的なからくりを施したトリックに、興味がわいてきたのはどうしてだろう?
いや、列車の消失などという大掛かりな仕掛けがどのように行われるのだろうと、本書のようなタイトルを見ただけで、胸が躍るのだ。 僕にとっては、本格推理小説の醍醐味は、なんと言ってもトリックの面白さに尽きる。
この読書記録を綴るブログでは、本格推理だけではなくたくさんの種類のミステリーを読んできたから、昔夢中になった本格ミステリーをついつい忘れがちになるが、本書のようなトリック重視のミステリーを読むと、主にこんなミステリーばかりを読んでいた、以前のことを思い起こしてさらに、同様のものを探して読みたくなる。
本書は静岡県を走るJR東海の大井川鉄道井川線を舞台にした列車の消失事件を描くストーリーだ。「春を走る列車の歴史」という企画のもと、東京駅を出発して静岡駅まで新幹線、静岡から普通列車で東海道線を金山で、金谷から大井川鉄道千頭まではSL列車だ。そして最後、千頭からは森林鉄道井川線をディーゼル気動車井川ダムに向かうというコースであった。
ところが、千頭駅からJR東海静岡支社に奇妙な電話が入った。7両編成の列車のうち、6両目だけが走行中に消えてしまったというのだ。ミステリーのスタートである。
にほんブログ村 |











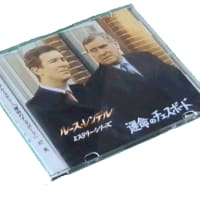

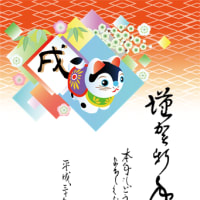





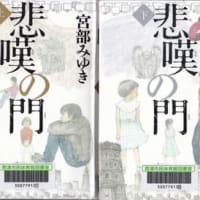
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます