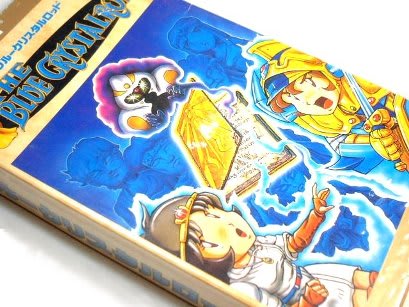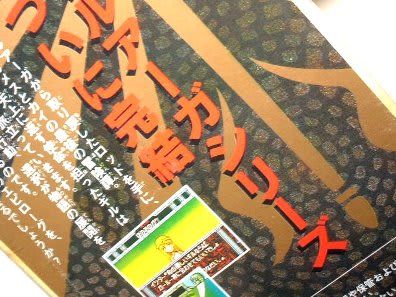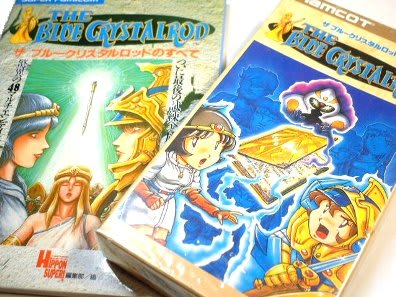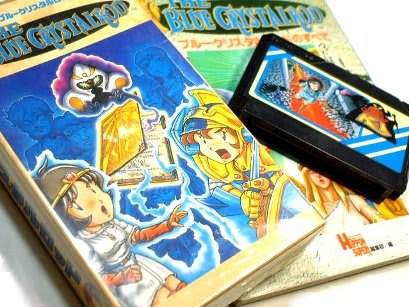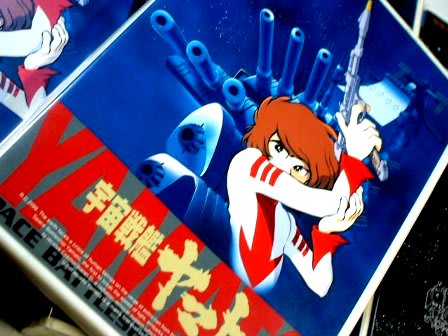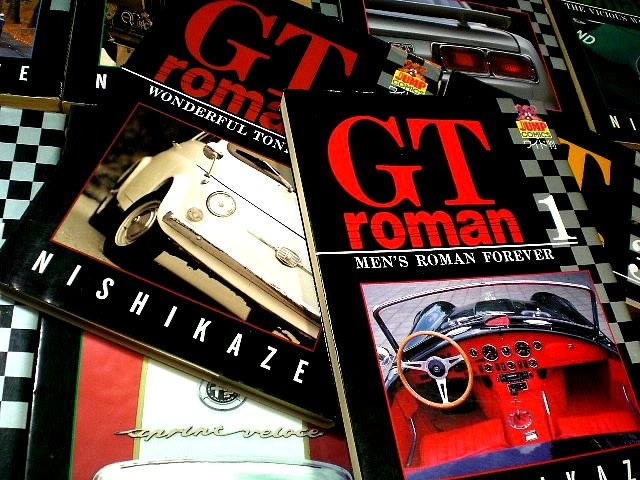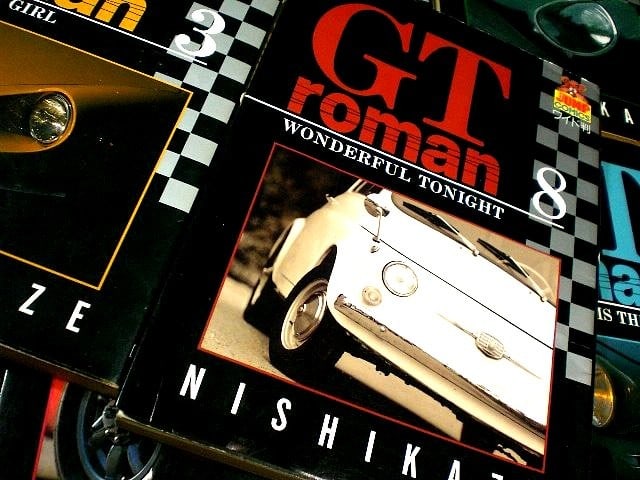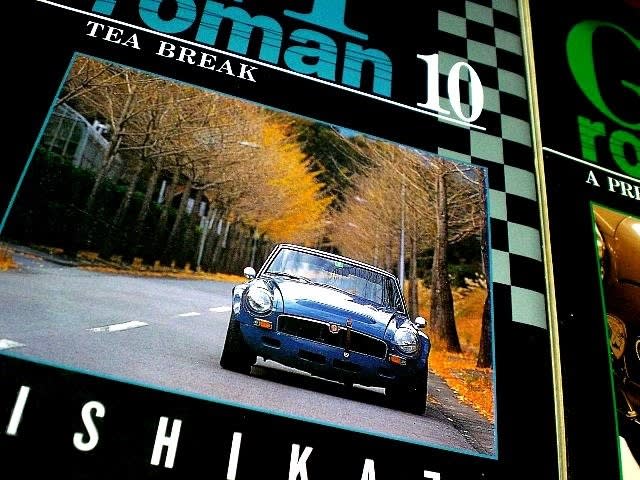週の真ん中(でもないか)、散財日記です。
Atari 2800ソフト・GANGSTER ALLEY・(中古/SPECTRAVIDEO) 100円
DVD・スターウォーズⅢ・シスの復讐・(中古/20th FOX) 700円
スターウォーズDVDは、レンタルアップ商品。中古セルを買ったと思えばまあ割安だったでしょうか。『GANGSTER ALLEY』は、Atari 2800用ビデオゲームソフトです。内容は、ビルの窓からのぞくギャングを撃つという、当時(83年)にはありがちなゲームです。Atari 2800は、あのアタリショックを引き起こしたAtari 2600(Video Computer System/VCS)のバージョンアップ版。といっても性能は変わらず、木目模様からクールな外観へとデザインの変更が行なわれたバージョンです。Atariの古いゲーム機をお持ちの方には、なんてことはないのですが、私はもっていませんので新鮮な感じがします。解像度的には、カセットビジョンとSG-1000の中間ぐらいでしょうか。そのためFCが発売されていた時期のものにしては、古臭いです。内容は、日本向けにローカライズしたものではなく、あちら仕様のものにAtari 2800用とシールを貼っただけのもの。英語マニュアルと日本語版マニュアル、当時のカタログが付いていました。紙箱やマニュアルの感じは、FCより初期MSX1に似た雰囲気です。ソフトがあるということは、ひょっとして・・・と必死に探したのですが、さすがにそれは無理でした。本体がないのでコレクション的な意味は全くありませんが、ほんのちょっとだけあの頃の空気を感じることはできました。
Atari 2800ソフト・GANGSTER ALLEY・(中古/SPECTRAVIDEO) 100円
DVD・スターウォーズⅢ・シスの復讐・(中古/20th FOX) 700円
スターウォーズDVDは、レンタルアップ商品。中古セルを買ったと思えばまあ割安だったでしょうか。『GANGSTER ALLEY』は、Atari 2800用ビデオゲームソフトです。内容は、ビルの窓からのぞくギャングを撃つという、当時(83年)にはありがちなゲームです。Atari 2800は、あのアタリショックを引き起こしたAtari 2600(Video Computer System/VCS)のバージョンアップ版。といっても性能は変わらず、木目模様からクールな外観へとデザインの変更が行なわれたバージョンです。Atariの古いゲーム機をお持ちの方には、なんてことはないのですが、私はもっていませんので新鮮な感じがします。解像度的には、カセットビジョンとSG-1000の中間ぐらいでしょうか。そのためFCが発売されていた時期のものにしては、古臭いです。内容は、日本向けにローカライズしたものではなく、あちら仕様のものにAtari 2800用とシールを貼っただけのもの。英語マニュアルと日本語版マニュアル、当時のカタログが付いていました。紙箱やマニュアルの感じは、FCより初期MSX1に似た雰囲気です。ソフトがあるということは、ひょっとして・・・と必死に探したのですが、さすがにそれは無理でした。本体がないのでコレクション的な意味は全くありませんが、ほんのちょっとだけあの頃の空気を感じることはできました。