日本近代文学の森へ (115) 志賀直哉『暗夜行路』 3 祖父と父 「前篇 序詞(主人公の追憶)」その3
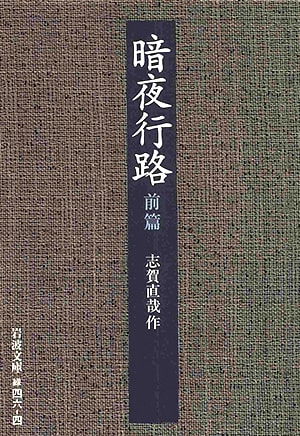
2019.6.14
根岸の家では総てが自堕落だった。祖父は朝起きると楊子をくわえて銭湯へ出かけた。そして帰るとその寝間着姿で朝餉の膳に向った。
朝寝、朝酒、朝湯が大好きで、それで身上つぶした、とは、民謡「会津磐梯山」の一節だが、ぼくはこの歌詞を幼い頃に知って、片時も忘れたことはない。朝寝はともかく、朝湯、朝酒は、ぼくにとっては極悪非道の行いのごとく心の底に叩き込まれ、いまだに、それをしたことはない。それをやっちゃあオシマイだよと、心のどこかで誰かがいつもいうのだ。
だからこの一節の「自堕落」は、不思議なほどよく分かる。朝起きると──それもきっとさんざ朝寝して遅く起きるということだろうが──「楊子をくわえて銭湯へ出かけ」る祖父は、まさに「自堕落」の極地である。ちなみに、楊枝を加えて外を歩くという行為は、ぼくにはどうにも容認できない。よく居酒屋かなんかから「楊枝をくわえた」オヤジが出てくるが、ぼくはいつも目をそむけてしまう。それは別に「自堕落」といった類いのものではないが、なんだか品がない。
まして朝湯から帰った祖父が「寝間着姿で」朝食の膳に向かうなど、自堕落にもほどがあるというものだ。
ぼくは横浜の下町の職人の家に生まれたけれど、どういうわけか「品よく」育ったらしく、そうした下町にありがちな生活態度には本能的な嫌悪感を持っているわけだが、思えばそうした「自堕落」さは、職人とは無縁なのかもしれない。
まあ、それはそれとして、主人公が祖父に対してもった嫌悪感は、こうした記述の端々から感じられておもしろいのだ。
その祖父に家には、種々雑多な人間が集まってきて、「花合戦」をする。つまりは花札だ。これもなんだか下卑ている。またまた私事で恐縮だが、我が家には、「賭け事」の匂いもなかった。祖父からも父からも、また我が家に雇われているペンキ職人の誰からも、「賭け事」の話を聞いたことがない。家庭内で、ちょっとしたことで「賭ける」ことすら皆無だった。そのためか、ぼくはパチンコを数回やったほかは、一度も「公営ギャンブル」にすら手を出したことがない。宝くじ一枚買ったことがないのだ。だから、主人公の祖父の家で、日ごとにわけのわからない連中が集まって「花札」をやっているなんて、ぼくには無縁の世界だ。
そういえば、都立高校に勤めていたころ、修学旅行の引率で京都へ向かう新幹線の車内で、生徒達が花札をやってるのを見つけて驚愕したことがある。ぼくは慌てて、やめろ! と叫んだが、生徒たちはぽかんとして、どうしてトランプはよくて花札はダメなんですか? と聞いてきた。それにぼくがどう答えたか忘れたが、そんな品のないことはやめろと言ったかもしれない。
来る客も変った色々な種類の人間が来た。殊に花合戦をする、その晩には妙な取合せの人々が集まって来た。大学生、それから古道具屋、それから小説家(?)、それから山上さんと皆がいっている五十余のちょっと未亡人らしい女などであった。この女はその頃の医者が持ったような小さい黒革の手さげ鞄を持って来た。それには、きまって沢山な小銭と、一揃いの新しい花札と太い金縁の眼鏡とが入っていたそうである。しかしこの女は未亡人ではなく、その頃大学で歴史を教えていた或る年寄った教授の細君で、この女の甥がかつてお栄と同棲していた、その縁故で、良人に隠れて好きな遊び事のために来たのだということである。その甥という男は大酒飲みで、葉巻のみで、そして骨まで浸み貫った放蕩者で、とうとうその二、三年前にほとんど明かな原因なしに自殺してしまったという事を私は二十年ほどしてお栄から聞いた。
これが「根岸の家」だ。得体のしれない人間ばかり。こういう人間たちに対して、主人公が相容れないものを感じていたのだ。けれども、「お栄」だけは違った。
お栄は普段少しも美しい女ではなかった。しかし湯上りに濃い化粧などすると、私の眼にはそれが非常に美しく見えた。そういう時、お栄は妙に浮き浮きとする事があった。祖父と酒を飲むと、その頃の流行歌を小声で唄ったりした。そして、酔うと不意に私を膝へ抱き上げて、力のある太い腕で、じっと抱き締めたりする事があった。私は苦しいままに、何かしら気の遠くなるような快感を感じた。
私は祖父をしまいまで好きになれなかった。むしろ嫌いになった。しかしお栄は段々に好きになって行った。
主人公の「性の目覚め」だろう。普段は少しも美しい女ではないのに、「湯上りに濃い化粧などする」と急に美しくなる女。5、6歳の男の子が、そんなことに気づくものだろうかという疑問は残る。それは急に抱きしめられた快感から遡った後付けの印象なのだろうか。
祖父は最後まで「好きになれなかった」、そしてお栄は「段々に好きになって行った」。では父はどうだったのか。ここで、父とのエピソードが印象的に語られる。
「根岸の家へ移って半年余り経った或る日曜日か祭日かの事であった。」というのだから、主人公がやはり5、6歳の頃だ。久しぶりに祖父に連れられて本郷の父の家にいった主人公は、珍しく機嫌のいい父と角力をとることになる。
「どうだ、謙作。一つ角力をとろうか」父は不意にこんな事をいい出した。私は恐らく顔一杯に嬉しさを現わして喜んだに違いない。そして首肯いた。
「さあ、来い」父は坐ったまま、両手を出して、かまえた。
私は飛び起き様に、それへ向って力一ぱい、ぶつかって行った。
「なかなか強いぞ」と父は軽くそれを突返しながらいった。私は頭を下げ、足を小刻みに踏んで、またぶつかって行った。
私はもう有頂天になった。自身がどれほど強いかを父に見せてやる気だった。実際角力に勝ちたいというより、私の気持では自分の強さを父に感服させたい方だった。私は突返されるたびに遮二無二ぶつかって行った。こんな事は父との関係ではかつてなかった事だ。私は身体全体で嬉しがった。そして、おどり上り、全身の力で立向かった。しかし父はなかなか私のために負けてはくれなかった。
なぜか幼稚園か小学生のころの父とのことを思い出す。正月だったのか、夏休みだったのかまったく覚えていないのだが、何かの遊びを父としていたぼくは嬉しさのあまり、キャッキャと声を挙げて笑ったようだ。それを聞いた祖母が「ほらこんなに喜んでいるじゃないか、お前ももっと遊んであげな。」というようなことを父に向かって言った。その祖母の言葉をはっきりと覚えているのだ。
父はペンキ屋の親方として忙しい日々で、ぼくと家で遊ぶというようなことはめったになかった。だから、何の遊びかしらないが、珍しく父が相手をしてくれたことがぼくにはひどく嬉しかったに違いないのだ。父が遊び相手になってくれるということが、子供にとってどんなに嬉しいことかということを、その祖母の言葉によってぼくは初めて気がついたのかもしれなかった。けれども、そんな嬉しい時間は、その後、二度となかったような気もしている。その祖母の言葉を聞いたぼくが、なぜかひどく悲しい気分になったような気がするからだ。
いわば自分を捨てた父が、思いがけず「角力をとろう」と言ってくれたことに主人公がどんなに喜んだか、この一節は、その子供の気持ちを実に見事に描いている。「私は身体全体で嬉しがった。」というような稚拙とさえ言える表現をも辞さないで志賀直哉はその喜びを描く。
しかし、その喜びがいつしか憎しみへと変わっていく。そこの描き方も実に見事なものだ。長いが引用しておく。
「これなら、どうだ」こういって父は力を入れて突返した。力一ぱいにぶつかって行った所にはずみを食って、私は仰向け様に引っくりかえった。ちょっと息が止まる位背中を打った。私は少しむきになった。そして起きかえると、なお勢込んで立向かったが、その時私の眼に映った父は今までの父とは、もう変って感じられた。
「勝負はついたよ」父は亢奮した妙な笑声でいった。
「まだだ」と私はいった。
「よし。それなら降参というまでやるか」
「降参するものか」
間もなく私は父の膝の下に組敷かれてしまった。
「これでもか」父はおさえている手で私の身体をゆす振った。私は黙っていた。
「よし。それならこうしてやる」父は私の帯を解いて、私の両の手を後手に縛ってしまった。そしてその余った端で両方の足首を縛合せてしまった。私は動けなくなった。
「降参といったら解いてやる」
私は全く親みを失った冷たい眼で父の顔を見た。父は不意の烈しい運動から青味を帯びた一種殺気立った顔つきをしていた。そして父は私をそのままにして机の方に向いてしまった。
私は急に父が憎らしくなった。息を切って、深い呼吸をしている、父の幅広い肩が見るからに憎々しかった。その内、それを見つめていた視線の焦点がぼやけて来ると、私はとうとう我慢しきれなくなって、不意に烈しく泣き出した。
父は驚いて振り向いた。
「何だ、泣かなくてもいい。解いて下さいといえばいいじゃないか。馬鹿な奴だ」
解かれても、まだ私は、なき止める事が出来なかった。
「そんな事で泣く奴があるか。もうよしよし。彼方へ行って何かお菓子でも貰え。さあ早く」こういって父は其処にころがっている私を立たせた。
私は余りに明ら様な悪意を持った事が羞かしくなった。しかし何処かにまだ父を信じない気持が私には残っていた。
祖父と女中とが入って来た。父は具合悪そうな笑いをしながら、説明した。祖父は誰よりも殊更に声高く笑い、そして私の頭を平手で軽く叩きながら「馬鹿だな」といった。
小学生などが、ふざけてじゃれ合っているうちに、だんだん本気になってきて、とうとう激しい喧嘩になってしまうということがよくあるが、それに似ている。似ているがまったく違う。それは、主人公と父との間に決定的な溝があるからである。
ずいぶん後になって明かされることだが、謙作は、実は祖父と母との間にできた不義の子で、この父とは血のつながりがないのだ。この父にすれば、謙作はどうしても愛することのできない子供なのだ。たまに遊びにきた謙作に「角力をとろうか」と愛想を言うことはできても、とことん謙作の相手になって遊んでやることができない。謙作が、ムキになってかかってくればくるほど、心の中からは憎しみの感情が湧き出てしまう。謙作はそんなことはまったく知らないから、夢中になって父に向かって行く。ただ自分の強さを父に見せたいために。けれども、父の意外な反応に驚く。「その時私の眼に映った父は今までの父とは、もう変って感じられた。」のである。
こともあろうに自分の妻と自分の父が過ちを犯し、不義の子を産んだ。そのことの耐えがたさに、子供を手放すが、それでも自分の父ゆえに、義絶することもできず、その子供がこうして遊びにくれば相手もしてやらざるをえない。けれども、その子供に対するわだかまりは、子供への冷たい仕打ちとなってしまう。苛立ちは子供への暴力となる。なんともやるせない話だ。
そこへ入ってきた祖父にむかって、「具合悪そうな笑いをしながら、説明」する父。それを聞いて「誰よりも殊更に声高く笑」う祖父。「私の頭を平手で軽く叩きながら『馬鹿だな』」という祖父。
ほどきようもない感情のもつれのまっただ中に成長していく主人公。その主人公、時任謙作は、その後どのような人生を歩むことになるのか。「序章」はここで終わり、いよいよ「第一」に入っていく。
引用出典「暗夜行路 前篇」岩波文庫 2017年第11刷

















