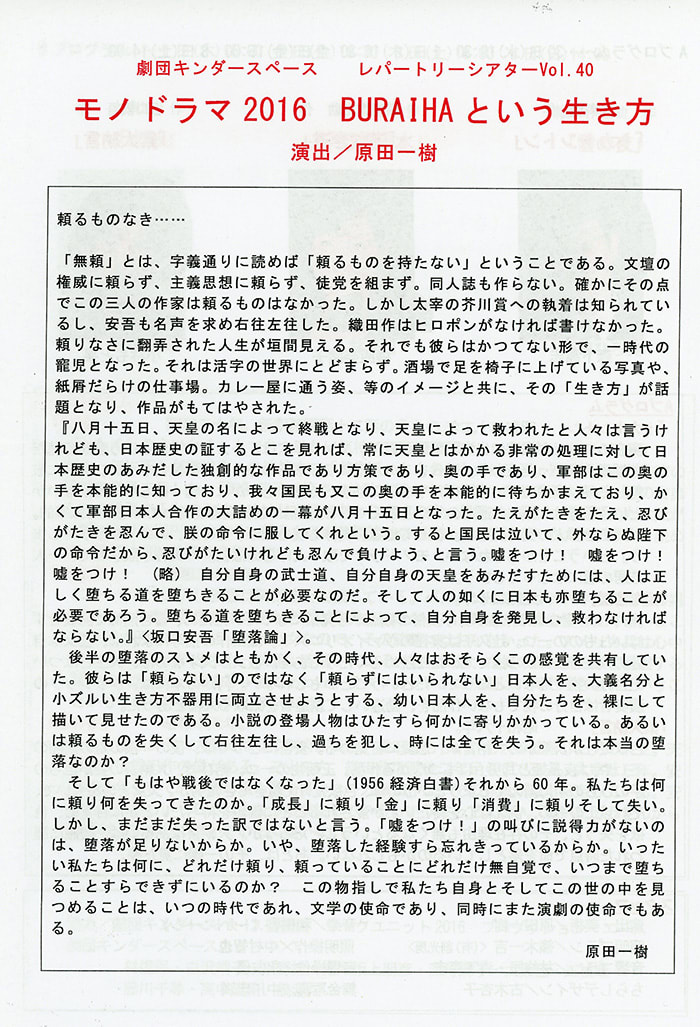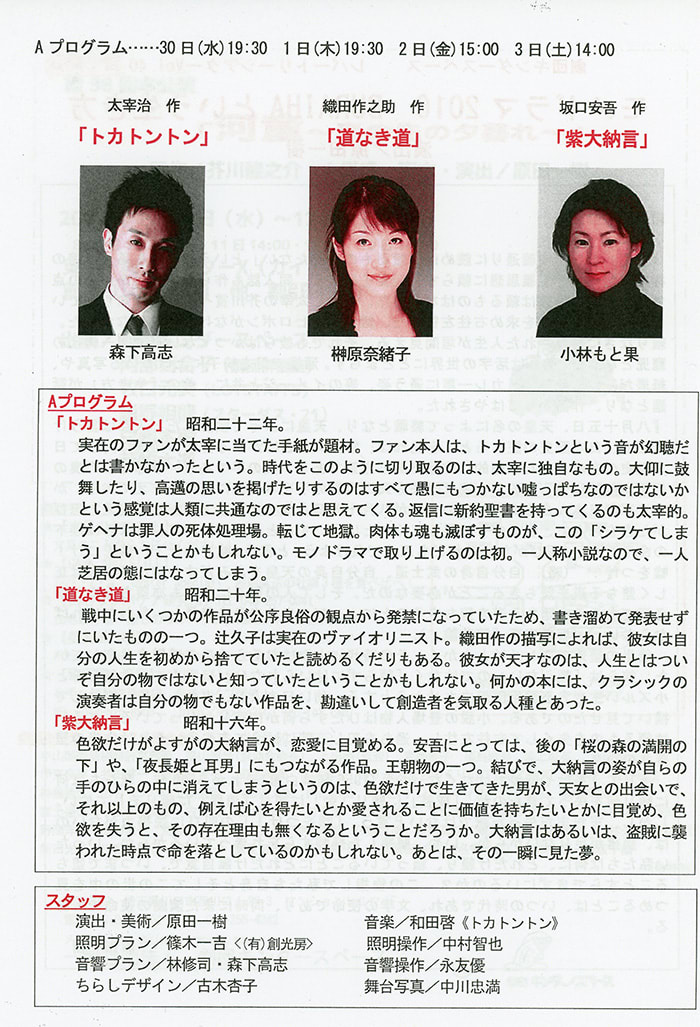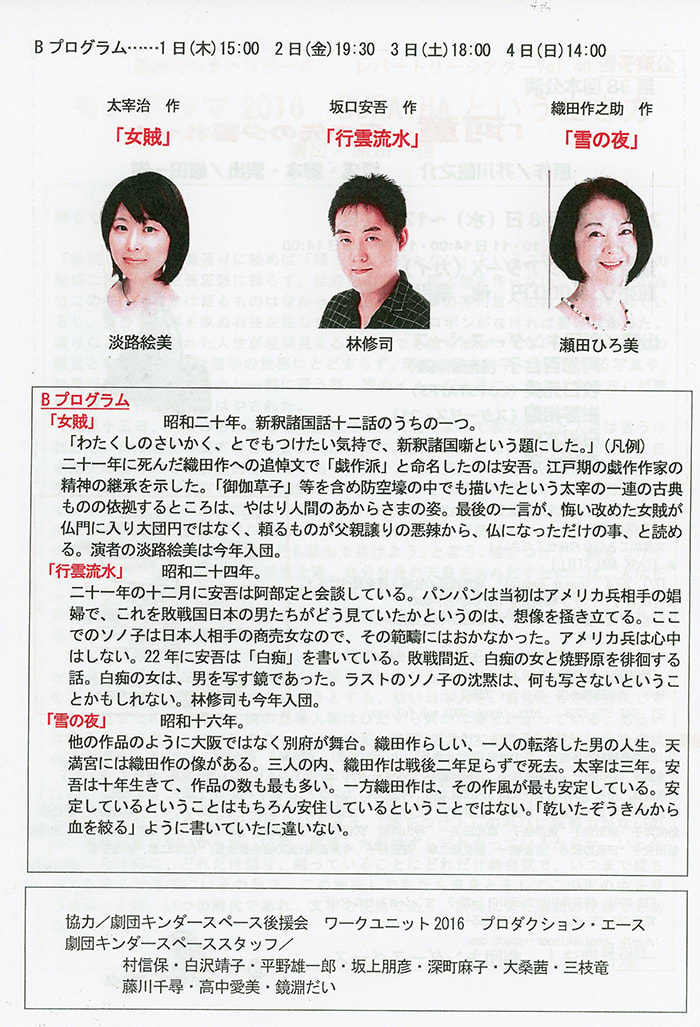木洩れ日抄 10 「モノドラマ」の魅力──文学と演劇の間に

2016.12.5
劇団キンダースペースのモノドラマを最初に見たのはいつだったのだろう。キンダースペースの公演記録によれば、最初に「モノドラマ」が出てくるのが2004年のことだから、最初から見たとして(見ていない可能性も高いが)10年以上も前のことになる。キンダーは、12年の長きにわたって、このキンダーだけのオリジナルな演劇の形式「モノドラマ」を上演し続けてきたことになる。なぜ、それほどまでにキンダーは「モノドラマ」にこだわり続けてきたのか、主宰の原田さんに直接に質問したことはないが、今回の「モノドラマ」を見ながら、自分なりに何となく分かったような気がしている。
原田一樹は、今回の公演チラシに、「戯曲が『戯(たわむ)れ曲(くせ)を尽くすこと』だとすれば、モノドラマとは言うまでもなく、戯曲に頼ること無しに文学と戯れる演劇である。」と記している。今回の「モノドラマ」のテーマが「BURAIHA(無頼派)という生き方」だったので、「戯曲に頼ること無しに」としたのだろうが、ぼくは、初めて「モノドラマ」の定義を原田さんから聞いた気がした。そうか、そういうことか、とぼくなりに納得するところがあった。以下は、ぼくなりの勝手な解釈である。
「戯曲に頼る演劇」とは、それではなにか。言うまでもなく、普通の演劇はみな「戯曲」があって、それを演ずる。つまり戯曲に「頼っている」わけである。戯曲には、すべての語られるべき「セリフ」が書かれており、演じられるべき行為までもが書かれていることもある。演出家は、それらのセリフとト書きに対して、もちろん「頼り切る」のではなく、自らの解釈を投入してひとつの芝居を作り上げていく。演者は、自分に与えられたセリフを、演出家の要求や自らの工夫の中で咀嚼し、舞台にのせていく。演者は、自らの役になりきればよい。もちろんそれは容易なことではないが、役を演じるだけでいいというのは、「モノドラマ」に比べれば「楽」である。
「モノドラマ」は、見たことのない人にはイメージしにくいだろうが、ある小説を、一人で演じる。「戯曲化した小説」ではなくて、小説をじかに演じるのだ。当然複数の登場人物が出てくることが多いわけだから、それを演じ分けなければならない。しかも、「地の文」も語るのだ。いわゆる「一人芝居」というものとはその辺が違うのではなかろうか。ぼくは、「一人芝居」をあまり多く見たことがないので、はっきりしたことは言えないが、「一人芝居」は、多くの場合、一人称の、一人語りではなかろうか。
「モノドラマ」は、「一人芝居」より、むしろ落語に近いと言えばいいだろうか。ただし、落語は、原則座布団の上に座ったまま演じるものだから、そこが違う。(もっとも、古くは落語にも簡単な舞台装置で芝居の一部を語り演ずる形式があったわけだが、今はほとんど演じられない。)
形式の面からいえば、「一人芝居」でもなく「落語」でもなく「朗読」でもない。やはり独自な形式を持つのが「モノドラマ」なのだ。
それは、最初に見たときから分かっていたことだ。問題は、なぜ「モノドラマ」か、ということだ。落語や、朗読ではなく、なぜ「モノドラマ」でなければならないのかということだ。それはいつも頭の片隅に、何か解決のつかない疑問としてわだかまってきたように思うのだ。その疑問が、今回、氷解した、とまでは言わないが、原田さんの言葉で、何となく分かったということなのだ。
「一人芝居」の場合は、きちんとした戯曲を持つだろう。「一人芝居」としての「戯曲」を劇作家は書く。それに従って演者は演じる。必ずしも一人称の一人語りでなくてもよい。
朗読は、作品を読むわけだから、やはり「戯曲」がある芝居と基本的には同じだ。朗読者は、「与えられた言葉」を、いかにして舞台のうえに表現するかを考えればいいのだ。
「モノドラマ」の本質は、一人で何役も演じるとか、地の文も語るとかいうところには実はない。そうではなくて、演者が、「文学」の本質と直接に向き合い、文学の中から演劇的なものを引きずり出し、自分の力で、文学を演劇化する行為であるということだ。そこでは、演者は、「戯曲」に頼れない。演出家にも頼れない。もちろん演出家はいろいろと口を出すだろう。しかし、それがすべてではない。演者は、自分で文学の中に飛び込んで、何かをつかんでこなければならない。そしてそれを自分で舞台の上に表現し尽くさなければならない。考えてみれば途方もないことだ。
「文学の中から演劇的なものを引きずり出す」と書いたが、それなら「演劇的なもの」とは何か。それを考えていったらきりがないが、それは必ずしも対立や葛藤が生み出す派手な「ドラマ」を意味しないだろう。さしあたり、舞台と観客の間に、緊張や共感を呼ぶもの、とでもいうしかない。
ぼくらは、太宰治や、織田作之助や、坂口安吾やの小説を一人で読んで、十分に感動し、笑うことができる。けれども、小説を読むことと、芝居を見ることとの決定的な違いは、「共感の場」があるかどうかということだ。小説を読むという行為は、原則的には限りなく孤独な行為であって、同時に同じ小説を読むという「場」はない。「モノドラマ」は、観客を前に演じられる芝居である以上、そこにはかならず「共感の場」がある。
その観客を前に、一人の演者が文学を芝居にしてみせる。しかも、朗読とは違って、演者には「自由」がある。動いてもいい。衣装を変えてもいい。二人のセリフを同じ方向を向いてあまり違わない声で言ってもいい。「おまえさん!」と役になりきって言った直後に、そのままの姿勢で、「と彼女は声を殺して言った。」と説明してもいい。この自由さは、演者を苦しめることだろう。だが同時に、演者を、文学と一体化した陶酔に誘い、その陶酔は観客にも伝わるだろう。
「モノドラマ」が、「文学との戯れ」だとしたら、どのように戯れたっていいのだ。その戯れ方が、おもしろいのだから。演者は、自信をもって、戯れ尽くせばいいのだ。その「戯れ」の真剣さが、観客の共感を呼ぶだろう。
常に舞台に生成され続けていくスリリングな演劇。「文学」と「演劇」の間に、奇跡のように生まれる「文学空間」。それが「モノドラマ」なのだ。
完成された「モノドラマ」というものは、ほんとうはない。「モノドラマ」は「完成」など目指さない。文学の本質を、求めつづけ、戯れつづける。そんなものに「完成」などあっていいわけはないのだ。
そうはいっても、今回の公演では、「完成度が高い」と表現するしかない芝居もあった。森下高志の演じた「トカトントン」(太宰治)、瀬田ひろ美の演じた「雪の夜」(織田作之助)の2作だ。
『トカトントン』は、森下の自信あふれる演技によって、これ以上ないと思われる「モノドラマ」の「完成形」を予感させた。音楽も秀逸で、「トカトントン」のメロディーは、これ以外にもう頭に浮かばないだろう。
『雪の夜』は、瀬田ひろ美の圧倒的な表現力によって、「モノドラマ」のもう一つの「完成形」を垣間見せた。まるで映画を見るかのように鮮やかに舞台に浮かび上がる街の情景と人間の心の風景は、いつまでも見ていたいと切実に思わせる魅力で観客の胸にせまった。こんごなんどでも、キンダーのレパートリーとして演じ続けてほしいと願う。
榊原奈緒子の『道なき道』(織田作之助)は、天才と呼ばれるものがいかに背後に血の滲むような努力によって支えられているかを訴える父親の姿がこころにしみた。榊原の澄んだ声は、いつ聞いても耳に快い。
小林もと果の『紫大納言』(坂口安吾)は、最近とみに深みを増してきた小林の声と演技が、あっという間に観客を王朝の世界へと連れ去っていく。小林のつくる舞台の空気は実に独特なものがあり、いつも心ひかれて見入ってしまう。
『女賊』(太宰治)は、入団1年目の淡路絵美が、お姫様から女賊へと変身していく人間のおもしろさを、あっけらかんとした明るさで描いてみせた。深みには欠けるが、なんともいえないポップでユーモラスな感覚が魅力だった。
『行雲流水』(坂口安吾)は、これも入団1年目の林修司が、坂口安吾の戯作魂を軽快に演じてみせた。荒削りだが、落語のような楽しさがまた魅力だった。演技なのか「地」なのか分からない「微笑」に妙に惹きつけられた。
「モノドラマ」を見るたびに、演劇とともに文学のはかりしれない面白さに気づかされる。今では、あまり読まれることもない近代文学に、こうして光を当て続けてくれる劇団は、他にはない。若手の劇団員も次々と入り、ますます充実していくキンダースペースからは今後も目が離せない。