あんてぃーく倶楽部 による清の東陵への遠足、続きです。
道中、一本道なので、薊県の独楽寺と白塔寺にも行きました。
まずは最初の地図でもう一度、位置を確認しておきます。

東陵に向かう途中になるんですねー。

今回は、鼓楼、文廟などには行けませんでしたが、
これも次回のお楽しみということですな。

朝8時前に薊県に到着。
何しろ、朝6時出発でしたからねー。道中、スムーズに到着しました。


朝の通りは、さわやか。
独楽寺もまだ開いていません。

お店が一部、開いていたので、ひやかしに行きます。



クッキー屋さん。紫いものクッキー、おいしそうですね。
こちらでは、市場でもよく紫いもが売っていて、この派手な色を見ても、そんなに不気味には感じません。

独楽寺がまだ開いていないので、まずは白塔寺に行きます。
両方とも今では、貴重な遼代の建物。白塔寺はもともと、独楽寺の一部だったとのこと。
これから歩いて行く小道は、すべて独楽寺の伽藍の中だったということですねー。
けっこう巨大な敷地だったということですね・・・。

小道の中に入って行くと、一昔の北京の胡同を行くようですねー。懐かしい・・・・。

お! 出ました! 省エネ型湯沸かし器!
これ便利なんですよー。
真ん中がドーナツ型に空いていて、そこに燃えるものを何でも入れて燃やせばいいんですが、
周囲からぐるりと、すべての熱源を無駄なく吸収できるので、少ない燃料ですぐにお湯がわくんですー!
東日本の震災の直後、これをたくさん被災地に送ったら、絶対役にたつ! と思ったものです。


こちらは、これから建て替える家。それにしても敷地が巨大だ!

お! 白塔が見えてきましたよー!




白塔寺が、独楽寺と一体だったということを1932年に建築家の梁思成がお墨付きを出した、と書いていますね。
京都をアメリカから守ってくれたけど、北京を守ることができなかった、といわれる人です・・・。
10代初めまで日本で育った、日本とも縁の深い人ですね。

白塔寺の入口

白塔寺の入口には、占いのお店がありますね。
さすが、ニーズに応えているというか・・・。
お寺の中にも、妙齢の美しい娘さんが、何かを思いつめたように熱心にお参りしていました。
こちらのお参りは、両ひざをついて、頭まで地面につけますからね。
やはり何か強い思いがあるのでしょうな。
そんな人には、出口を出たところに、ちょうど悩める人を導く店構え・・・。


入ったところ。境内。

さああー。
いよいよ塔ですー。

説明に「インドのストゥーパと中国の伝統建築様式を融合させた、国内で現存する塔の中ではめずらしい様式」
とありました。
私は普段、明清代が専門なので、その時代のものと比べると、
まさに南アジアの匂いがプンプンして、中国に染まっていないー! と感じます。

「諸法因縁生 我説是因縁」(諸法、縁のために起き、 これこそ因縁なり) ・・・ですかね。

各伽藍の名前が載っているので、一応チェック


石碑は、何も書いていないように思えるが・・・?
文革の時に削られてしまったとか? 謎です。















塔の裏は、「塔後胡同」ですって。
白塔寺を見終わった頃には、そろそろ独楽寺も開く時間となったので、
再び、独楽寺の前まで戻ります。


きっぶ売り場も「清代の民居」だそうな。


お!
来る前にちらりと見た百度百科で、和[王申]の墓の前に
あった狛犬のペアが、独楽寺に移された、と書いてあったので、どれかと思っていたら、
これだったのね!
和[王申]のものなら、数百年はたっているはずで、え、えらいきれいすぎはしないかい??
しかも誰や。目ん玉に赤いペンキを塗った阿呆は。
独楽寺の中には、ほかにも何対かの狛犬がいるので、一応、すべて写真は撮ってきたが、
一番可能性が低く思えたこの一対でしたかー。
和[王申]の墓は、元々、薊県に建てられていたそう。
しかし墓に入る前に罪を得て死刑になったので、そんな立派な墓に入ることは許されず、今は昌平の小さな土饅頭に埋葬されている。
薊県の巨大な墓の跡は、今はダム湖の下に沈んでいるそうだ。


独楽寺も白塔寺と同じで、創建は遼代。
お寺自体は隋代から続くとのこと。

この山門の看板は、明代の厳崇の文字だそう。
厳崇といえば、時代劇のドラマでは、悪役で登場することも多い宰相だが、いずれまた詳しく知りたい人物やわー。

見取り図があったので、とりあえず、押さえておきまひょ。

山門の壁画
なかなかみごとですが、これは清代のものだそう。
山門と観音殿(巨大観音様のいる本殿)は、遼代のもの、その他の建築は明清代のもの。
ぎゃああ。
今、説明を見たら、山門の金剛力士像は、遼代のオリジナルですって。
わたしったら、なぜ写真を撮らなかったんだろう??
うううー。
中国では、古い金剛力士像が残っているところが少なく(特に北京周辺は)、
今、作りました、といわんばかりのけばけばしい科学塗料で塗装した軽薄で安っぽい新品をおいているお寺がほとんど。
だから入口の金剛さんには、あまり興味を示さなくていい、と頭にすりこまれていたのがいかんかった・・・。
ちらりと見た時、色が渋いなああ、とは思ったものの、まさか遼代のオリジナルとは・・・。
・・・・また今度、訪れる時の楽しみにとっておきましょう・・・。
・・・・とあきらめの境地だったのですが、この記事を出してから、なんと当日ごいっしょした会員の方が
ご自分が撮影されていたお写真をくださいました(涙)!
ありがとうございます!


こうして改めて見ると、やっぱり渋いですねー。
節くれだった腕といい、まんまるな乳首といい、なんだかえらい個性的・・・・。

こちらが観音殿。
残念ながら、中は撮影禁止。巨大な観音像はみごとの一言。

せめてネットでみつけた画像を一枚。
出典 は、掲示板。
おそらく貼った人もどこかから引っ張ってきたものなんだろうけど・・・。
そう。
こんな感じで、見上げるような巨大さ。
上に階段で上がることもでき、窓からは、ちょうどお顔が見えるようになっているのだと思う・・。





扁額は、咸豊帝(西太后のだんな)の筆によるものだそう。
敷地内に行宮があるから、乾隆以降の皇帝は、お墓詣りのたびにここに立ち寄ったということですな。
前述の建築家・梁思成は、独楽寺を見て、「濃厚な唐風建築の特徴がある」といい、当初は唐代の創建なのではないか、と考えたという。
その後、敷地内の最も時代の早い石碑が遼代のものであり、そこに建築物を「再建」したとあるため、現存するものは遼代と判明した。
しかし確かに建築様式は、唐代のものを踏襲しているのかもしれない。
伊勢神宮の式年遷宮ではないが、人々の記憶のあるうちに、まったく同じものを建てると、その姿形は、そのまま伝わるということがある。
うろ覚えだが、確か司馬遼太郎の『街道を行く』シリーズに、「なぜ東大寺には雨どいがない」という内容があり、
歴史上、何度も焼け落ちて再建されたのに、いまだに雨どいがない理由について、東大寺のお坊さんが「昔からそうだったから」と答えたとか。
中国の伝統建築には雨どいがなく、その後、日本で独自に加えたものなのだそうだが、
東大寺は中国から帰ってきた僧侶が大陸の様式を忠実に再現した初期の建築物であり、すでにその存在自体が権威になってしまった。
だからオリジナルが何度焼け落ちても、人々の記憶が残っているうちに再建を繰り返し、
善きも悪きもすべて含めて、改善を加えることなく、様式がそっくりそのまま受け継がれたらしい。
・・・そういうことが、この独楽寺の本殿にも言えるのかもしれない・・・。

右側に乾隆帝の行宮が見えます。

なんだか迫力あるたたずまいの木だと思ったら、千年を超す樹齢ですってー。
すごいー。

巨大な観音様の後ろには、韋駄天さまを祭った亭があります。




後ろから見た図。
建物と韋駄天像は、ともに明代のもの。
明代、行脚僧にとって、境内内の韋駄天像のポーズは、一つの暗号になっていたという。
像が合掌をしていれば、行脚僧の滞在を歓迎するという意味であり、何日でもただ食いただ泊まりをしてよかった。
逆に像が棍棒をむんずと持って、仁王立ちになっていれば、「来るな」という意味だそうだ。
北京周辺でオリジナルの仏像や塑像が残っているところは、きわめて珍しい。
大躍進の時、派手に溶解炉に放り込み、鉄(銅もすべていっしょくたに)の塊にされてしまったのだと聞いた。
こうしてたまに古いオリジナルに出くわすことができると、やはり感動する・・・・。
文物保護の面でも、梁思成の貢献があるという。
1966年、文化大革命が勃発すると、各地の寺院が破壊を受けた。
梁思成は、危険を冒して薊県にやってくると、現状を調査。
観音殿に避雷針をつけ、窓を設置すべし、と国家文化部から9000元の予算を取ることに成功した。
1976年に起きた唐山の大地震の際は、観音殿の壁の一部が崩れ落ちたが、
建物の柱はびくともせず、観音様もまったく無傷だった。
縦に高くそびえる巨大な観音像と、それを取り囲むように立つ、同じく高層の観音殿が、歴代の大地震にも耐え、
びくともしなかったことに、改めて注目が集まった。
以来、それが新たな研究課題となっているのだという。

報恩殿

この時点では、どの狛犬が和[王申]の墓にあったものがわからぬので、とりあえずすべての狛犬を撮っておいたのよ。
「報恩院」の扁額は、咸豊帝(西太后のだんな。何度も強調してごめんよ。でも事実だし、それがわかりやすいんだよ)の筆によるものだそうだ。
・・・しかしなんだかぴかぴか過ぎないかい???
たとえ、分厚く塗り込めた塗料の下には、本物のオリジナルがあるのだとしても、
こういう風情を台無しにした修復の仕方は、やっぱりしらけるわー。


この歯の欠け具合といい、鼻のもげ具合といい、打倒された汚職官僚の末路を如何にも現しておらんかね??
・・・などと、勝手に妄想しつつ・・・。
しかしどうやらはずれなようですね。表玄関の二頭が正解。
こちらの鼻もげは、無駄ということ???

三世仏殿

石碑があると、反射的に写真を撮ってしまうが、どうも様子がおかしい。
石碑が立派すぎるのだ。
奥の仏殿を覗いて見ると、遼代や明代の渋いオリジナルを見た目には、久しぶりに安っぽいけばけばしい仏像が異様さを持って目に飛び込んできた。
どうやらつい最近、人々がお布施を出し合って、新たに仏像を寄付し、それを記念する石碑のようだ。
ケバい仏像さんたちは、撮る価値ないので、残念ながら、証拠写真なし(爆)
最後に、ずっと気になっていた乾隆帝の行宮の方へどんどん行きまひょ。




当初は、この狛犬セットが本命だと思ってましたよ!
しかし残念ながら、これもはずれ。
…確かに言われて見ると、国家予算10年分以上を溜めこんでいた和[王申]さまの陵墓の前に置かれる狛犬としては、
ちいと小さすぎるんですな。
まあ。いいでしょう。
久しぶりに狛犬をたくさん撮った、というのも・・・。

私たちが東陵に行くのに、薊県に立ち寄ったのと同じように、
清の皇帝たちも、東陵に行く途中の宿泊所として、この伽藍の中に行宮を作ったということである。
乾隆18年(1753年)創建。
天津地区で現存する唯一の行宮でもある。
残っていたのは、この正殿のみだったが、現在は回廊十四間分も復元。


碑文は、乾隆帝が王羲之や顔真卿などの歴代の名書家の文字を真似て書いたもの。
石碑は、清代のオリジナル。それを壁の中に塗り込めて回廊にしている。
壁に塗り込める、という形式は、恐らく乾隆帝がやったものではなく、現代の文物局の人のアイデアなんだと思う(笑)。
乾隆帝本人の自作の詩は、ごく少ないが、いくらか混ざっているらしい。
中国語ブログ 一蓑居的博客 さんが、その解読を試みている。
しかし中国の知識人にも、すーっとすぐに解読できるものではないらしく、いろいろとあーでもないこーでもない、
現場で同行者が間違った解釈をしていた、ネットで調べたら、唯一出てきたブログもあまり解説していない、とぶつぶつ言いながらの試み。
ぎゃあああ。
すみません。予約機能にセットしたまま、この数日のうちに訳そうと思っていたら、
時間切れで訳さないまま、アップされてしまいました・・・。
今、時間が取れないので、このまま中国語のままにしてしまいます。。。。
また時間が取れたら、訳します。
最新記事でお知らせを出しますので、あしからずー。
緑雲紅雨日逡巡 绿云,比喻树叶茂盛;红雨,比喻落花,或特指桃花,
李贺《将进酒》诗有“况是青春日将暮,桃花乱落如红雨”。
树叶长得茂盛,落花如雨乱飞时,正是阳春四月间。
逡巡,有两义,一是迟疑徘徊,欲行又止;一是顷刻,不一会意。
这里应是后义,说每天都变得很快。——绿树如云,落花如雨的季节,每天都有变化。
又見楊花点玉津 玉津,玉津园,北宋京城汴梁南门外的名园,园内外遍植杨柳。
杨花,也即柳絮,古时柳树也叫杨树。——又看到杨花柳絮点点飘飞到玉津园的时候了。
两句写春天景象:如云的绿树,如雨的落花,空中飞舞着柳絮杨花。
绿的、红的、白的颜色,以鲜艳的色彩绘出春天美景。
未谱豳风歌七月 豳风,《诗经》里十五《国风》(民歌)之一。
豳,古地名,今陕西彬县、旬邑一带。《豳风》中最长的一首诗叫《七月》。
诗中开头和反复用以起兴的句子是“七月流火,九月授衣”。
秋天(七月)开始了,天气转凉了。气温正和春末差不多。——不是唱《豳风》中《七月》歌的季节。
却看北地殿三春 三春,春天分孟春、仲春、季春三月。殿,在最后。
这里指春末。——眼前看到的是北方佛庙里的暮春景象。
纷如道韫诗中雪 道韫,谢道韫,晋代著名的才女,著名能臣谢安的侄女。
一次下雪,谢安问,“白雪纷纷何所似?”谢安的侄子谢朗说,“散盐空中差可拟?”
道韫说,“未若柳絮因风起。”谢安听了非常高兴。后人就称谢道韫为“咏絮才”。
——纷纷飘飞的是谢道韫诗中比喻雪的柳絮。
污比元规扇上尘 “元规尘”,也是个典故,
《世说新语》《轻詆》:“庾公(亮)权重,足倾王公(导)。
庾在石城,王在冶城。坐大风扬尘,王以扇拂尘,曰:‘元规尘污人。’”
元规,庾亮的字。比喻人的声势逼人。诗句意——它的污浊烦人,犹如元规掀起的尘土。
两句写杨花漫天飞舞的特点,也写了它带给人们的感受——烦恼。
每对清和赋云汉 清和,天气清明和暖,暮春初夏天气,多指四月,即诗中所写时间。
云汉,天河。——每当晴朗的夜晚,仰视天河赋诗。
长空宛转越愁人 看天河,自然要想到牛郎织女的故事,他们是到七月七日才渡鹊桥相会的呀。
——看万里长空蜿蜒曲折的银河,真为等待跨越的牛郎织女发愁啊!
写对夜空的想象,对时间的感慨。
全诗以杨花(柳絮)为中心,写出春天的美好景致,温暖宜人的天气,又有一点“镇日惹飞絮”的烦恼。由白天写到夜晚,想到牛郎织女的盼望相会,表达了对他们的同情。做为皇帝,能有这样的人情味,倒也难能可贵。最后两句,如果从皇帝身份角度去考虑,也可说是对治理国家艰难的感叹。清和,可指政治清明天下太平。——每当要做使国家太平繁荣的文章,想到长路漫漫,欲达到目的可就太难了!



ぽちっと押してくださると、励みになります!

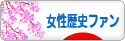
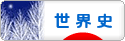
道中、一本道なので、薊県の独楽寺と白塔寺にも行きました。
まずは最初の地図でもう一度、位置を確認しておきます。

東陵に向かう途中になるんですねー。

今回は、鼓楼、文廟などには行けませんでしたが、
これも次回のお楽しみということですな。

朝8時前に薊県に到着。
何しろ、朝6時出発でしたからねー。道中、スムーズに到着しました。


朝の通りは、さわやか。
独楽寺もまだ開いていません。

お店が一部、開いていたので、ひやかしに行きます。



クッキー屋さん。紫いものクッキー、おいしそうですね。
こちらでは、市場でもよく紫いもが売っていて、この派手な色を見ても、そんなに不気味には感じません。

独楽寺がまだ開いていないので、まずは白塔寺に行きます。
両方とも今では、貴重な遼代の建物。白塔寺はもともと、独楽寺の一部だったとのこと。
これから歩いて行く小道は、すべて独楽寺の伽藍の中だったということですねー。
けっこう巨大な敷地だったということですね・・・。

小道の中に入って行くと、一昔の北京の胡同を行くようですねー。懐かしい・・・・。

お! 出ました! 省エネ型湯沸かし器!
これ便利なんですよー。
真ん中がドーナツ型に空いていて、そこに燃えるものを何でも入れて燃やせばいいんですが、
周囲からぐるりと、すべての熱源を無駄なく吸収できるので、少ない燃料ですぐにお湯がわくんですー!
東日本の震災の直後、これをたくさん被災地に送ったら、絶対役にたつ! と思ったものです。


こちらは、これから建て替える家。それにしても敷地が巨大だ!

お! 白塔が見えてきましたよー!




白塔寺が、独楽寺と一体だったということを1932年に建築家の梁思成がお墨付きを出した、と書いていますね。
京都をアメリカから守ってくれたけど、北京を守ることができなかった、といわれる人です・・・。
10代初めまで日本で育った、日本とも縁の深い人ですね。

白塔寺の入口

白塔寺の入口には、占いのお店がありますね。
さすが、ニーズに応えているというか・・・。
お寺の中にも、妙齢の美しい娘さんが、何かを思いつめたように熱心にお参りしていました。
こちらのお参りは、両ひざをついて、頭まで地面につけますからね。
やはり何か強い思いがあるのでしょうな。
そんな人には、出口を出たところに、ちょうど悩める人を導く店構え・・・。


入ったところ。境内。

さああー。
いよいよ塔ですー。

説明に「インドのストゥーパと中国の伝統建築様式を融合させた、国内で現存する塔の中ではめずらしい様式」
とありました。
私は普段、明清代が専門なので、その時代のものと比べると、
まさに南アジアの匂いがプンプンして、中国に染まっていないー! と感じます。

「諸法因縁生 我説是因縁」(諸法、縁のために起き、 これこそ因縁なり) ・・・ですかね。

各伽藍の名前が載っているので、一応チェック


石碑は、何も書いていないように思えるが・・・?
文革の時に削られてしまったとか? 謎です。















塔の裏は、「塔後胡同」ですって。
白塔寺を見終わった頃には、そろそろ独楽寺も開く時間となったので、
再び、独楽寺の前まで戻ります。


きっぶ売り場も「清代の民居」だそうな。


お!
来る前にちらりと見た百度百科で、和[王申]の墓の前に
あった狛犬のペアが、独楽寺に移された、と書いてあったので、どれかと思っていたら、
これだったのね!
和[王申]のものなら、数百年はたっているはずで、え、えらいきれいすぎはしないかい??
しかも誰や。目ん玉に赤いペンキを塗った阿呆は。
独楽寺の中には、ほかにも何対かの狛犬がいるので、一応、すべて写真は撮ってきたが、
一番可能性が低く思えたこの一対でしたかー。
和[王申]の墓は、元々、薊県に建てられていたそう。
しかし墓に入る前に罪を得て死刑になったので、そんな立派な墓に入ることは許されず、今は昌平の小さな土饅頭に埋葬されている。
薊県の巨大な墓の跡は、今はダム湖の下に沈んでいるそうだ。


独楽寺も白塔寺と同じで、創建は遼代。
お寺自体は隋代から続くとのこと。

この山門の看板は、明代の厳崇の文字だそう。
厳崇といえば、時代劇のドラマでは、悪役で登場することも多い宰相だが、いずれまた詳しく知りたい人物やわー。

見取り図があったので、とりあえず、押さえておきまひょ。

山門の壁画
なかなかみごとですが、これは清代のものだそう。
山門と観音殿(巨大観音様のいる本殿)は、遼代のもの、その他の建築は明清代のもの。
ぎゃああ。
今、説明を見たら、山門の金剛力士像は、遼代のオリジナルですって。
わたしったら、なぜ写真を撮らなかったんだろう??
うううー。
中国では、古い金剛力士像が残っているところが少なく(特に北京周辺は)、
今、作りました、といわんばかりのけばけばしい科学塗料で塗装した軽薄で安っぽい新品をおいているお寺がほとんど。
だから入口の金剛さんには、あまり興味を示さなくていい、と頭にすりこまれていたのがいかんかった・・・。
ちらりと見た時、色が渋いなああ、とは思ったものの、まさか遼代のオリジナルとは・・・。
・・・・また今度、訪れる時の楽しみにとっておきましょう・・・。
・・・・とあきらめの境地だったのですが、この記事を出してから、なんと当日ごいっしょした会員の方が
ご自分が撮影されていたお写真をくださいました(涙)!
ありがとうございます!


こうして改めて見ると、やっぱり渋いですねー。
節くれだった腕といい、まんまるな乳首といい、なんだかえらい個性的・・・・。

こちらが観音殿。
残念ながら、中は撮影禁止。巨大な観音像はみごとの一言。

せめてネットでみつけた画像を一枚。
出典 は、掲示板。
おそらく貼った人もどこかから引っ張ってきたものなんだろうけど・・・。
そう。
こんな感じで、見上げるような巨大さ。
上に階段で上がることもでき、窓からは、ちょうどお顔が見えるようになっているのだと思う・・。





扁額は、咸豊帝(西太后のだんな)の筆によるものだそう。
敷地内に行宮があるから、乾隆以降の皇帝は、お墓詣りのたびにここに立ち寄ったということですな。
前述の建築家・梁思成は、独楽寺を見て、「濃厚な唐風建築の特徴がある」といい、当初は唐代の創建なのではないか、と考えたという。
その後、敷地内の最も時代の早い石碑が遼代のものであり、そこに建築物を「再建」したとあるため、現存するものは遼代と判明した。
しかし確かに建築様式は、唐代のものを踏襲しているのかもしれない。
伊勢神宮の式年遷宮ではないが、人々の記憶のあるうちに、まったく同じものを建てると、その姿形は、そのまま伝わるということがある。
うろ覚えだが、確か司馬遼太郎の『街道を行く』シリーズに、「なぜ東大寺には雨どいがない」という内容があり、
歴史上、何度も焼け落ちて再建されたのに、いまだに雨どいがない理由について、東大寺のお坊さんが「昔からそうだったから」と答えたとか。
中国の伝統建築には雨どいがなく、その後、日本で独自に加えたものなのだそうだが、
東大寺は中国から帰ってきた僧侶が大陸の様式を忠実に再現した初期の建築物であり、すでにその存在自体が権威になってしまった。
だからオリジナルが何度焼け落ちても、人々の記憶が残っているうちに再建を繰り返し、
善きも悪きもすべて含めて、改善を加えることなく、様式がそっくりそのまま受け継がれたらしい。
・・・そういうことが、この独楽寺の本殿にも言えるのかもしれない・・・。

右側に乾隆帝の行宮が見えます。

なんだか迫力あるたたずまいの木だと思ったら、千年を超す樹齢ですってー。
すごいー。

巨大な観音様の後ろには、韋駄天さまを祭った亭があります。




後ろから見た図。
建物と韋駄天像は、ともに明代のもの。
明代、行脚僧にとって、境内内の韋駄天像のポーズは、一つの暗号になっていたという。
像が合掌をしていれば、行脚僧の滞在を歓迎するという意味であり、何日でもただ食いただ泊まりをしてよかった。
逆に像が棍棒をむんずと持って、仁王立ちになっていれば、「来るな」という意味だそうだ。
北京周辺でオリジナルの仏像や塑像が残っているところは、きわめて珍しい。
大躍進の時、派手に溶解炉に放り込み、鉄(銅もすべていっしょくたに)の塊にされてしまったのだと聞いた。
こうしてたまに古いオリジナルに出くわすことができると、やはり感動する・・・・。
文物保護の面でも、梁思成の貢献があるという。
1966年、文化大革命が勃発すると、各地の寺院が破壊を受けた。
梁思成は、危険を冒して薊県にやってくると、現状を調査。
観音殿に避雷針をつけ、窓を設置すべし、と国家文化部から9000元の予算を取ることに成功した。
1976年に起きた唐山の大地震の際は、観音殿の壁の一部が崩れ落ちたが、
建物の柱はびくともせず、観音様もまったく無傷だった。
縦に高くそびえる巨大な観音像と、それを取り囲むように立つ、同じく高層の観音殿が、歴代の大地震にも耐え、
びくともしなかったことに、改めて注目が集まった。
以来、それが新たな研究課題となっているのだという。

報恩殿

この時点では、どの狛犬が和[王申]の墓にあったものがわからぬので、とりあえずすべての狛犬を撮っておいたのよ。
「報恩院」の扁額は、咸豊帝(西太后のだんな。何度も強調してごめんよ。でも事実だし、それがわかりやすいんだよ)の筆によるものだそうだ。
・・・しかしなんだかぴかぴか過ぎないかい???
たとえ、分厚く塗り込めた塗料の下には、本物のオリジナルがあるのだとしても、
こういう風情を台無しにした修復の仕方は、やっぱりしらけるわー。


この歯の欠け具合といい、鼻のもげ具合といい、打倒された汚職官僚の末路を如何にも現しておらんかね??
・・・などと、勝手に妄想しつつ・・・。
しかしどうやらはずれなようですね。表玄関の二頭が正解。
こちらの鼻もげは、無駄ということ???

三世仏殿

石碑があると、反射的に写真を撮ってしまうが、どうも様子がおかしい。
石碑が立派すぎるのだ。
奥の仏殿を覗いて見ると、遼代や明代の渋いオリジナルを見た目には、久しぶりに安っぽいけばけばしい仏像が異様さを持って目に飛び込んできた。
どうやらつい最近、人々がお布施を出し合って、新たに仏像を寄付し、それを記念する石碑のようだ。
ケバい仏像さんたちは、撮る価値ないので、残念ながら、証拠写真なし(爆)
最後に、ずっと気になっていた乾隆帝の行宮の方へどんどん行きまひょ。




当初は、この狛犬セットが本命だと思ってましたよ!
しかし残念ながら、これもはずれ。
…確かに言われて見ると、国家予算10年分以上を溜めこんでいた和[王申]さまの陵墓の前に置かれる狛犬としては、
ちいと小さすぎるんですな。
まあ。いいでしょう。
久しぶりに狛犬をたくさん撮った、というのも・・・。

私たちが東陵に行くのに、薊県に立ち寄ったのと同じように、
清の皇帝たちも、東陵に行く途中の宿泊所として、この伽藍の中に行宮を作ったということである。
乾隆18年(1753年)創建。
天津地区で現存する唯一の行宮でもある。
残っていたのは、この正殿のみだったが、現在は回廊十四間分も復元。


碑文は、乾隆帝が王羲之や顔真卿などの歴代の名書家の文字を真似て書いたもの。
石碑は、清代のオリジナル。それを壁の中に塗り込めて回廊にしている。
壁に塗り込める、という形式は、恐らく乾隆帝がやったものではなく、現代の文物局の人のアイデアなんだと思う(笑)。
乾隆帝本人の自作の詩は、ごく少ないが、いくらか混ざっているらしい。
中国語ブログ 一蓑居的博客 さんが、その解読を試みている。
しかし中国の知識人にも、すーっとすぐに解読できるものではないらしく、いろいろとあーでもないこーでもない、
現場で同行者が間違った解釈をしていた、ネットで調べたら、唯一出てきたブログもあまり解説していない、とぶつぶつ言いながらの試み。
ぎゃあああ。
すみません。予約機能にセットしたまま、この数日のうちに訳そうと思っていたら、
時間切れで訳さないまま、アップされてしまいました・・・。
今、時間が取れないので、このまま中国語のままにしてしまいます。。。。
また時間が取れたら、訳します。
最新記事でお知らせを出しますので、あしからずー。
緑雲紅雨日逡巡 绿云,比喻树叶茂盛;红雨,比喻落花,或特指桃花,
李贺《将进酒》诗有“况是青春日将暮,桃花乱落如红雨”。
树叶长得茂盛,落花如雨乱飞时,正是阳春四月间。
逡巡,有两义,一是迟疑徘徊,欲行又止;一是顷刻,不一会意。
这里应是后义,说每天都变得很快。——绿树如云,落花如雨的季节,每天都有变化。
又見楊花点玉津 玉津,玉津园,北宋京城汴梁南门外的名园,园内外遍植杨柳。
杨花,也即柳絮,古时柳树也叫杨树。——又看到杨花柳絮点点飘飞到玉津园的时候了。
两句写春天景象:如云的绿树,如雨的落花,空中飞舞着柳絮杨花。
绿的、红的、白的颜色,以鲜艳的色彩绘出春天美景。
未谱豳风歌七月 豳风,《诗经》里十五《国风》(民歌)之一。
豳,古地名,今陕西彬县、旬邑一带。《豳风》中最长的一首诗叫《七月》。
诗中开头和反复用以起兴的句子是“七月流火,九月授衣”。
秋天(七月)开始了,天气转凉了。气温正和春末差不多。——不是唱《豳风》中《七月》歌的季节。
却看北地殿三春 三春,春天分孟春、仲春、季春三月。殿,在最后。
这里指春末。——眼前看到的是北方佛庙里的暮春景象。
纷如道韫诗中雪 道韫,谢道韫,晋代著名的才女,著名能臣谢安的侄女。
一次下雪,谢安问,“白雪纷纷何所似?”谢安的侄子谢朗说,“散盐空中差可拟?”
道韫说,“未若柳絮因风起。”谢安听了非常高兴。后人就称谢道韫为“咏絮才”。
——纷纷飘飞的是谢道韫诗中比喻雪的柳絮。
污比元规扇上尘 “元规尘”,也是个典故,
《世说新语》《轻詆》:“庾公(亮)权重,足倾王公(导)。
庾在石城,王在冶城。坐大风扬尘,王以扇拂尘,曰:‘元规尘污人。’”
元规,庾亮的字。比喻人的声势逼人。诗句意——它的污浊烦人,犹如元规掀起的尘土。
两句写杨花漫天飞舞的特点,也写了它带给人们的感受——烦恼。
每对清和赋云汉 清和,天气清明和暖,暮春初夏天气,多指四月,即诗中所写时间。
云汉,天河。——每当晴朗的夜晚,仰视天河赋诗。
长空宛转越愁人 看天河,自然要想到牛郎织女的故事,他们是到七月七日才渡鹊桥相会的呀。
——看万里长空蜿蜒曲折的银河,真为等待跨越的牛郎织女发愁啊!
写对夜空的想象,对时间的感慨。
全诗以杨花(柳絮)为中心,写出春天的美好景致,温暖宜人的天气,又有一点“镇日惹飞絮”的烦恼。由白天写到夜晚,想到牛郎织女的盼望相会,表达了对他们的同情。做为皇帝,能有这样的人情味,倒也难能可贵。最后两句,如果从皇帝身份角度去考虑,也可说是对治理国家艰难的感叹。清和,可指政治清明天下太平。——每当要做使国家太平繁荣的文章,想到长路漫漫,欲达到目的可就太难了!



ぽちっと押してくださると、励みになります!



















時の権力者が、いくら残そうとしても、
次代を担う権力者が歴史を塗り替えてしまう・・・・・
よくあるお話ですよね。
日本では、源氏が平家の歴史を塗り替える、
徳川が豊臣の歴史を塗り替える・・・・・
歴史は嘘ばっかりが横行しているような気もしないではないですね。
いつも(^_-)-☆ありがとうです!
そうなのかもしれないですね。
それでもどこか、辻褄が合わない、ほころびのようなものを見つけ、
事実に近づけることができたらいいですねー。