エセン・ハーンは英宗をたてにして、大同の城門を開けさせようとしたが、
これも喜寧の入れ知恵だったといわれる。
つまり大同の城門の外までやってきたモンゴル軍が、英宗に命令させ、城門を開けさせようとしたのである。
開けたら最後、モンゴル軍がどっとなだれ込んできて、あっという間に城が落とされるに決まっているが、
開けなければ英宗を見殺しにすることになり、もし皇帝に返り咲いた場合、どんな罰を受けるかもわからない。
官軍は困り果てたが、やっとのことで妥協案として思いついたのが、かごに乗って兵士が
城門の上から外に降り立ち、皇帝にご挨拶をし、苦境を説明してどうしても門を開けられないことを納得してもらうことだった。
この時、奇妙なことを言い出した人がいるという。
今となっては出典がうろ覚えで、詳しくは思い出せないのだが、
ある軍官におまえがいけ、というと、いや。おれは誰々に殺されるから、いやだといったという。
理由はモンゴル側の誰々のところに娘を嫁をやる約束になっていたが、
今回の外交関係の悪化で、娘をやれなくなってしまった、今降り立ったら、娘の岳父になる予定だった
モンゴル側の軍官があそこにいるから、八つ裂きにされる、と。
つまり国交が断絶し、しょっちゅう殺し合いをしている戦争状態の軍人同士が、
実は秘密裏に婚戚を交わし、裏取引の関係が成立していたということである。
例えば、自分の所属する大同の城は攻めずに他の城を攻めにいってくれとか、
攻める場合は、事前に日取りと場所を知らせ、自分とかち合って戦死しなくてもいいようにするとか、そういうことだろう。
軍人がこのていたらくでは、庶民は殺されたり、略奪されたり、奴隷にされたり、いい面の皮である。
慢性化する戦争に、軍人のほうがもううんざり、死にたくないから、一計案じたというわけである。
軍規の乱れ、壮絶なり。
このような秘密の婚戚関係では、モンゴルに嫁にいった娘が里帰りなどできるはずはない。
父親が見張りの当直をしているときに、城下から矢文が射込まれ、手紙を開いてみると、
娘が無事に子供を生みましたよ、と書いてあった、などという話もある。
お上の気持ち、下々は知らず、である。
さて。
懸賞金までかけられた「漢奸」(・・・・と中国側はいうが、女真族なのだから、ちょっとちゃうやろー)
の喜寧は、どうなったか。
エセンに取り入り、得意満面の喜寧を見て、英宗はあきれ果て、怒りで眩暈がしたが、どうにもできない。
大同城が英宗をだしに脅しても門を開けず、聳え立つ難攻不落の城壁の守りは堅く、簡単に落ちないと見ると、
ルートを変えて北京に迫ることにした。
このルートの提案も中原の地理事情に詳しい喜寧がエセンに入れ知恵したといわれる。

地図で位置関係の確認。
少し印刷が薄いが、左端に大同、真ん中に土木、下の方に紫荊関があるのがわかるだろうか。
西から南下し、山西と華北平原の間に横たわる太行山の中で、谷に沿った、昔からの抜けルートがある。
そこに関所を作り、異民族の侵入を阻止したのが、紫荊関である。
エセンの軍隊は紫荊関を攻撃し、2日で陥落させた。
ここは大同ほど城壁が堅牢に作られておらず、守る兵も少ない。
つまり、これまで中原の地理にあまり詳しくないモンゴル側があまり攻めない場所だからこそ、
守備が薄く、落とされやすかったのである。
それを喜寧は知っていて、提案したルートである。
この戦役で守備都御史の孫祥は戦死した。
太行山から抜けると、悠々と華北平原に出た。
易県、良郷、盧溝橋、と北上し、北京城の南に出た。
最も、北京城を囲んだはいいものの、守る側の于謙は、22万人の軍を北京の九門の麓に配備し、
決死の覚悟で臨んでいる。
北側の長城の防衛線も固く守られており、まもなく全国各地の軍隊も支援に到着するだろう。
これ以上、長城内でぐずぐずしていたら、帰り道も確保できなくなることを危ぶんだエセンは、
北京城を4日包囲しただけで、再び元の道を帰り出した。
エセンを北京の城下に忽然と出現させるという離れ業は、喜寧の存在なしにありえない。
英宗の怒りや、如何ばかりかというところだが、どうすることもできない。
北京包囲に失敗して返ってきても、喜寧はエセンのおそば近くで得意満面である。
後に英宗は謀略を図り、袁彬、哈銘などと推し量り、喜寧を使者として北京に派遣するよう説得する。
この際に、土木の変で同時に捕虜となった明軍の兵士・高磐も同行させたのである。
英宗はこっそり高磐に言い含め、自ら書状を書き、高磐のズボンの中に縫いこんでおいた。
喜寧は得意満面にオイラトと英宗の両方の使者を従え、宣府に入り、明軍との談判の席についた。
明側の将軍は城門を開けるわけに行かないので、
城から出てきて、城下で喜寧とともに宴会を持ち、愉快に(少なくともそんな振りをして)飲んだ。
この時、高磐が突然大声を出し、喜寧にむしゃぶりついて行って放さず、大声で
「太上皇の旨ありー!!」と叫んだ。
北京では、すでに英宗の弟・代宗(景泰帝)が即位しているから、英宗は「太上皇」なわけである。
これを聞いた明の将軍らは、間髪いれずに「ははああー!!」と、全員がひれ伏した。
英宗が喜寧の非道の罪状を書き連ねた諭旨を読み上げ、その場ですべてのオイラトの使者を捕らえ、
喜寧を縛り上げて北京に送った。
英宗の直筆で書かれた手紙を読み、高磐の訴えを聞くと、景泰帝と周りの大臣らは、怒りに打ち震えた。
宦官の喜寧はNao市(明代の刑場)に送られ、三千切れ余り、
肉を少しずつ削りとられるこの世の極刑「凌遅」の刑を受けて死んだ。
懸賞金をかけるまでもなく、捕らわれの身となりながらも思いを果たした英宗の見事なる意地であった。
喜寧はこうして捕らえられ、殺されたが、もはや取り返しはつかなかった。
つまりエセンは、初めてスパイ、そのもたらす情報のすばらしさに気づいてしまったのである。
事前に敵の事情を知ることは、こんなに違うものなのか、と。
その敵情を元に、謀略・作戦を立てられる漢人を参謀に持つことは、こんなに違うものなのか、と。
喜寧が殺されても、その代わりを探せばいいだけである。
今まではこんなに役に立つものと思っていなかったから、探さなかっただけである。
要するに圧倒的な機動力の騎兵隊で、略奪するだけして引き揚げればいいのに、
情報も謀略もへったくれもあるかい、と思っていたのである。
しかしこれまでは、今回のように長城を越えて奥深く、北京まで駆けることは、不可能だった。
荒らすだけ荒らして、人も土地も建物も、骨とあばらだけになり、
ほとんど旨味のなくなってしまった長城の付近に比べ、華北の平原はなんと豊かだったことか。
一度、その味をしめてしまえば、もう後戻りはできない。
景泰元年(1450)、大同総兵の郭登が、スパイを捕らえた。その中の一人は宦官・郭敬の家人、
もう一人は義州軍の王文という。
つまり郭敬は喜寧が捕まってから、その後釜にされた宦官だろう。
英宗とともに捕虜にされた宦官はたくさんいたに違いない。
北京に使者を送りこみ、家の使用人をスパイに利用しようとしたのだろう。
もう一人は、兵士である。同じようにモンゴルの捕虜となり、スパイ活動に従事するようになった。
同年、居庸関でスパイの劉玉が捕らえられた。彼は明の鎮守官・韓政の家人であった。
明の軍官までが、捕虜になった後は、使用人を巻き込んでまでスパイ活動に協力していたのである。
こうしてモンゴル側の攻め方も次第に巧妙に、狡猾になってくる。
土木の変が過ぎ、エセンハーンが死んだ後も漢人の活用はもはや伝統となってゆく。
その後の天順、成化年間(1457-1487)におけるモンゴルの侵入のほとんどは、漢人の道先案内人によるものだといわれる。
それでもまだ長期的なビジョンをもった軍事計画を立てるまでには至らない。
このため例えば、河套地区に侵入しても略奪はできるが、長期的に占領して領土とすることはできなかったのである。
河套地区はつまり、現在の内モンゴル・オルドス地区である。
黄河がぐるりと取り囲む、コップを逆さにしたような部分のうち、
北の一部がオルドス、楡林から南が陝西である。
そのすぐ南に我らが佳県がある。
この時代、オルドスはまだ明の領土だった。
黄河を北の境界としていたのである。
漢人の本格的かつ高度な活用が始まるのは、正徳年間(1506-1521)になってからである。
正徳年間、明の国境軍で「指揮」(官職名の一つ)を勤めていた
「獅児李」(「ライオンの李」くらいの意味か。本名ではなく、あだ名ですな)
が戦闘でモンゴル側の捕虜になり、重用されて軍事参謀になった。
モンゴル側のスパイ(つまりは漢人)を捕まえて自供させると、必ず皆がその名を口にした。
獅児李はモンゴルの諸部族から絶対的に信頼されており、彼の立てる作戦であれば、
皆がその命令に従うという。
元は自らが明軍の指揮を勤めていただけに、明軍の軍事配備、虚実もすべて知る身である。
明の盲点をずばりと衝いて攻撃してくるため、明側への打撃は大きかった。
その首にも懸賞金がかけられた。
「指揮使」職の子孫代々までの世襲、賞金は銀2千両である。
このように当初はモンゴル側の捕虜となるか、奴隷にさらわれるかして
本人の望まないままにモンゴルに連れてこられた漢人が多かったわけだが、
生きるため、少しでもましな生活を与えてもらうため、必要に迫られて漢人らはモンゴル側に協力してゆく。
さらわれた人々は、望郷の念、絶え難くもあるが、モンゴル側の監視は厳しく、簡単に逃亡できるものではない。
例えできたとしても、長城沿線の城門のドアをノックすれば、逆に明軍の兵士に殺されることが多い。
つまり「モンゴル人を成敗した」と、手柄にされてしまうのだ。
相次ぐモンゴルの略奪で、国境軍の兵士らは常に大きなプレッシャーに晒されている。
「今回の襲撃でもまた決定的な勝利はなしか」と、上から責められる。
そこで、逃亡した漢人がやっとのことで長城の門を叩き、
「入れてくれ」と訴えても、聞こえなかった振りをして「成敗」してしまうのである。
なんたる悲惨なる運命か。
モンゴル側がこれを脅し文句に、漢人らの逃亡の念を絶たせる始末である。
「おまえらは逃げ帰っても、国境警備軍に殺されて手柄にされるのが落ちだぞ」と。
******************************************
写真: 楡林
歴史的風貌を再現した町並みですが、入っているお店は、普通のもの。
それでもこういう書道の道具を売っているお店とか、仏具とか、骨董とか、
何かしら歴史的なにおいのするところが多い。

こちらはブライダルサロン。結婚式のお色直しの衣装のようです。

パソコン教室でしょうかね。
中国的な扁額にeの文字が斬新。

続けて北に歩いていくと、見えてくるのは、鐘楼。


元々あったものが焼失したため、
1921年、陝西23県の官僚、郷紳らの出資により新たに西洋風のものに建て替えた。
民国時代の建物は、ハイカラでなんともいえない味わいですなあ。

元々は鐘楼ではなく、乾隆年間に建てられた牌楼だったという。
乾隆年間、地元出身の軍人であった雲南総兵・段騰龍が、ミャンマーに出兵し、現地で戦死した。
地元の人々が、故郷の英雄を記念して建てた牌楼だったのだという。
これが1921年に焼失したため、その代わりに建てられたのが、この鐘楼なのである。
文革時代には赤く塗られ、「東方紅楼」と改名されていた。


奥に伸びる四合院。楡林は、「小北京」の異名を持つ。

その本家の北京では、すでに胡同がほとんどぶっこわされてビルになっているか、
人間らしい生活ができないほどに、人々がひしめき合って暮らしているか、
原型もとどめないほどに、庭に掘っ立て小屋を増築して、じめじめと不潔になっているか、
というほとんどスラム化したような四合院が多いです。
今となってはもう「小北京」の楡林のほうが、往年の北京城を彷彿とさせるかもしれません。

銅製品のお店。
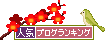

これも喜寧の入れ知恵だったといわれる。
つまり大同の城門の外までやってきたモンゴル軍が、英宗に命令させ、城門を開けさせようとしたのである。
開けたら最後、モンゴル軍がどっとなだれ込んできて、あっという間に城が落とされるに決まっているが、
開けなければ英宗を見殺しにすることになり、もし皇帝に返り咲いた場合、どんな罰を受けるかもわからない。
官軍は困り果てたが、やっとのことで妥協案として思いついたのが、かごに乗って兵士が
城門の上から外に降り立ち、皇帝にご挨拶をし、苦境を説明してどうしても門を開けられないことを納得してもらうことだった。
この時、奇妙なことを言い出した人がいるという。
今となっては出典がうろ覚えで、詳しくは思い出せないのだが、
ある軍官におまえがいけ、というと、いや。おれは誰々に殺されるから、いやだといったという。
理由はモンゴル側の誰々のところに娘を嫁をやる約束になっていたが、
今回の外交関係の悪化で、娘をやれなくなってしまった、今降り立ったら、娘の岳父になる予定だった
モンゴル側の軍官があそこにいるから、八つ裂きにされる、と。
つまり国交が断絶し、しょっちゅう殺し合いをしている戦争状態の軍人同士が、
実は秘密裏に婚戚を交わし、裏取引の関係が成立していたということである。
例えば、自分の所属する大同の城は攻めずに他の城を攻めにいってくれとか、
攻める場合は、事前に日取りと場所を知らせ、自分とかち合って戦死しなくてもいいようにするとか、そういうことだろう。
軍人がこのていたらくでは、庶民は殺されたり、略奪されたり、奴隷にされたり、いい面の皮である。
慢性化する戦争に、軍人のほうがもううんざり、死にたくないから、一計案じたというわけである。
軍規の乱れ、壮絶なり。
このような秘密の婚戚関係では、モンゴルに嫁にいった娘が里帰りなどできるはずはない。
父親が見張りの当直をしているときに、城下から矢文が射込まれ、手紙を開いてみると、
娘が無事に子供を生みましたよ、と書いてあった、などという話もある。
お上の気持ち、下々は知らず、である。
さて。
懸賞金までかけられた「漢奸」(・・・・と中国側はいうが、女真族なのだから、ちょっとちゃうやろー)
の喜寧は、どうなったか。
エセンに取り入り、得意満面の喜寧を見て、英宗はあきれ果て、怒りで眩暈がしたが、どうにもできない。
大同城が英宗をだしに脅しても門を開けず、聳え立つ難攻不落の城壁の守りは堅く、簡単に落ちないと見ると、
ルートを変えて北京に迫ることにした。
このルートの提案も中原の地理事情に詳しい喜寧がエセンに入れ知恵したといわれる。

地図で位置関係の確認。
少し印刷が薄いが、左端に大同、真ん中に土木、下の方に紫荊関があるのがわかるだろうか。
西から南下し、山西と華北平原の間に横たわる太行山の中で、谷に沿った、昔からの抜けルートがある。
そこに関所を作り、異民族の侵入を阻止したのが、紫荊関である。
エセンの軍隊は紫荊関を攻撃し、2日で陥落させた。
ここは大同ほど城壁が堅牢に作られておらず、守る兵も少ない。
つまり、これまで中原の地理にあまり詳しくないモンゴル側があまり攻めない場所だからこそ、
守備が薄く、落とされやすかったのである。
それを喜寧は知っていて、提案したルートである。
この戦役で守備都御史の孫祥は戦死した。
太行山から抜けると、悠々と華北平原に出た。
易県、良郷、盧溝橋、と北上し、北京城の南に出た。
最も、北京城を囲んだはいいものの、守る側の于謙は、22万人の軍を北京の九門の麓に配備し、
決死の覚悟で臨んでいる。
北側の長城の防衛線も固く守られており、まもなく全国各地の軍隊も支援に到着するだろう。
これ以上、長城内でぐずぐずしていたら、帰り道も確保できなくなることを危ぶんだエセンは、
北京城を4日包囲しただけで、再び元の道を帰り出した。
エセンを北京の城下に忽然と出現させるという離れ業は、喜寧の存在なしにありえない。
英宗の怒りや、如何ばかりかというところだが、どうすることもできない。
北京包囲に失敗して返ってきても、喜寧はエセンのおそば近くで得意満面である。
後に英宗は謀略を図り、袁彬、哈銘などと推し量り、喜寧を使者として北京に派遣するよう説得する。
この際に、土木の変で同時に捕虜となった明軍の兵士・高磐も同行させたのである。
英宗はこっそり高磐に言い含め、自ら書状を書き、高磐のズボンの中に縫いこんでおいた。
喜寧は得意満面にオイラトと英宗の両方の使者を従え、宣府に入り、明軍との談判の席についた。
明側の将軍は城門を開けるわけに行かないので、
城から出てきて、城下で喜寧とともに宴会を持ち、愉快に(少なくともそんな振りをして)飲んだ。
この時、高磐が突然大声を出し、喜寧にむしゃぶりついて行って放さず、大声で
「太上皇の旨ありー!!」と叫んだ。
北京では、すでに英宗の弟・代宗(景泰帝)が即位しているから、英宗は「太上皇」なわけである。
これを聞いた明の将軍らは、間髪いれずに「ははああー!!」と、全員がひれ伏した。
英宗が喜寧の非道の罪状を書き連ねた諭旨を読み上げ、その場ですべてのオイラトの使者を捕らえ、
喜寧を縛り上げて北京に送った。
英宗の直筆で書かれた手紙を読み、高磐の訴えを聞くと、景泰帝と周りの大臣らは、怒りに打ち震えた。
宦官の喜寧はNao市(明代の刑場)に送られ、三千切れ余り、
肉を少しずつ削りとられるこの世の極刑「凌遅」の刑を受けて死んだ。
懸賞金をかけるまでもなく、捕らわれの身となりながらも思いを果たした英宗の見事なる意地であった。
喜寧はこうして捕らえられ、殺されたが、もはや取り返しはつかなかった。
つまりエセンは、初めてスパイ、そのもたらす情報のすばらしさに気づいてしまったのである。
事前に敵の事情を知ることは、こんなに違うものなのか、と。
その敵情を元に、謀略・作戦を立てられる漢人を参謀に持つことは、こんなに違うものなのか、と。
喜寧が殺されても、その代わりを探せばいいだけである。
今まではこんなに役に立つものと思っていなかったから、探さなかっただけである。
要するに圧倒的な機動力の騎兵隊で、略奪するだけして引き揚げればいいのに、
情報も謀略もへったくれもあるかい、と思っていたのである。
しかしこれまでは、今回のように長城を越えて奥深く、北京まで駆けることは、不可能だった。
荒らすだけ荒らして、人も土地も建物も、骨とあばらだけになり、
ほとんど旨味のなくなってしまった長城の付近に比べ、華北の平原はなんと豊かだったことか。
一度、その味をしめてしまえば、もう後戻りはできない。
景泰元年(1450)、大同総兵の郭登が、スパイを捕らえた。その中の一人は宦官・郭敬の家人、
もう一人は義州軍の王文という。
つまり郭敬は喜寧が捕まってから、その後釜にされた宦官だろう。
英宗とともに捕虜にされた宦官はたくさんいたに違いない。
北京に使者を送りこみ、家の使用人をスパイに利用しようとしたのだろう。
もう一人は、兵士である。同じようにモンゴルの捕虜となり、スパイ活動に従事するようになった。
同年、居庸関でスパイの劉玉が捕らえられた。彼は明の鎮守官・韓政の家人であった。
明の軍官までが、捕虜になった後は、使用人を巻き込んでまでスパイ活動に協力していたのである。
こうしてモンゴル側の攻め方も次第に巧妙に、狡猾になってくる。
土木の変が過ぎ、エセンハーンが死んだ後も漢人の活用はもはや伝統となってゆく。
その後の天順、成化年間(1457-1487)におけるモンゴルの侵入のほとんどは、漢人の道先案内人によるものだといわれる。
それでもまだ長期的なビジョンをもった軍事計画を立てるまでには至らない。
このため例えば、河套地区に侵入しても略奪はできるが、長期的に占領して領土とすることはできなかったのである。
河套地区はつまり、現在の内モンゴル・オルドス地区である。
黄河がぐるりと取り囲む、コップを逆さにしたような部分のうち、
北の一部がオルドス、楡林から南が陝西である。
そのすぐ南に我らが佳県がある。
この時代、オルドスはまだ明の領土だった。
黄河を北の境界としていたのである。
漢人の本格的かつ高度な活用が始まるのは、正徳年間(1506-1521)になってからである。
正徳年間、明の国境軍で「指揮」(官職名の一つ)を勤めていた
「獅児李」(「ライオンの李」くらいの意味か。本名ではなく、あだ名ですな)
が戦闘でモンゴル側の捕虜になり、重用されて軍事参謀になった。
モンゴル側のスパイ(つまりは漢人)を捕まえて自供させると、必ず皆がその名を口にした。
獅児李はモンゴルの諸部族から絶対的に信頼されており、彼の立てる作戦であれば、
皆がその命令に従うという。
元は自らが明軍の指揮を勤めていただけに、明軍の軍事配備、虚実もすべて知る身である。
明の盲点をずばりと衝いて攻撃してくるため、明側への打撃は大きかった。
その首にも懸賞金がかけられた。
「指揮使」職の子孫代々までの世襲、賞金は銀2千両である。
このように当初はモンゴル側の捕虜となるか、奴隷にさらわれるかして
本人の望まないままにモンゴルに連れてこられた漢人が多かったわけだが、
生きるため、少しでもましな生活を与えてもらうため、必要に迫られて漢人らはモンゴル側に協力してゆく。
さらわれた人々は、望郷の念、絶え難くもあるが、モンゴル側の監視は厳しく、簡単に逃亡できるものではない。
例えできたとしても、長城沿線の城門のドアをノックすれば、逆に明軍の兵士に殺されることが多い。
つまり「モンゴル人を成敗した」と、手柄にされてしまうのだ。
相次ぐモンゴルの略奪で、国境軍の兵士らは常に大きなプレッシャーに晒されている。
「今回の襲撃でもまた決定的な勝利はなしか」と、上から責められる。
そこで、逃亡した漢人がやっとのことで長城の門を叩き、
「入れてくれ」と訴えても、聞こえなかった振りをして「成敗」してしまうのである。
なんたる悲惨なる運命か。
モンゴル側がこれを脅し文句に、漢人らの逃亡の念を絶たせる始末である。
「おまえらは逃げ帰っても、国境警備軍に殺されて手柄にされるのが落ちだぞ」と。
******************************************
写真: 楡林
歴史的風貌を再現した町並みですが、入っているお店は、普通のもの。
それでもこういう書道の道具を売っているお店とか、仏具とか、骨董とか、
何かしら歴史的なにおいのするところが多い。

こちらはブライダルサロン。結婚式のお色直しの衣装のようです。

パソコン教室でしょうかね。
中国的な扁額にeの文字が斬新。

続けて北に歩いていくと、見えてくるのは、鐘楼。


元々あったものが焼失したため、
1921年、陝西23県の官僚、郷紳らの出資により新たに西洋風のものに建て替えた。
民国時代の建物は、ハイカラでなんともいえない味わいですなあ。

元々は鐘楼ではなく、乾隆年間に建てられた牌楼だったという。
乾隆年間、地元出身の軍人であった雲南総兵・段騰龍が、ミャンマーに出兵し、現地で戦死した。
地元の人々が、故郷の英雄を記念して建てた牌楼だったのだという。
これが1921年に焼失したため、その代わりに建てられたのが、この鐘楼なのである。
文革時代には赤く塗られ、「東方紅楼」と改名されていた。


奥に伸びる四合院。楡林は、「小北京」の異名を持つ。

その本家の北京では、すでに胡同がほとんどぶっこわされてビルになっているか、
人間らしい生活ができないほどに、人々がひしめき合って暮らしているか、
原型もとどめないほどに、庭に掘っ立て小屋を増築して、じめじめと不潔になっているか、
というほとんどスラム化したような四合院が多いです。
今となってはもう「小北京」の楡林のほうが、往年の北京城を彷彿とさせるかもしれません。

銅製品のお店。



















こちらのレポートと、あらためてhttp://www2s.biglobe.ne.jp/~xianxue/DandX/DandX.htmのページの「2章7:明清の道教の衰退と世俗化」なるほどと認識しました。
人民中国になって全真教は香港で、正一教は台湾で引き継がれているとのこと。武侠小説がそこから発信されているというのも関係あるのでしょうね。
今胡龍の「大人物」というDVDをレンタルして見ています。14話まで見ました。