令和3年12月29日(水)
年用意 : 春支度

新年を迎えるためにいろいろ支度を整えること。
家の中の掃除、畳み替え(今は皆無)、障子貼、外回り繕い、
正月の買い物、松飾りや注連縄の手配、年木取り(新春用に
年末に薪を準備する事)、晴れ着縫い等がそれにあたる。
古い書物等を整理していると、カミさんから声がかかる。
「買物に出掛けるので、一緒に出掛けない?」珍しく、、
何のことはない、荷物持ちの誘いで在ろう。
否応なしにご同伴、、、久方に大須商店街へでかける。

毎年この時期(28日)に大須観音で開かれる「骨董市」
は今年は中止となった。
それでも境内には結構な人出がある。

商店街に入ると大層な賑わいをみせて、行き交う人は皆
マスクをしている。 日本人は皆礼儀正しく必ず皆さん
外出時はマスクをしている。(マスクは日本の文化)
ワクチン接種も必要であるが、欧米等では皆マスクを
嫌がり、人混みの多い劇場、スタジアムやパーティ会場
果ては居酒屋等でも皆混雑で蜜の中、マスク無しで大声
で絶叫、会食している、、この光景を目にすると感染の
防止は出来ず、パンデミックは止むを得ない、、、、
大統領や首相等の政府関係者が宣言しても無視される。
日本と欧米(韓国、ロシア等も)との違いはマスク。
大手スーパーへ立ち寄り、食料売り場へ、、、、

正月用のお節を始め、海産物、肉等、、人出の多さに
驚く、、、、


かまぼこ、出し巻、カニ等を買い求め、、、
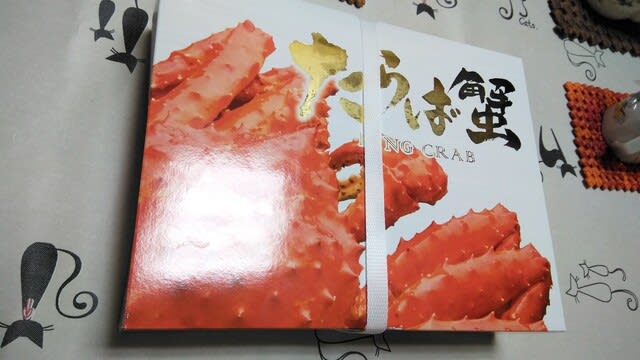
刺身やお節(小ぶりのもの)は31日に届く予定とか。
何やかやそれでも両手に一杯ぶら下げて、辺りを見回せ
ば、皆同じような姿でいらっしゃる、、、、、。
今日の1句
人混みの中妻逞しき年用意 ヤギ爺












































