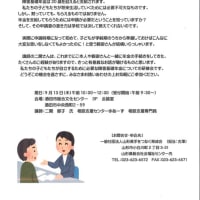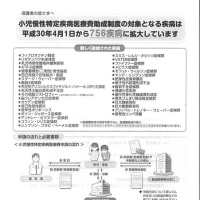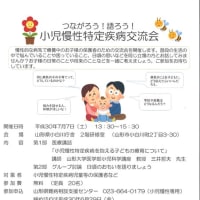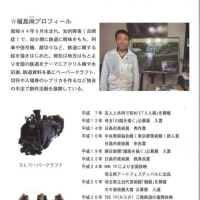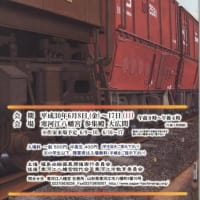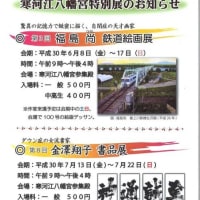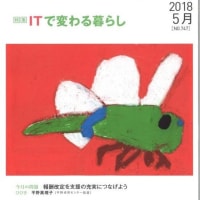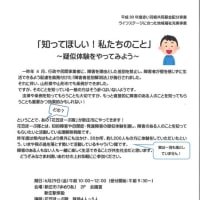浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第90回目。
国連総会で障害者の権利に関する条約が採択された。
その締結には国内法の整備が必要である。
そのあたりの事情が以下に説明されている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
2006(平成18)年12月、第61回国連総会において
障害を理由とするあらゆる分野における差別を禁止し、
障害者の権利を保障する「障害者の権利に関する条約(障害者の権利条約)」が
採択されました。
日本もこの条約の締結に向けて必要な国内法の整備を行っているところであり、
障害者基本法が改正されたことも、
障害者自立支援法に代わる新しい法律をどのようなものにするか
ということもそれと関連しているわけです。
その意味で、新法に関する骨格提言の内容は、きわめて重要なことだと思います。
どのような法律であっても、
その法律は確かな理念に裏打ちされたものでなければなりませんが、
障害者自立支援法は、その点が不十分であったといっても過言ではありません。
(2011.11.30)
【引用終わり】
*************************************************
国連における障害者の権利条約が採択されて、それの批准に向けて国内法の整備がずっと続いている。
日本として条約がきっちり履行されるように、障がい者制度の抜本的な改革に集中的に取り組んでいる。
日本の誠実な取り組みは、評価されるべきである。
批准まで時間はかかっているが、国内の合意を得る作業は必要である。
そのために、障害者総合支援法や虐待防止法、差別解消法の成立をみた。
こうした法の執行によって、より良い障がい者福祉の向上を図っていく。
障がい者が地域でごく当たり前の普通の暮らしができる社会を目指す。
(ケー)
その第90回目。
国連総会で障害者の権利に関する条約が採択された。
その締結には国内法の整備が必要である。
そのあたりの事情が以下に説明されている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
2006(平成18)年12月、第61回国連総会において
障害を理由とするあらゆる分野における差別を禁止し、
障害者の権利を保障する「障害者の権利に関する条約(障害者の権利条約)」が
採択されました。
日本もこの条約の締結に向けて必要な国内法の整備を行っているところであり、
障害者基本法が改正されたことも、
障害者自立支援法に代わる新しい法律をどのようなものにするか
ということもそれと関連しているわけです。
その意味で、新法に関する骨格提言の内容は、きわめて重要なことだと思います。
どのような法律であっても、
その法律は確かな理念に裏打ちされたものでなければなりませんが、
障害者自立支援法は、その点が不十分であったといっても過言ではありません。
(2011.11.30)
【引用終わり】
*************************************************
国連における障害者の権利条約が採択されて、それの批准に向けて国内法の整備がずっと続いている。
日本として条約がきっちり履行されるように、障がい者制度の抜本的な改革に集中的に取り組んでいる。
日本の誠実な取り組みは、評価されるべきである。
批准まで時間はかかっているが、国内の合意を得る作業は必要である。
そのために、障害者総合支援法や虐待防止法、差別解消法の成立をみた。
こうした法の執行によって、より良い障がい者福祉の向上を図っていく。
障がい者が地域でごく当たり前の普通の暮らしができる社会を目指す。
(ケー)