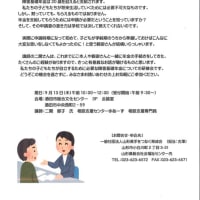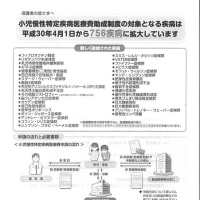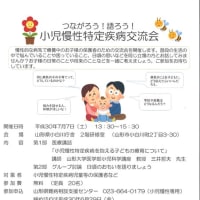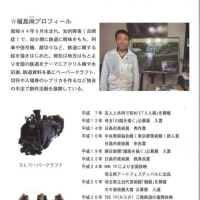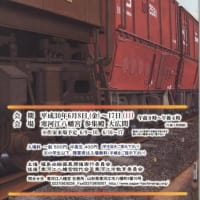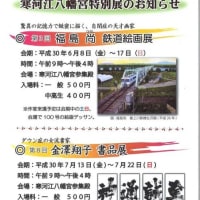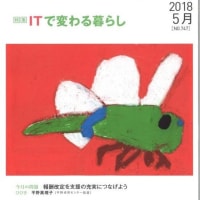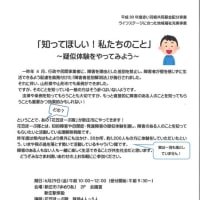浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第95回目。
障がい児の教育は確実に整備されてきた。
その割には、卒業後の障がい者の生活は十分と言えない。
以下では、障がい者の一生を見据えた施策が十分でなかったことが原因と指摘している。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
障害児教育の義務制の実施と障害者福祉
戦後日本の教育・福祉はそれなりに充実発展し、
障害児の学校教育も義務制となりました。
しかし学校を卒業後の就労や生活、
さらにその老後に至る「親亡き後」の暮らしを概観すれば、
その道筋は依然として未整備のままの状況が続いています。
それは障害の有無にかかわらず人の一生をどのように考えるか
という視点が欠けているからだと思います。
障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、
そのための教育をどのように考えるかが大切なわけですが、
そこに教育施策と福祉施策の連携の重要性があり、
そのための問題・課題があると思います。
【引用終わり】
*************************************************
障がい者の一生といった視点で、障がい者施策を見直す必要がある。
幼児期、就学期、卒後の就労期、そして終末期とライフステージにそった節目のある施策が求められる。
その時々に訪れる課題へしっかり対応できる態勢を創り上げていくことである。
障害者総合支援法は、その課題解決に役立つ法律でなければならない。
障がい者の一生の生活に役立つものにする必要がある。
(ケー)
その第95回目。
障がい児の教育は確実に整備されてきた。
その割には、卒業後の障がい者の生活は十分と言えない。
以下では、障がい者の一生を見据えた施策が十分でなかったことが原因と指摘している。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
障害児教育の義務制の実施と障害者福祉
戦後日本の教育・福祉はそれなりに充実発展し、
障害児の学校教育も義務制となりました。
しかし学校を卒業後の就労や生活、
さらにその老後に至る「親亡き後」の暮らしを概観すれば、
その道筋は依然として未整備のままの状況が続いています。
それは障害の有無にかかわらず人の一生をどのように考えるか
という視点が欠けているからだと思います。
障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、
そのための教育をどのように考えるかが大切なわけですが、
そこに教育施策と福祉施策の連携の重要性があり、
そのための問題・課題があると思います。
【引用終わり】
*************************************************
障がい者の一生といった視点で、障がい者施策を見直す必要がある。
幼児期、就学期、卒後の就労期、そして終末期とライフステージにそった節目のある施策が求められる。
その時々に訪れる課題へしっかり対応できる態勢を創り上げていくことである。
障害者総合支援法は、その課題解決に役立つ法律でなければならない。
障がい者の一生の生活に役立つものにする必要がある。
(ケー)