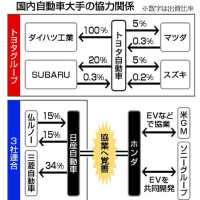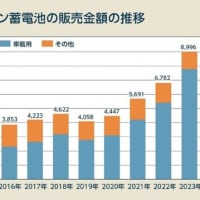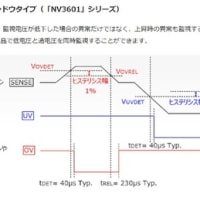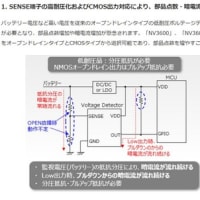前回の既出で、記し忘れてしまったことを中心に、追記して書き記して見たいと思います。それは、「融点660℃のアルミは何故溶けないのか?」ということです。
大まかに鉄(鋼)の融点は1,550℃、アルミは660℃と知られています。しかも、アルミは400℃を越えると極端な強度低下と内部組織が脆化し、冷温になっても元の金属的性質に戻らなくなると、ものの本には解説されています。
拙人は車両火災の事件などで現車を観察することがありますが、一般的な車両火災では火炎温度が800℃程度出あることが知られています。この温度に達すると、樹脂部品は200℃満たない温度で変形し、400℃程度で発火し、自ら発熱して火災を拡大させます。また、金属ではアルミニウム部位は融点が660℃ですので、溶け落ちている場面をしばしば見ます。鋼の部分は、車両火災ではまず溶けることはありませんが、高音で軟化しつつ、応力部位では変形が生じることになります。
車両火災の場合で火炎温度は800℃ですが、燃焼室内での火炎温度は最高2千℃程度まで達しますが、吸排気を繰り返していますから、常時2千℃を保つ訳ではありません。しかし、極短時間の繰り返しで、2千℃まで達する燃焼室壁面とかピストンヘッドが溶損しないで済むのは、燃焼拡大する火炎の最外側に温度境界層という断熱層ができることにあるそうです。
その様な理由で、燃焼室やピストンヘッドも溶損するまでの加熱は受けないで済むのですが、冷却水とかエンジノイルで、それなりに冷却することで、最高でも200℃以上になることがないようにされているそうです。アルミは特にですが、温度上昇と共に耐力が低下し、200℃で300%減すると知りますから、その辺りが限界温度となるのでしょう。
なお、高性能エンジンだとか大型車のエンジンなど、熱条件が厳しいエンジンでは、シリンダー下方から真上に吹き出すオイルジェットによる冷却と共に、ピストン内部に冠状の冷却油溝を形成することで、ピストンの過剰昇温を防止しています。
一方、エンジン内部は冷却水で100℃程度までの範囲で制御されております。またエンジンオイル油温も120℃程度までの昇温で留まる様に設計されています。もし、極限の運転状態やトラブルで、冷却水温度で120℃、油温で140℃を越えると、それぞれ問題が生じることになります。それは、冷却水の過剰温度は、ピストンであれば、過剰な膨張により、シリンダーとの隙間がなくなりカジリ(縦キズ)を生じるとか、シリンダーヘッドに熱膨張による歪みを生じ、ヘッドガスケットが押さえきれず吹き飛ぶというトラブルでしょう。油温の過剰温度は、まずは油膜保持性が低下することで、メタル類の焼き付き、エンジン内部のオイル冷却部位の加熱による問題を生じることが予想されます。
この様にエンジン内部は温度境界層という保護層で高温の燃焼ガスから逃れているのですが、ノッキングとか異常燃焼を起こした場合、その衝撃波は温度境界層を破壊し、直接熱を伝えてしまうということです。ですから、極小さい軽い「カリカリもしくはチリチリ」というノッキング音程度なら、直ぐにエンジン破壊に至ることはありませんが、その音が極端に大きくなり出力低下も感じる状態で継続運転しますと、ピストンや燃焼室内の溶損という重大トラブルに発展することがあり得ます。
大まかに鉄(鋼)の融点は1,550℃、アルミは660℃と知られています。しかも、アルミは400℃を越えると極端な強度低下と内部組織が脆化し、冷温になっても元の金属的性質に戻らなくなると、ものの本には解説されています。
拙人は車両火災の事件などで現車を観察することがありますが、一般的な車両火災では火炎温度が800℃程度出あることが知られています。この温度に達すると、樹脂部品は200℃満たない温度で変形し、400℃程度で発火し、自ら発熱して火災を拡大させます。また、金属ではアルミニウム部位は融点が660℃ですので、溶け落ちている場面をしばしば見ます。鋼の部分は、車両火災ではまず溶けることはありませんが、高音で軟化しつつ、応力部位では変形が生じることになります。
車両火災の場合で火炎温度は800℃ですが、燃焼室内での火炎温度は最高2千℃程度まで達しますが、吸排気を繰り返していますから、常時2千℃を保つ訳ではありません。しかし、極短時間の繰り返しで、2千℃まで達する燃焼室壁面とかピストンヘッドが溶損しないで済むのは、燃焼拡大する火炎の最外側に温度境界層という断熱層ができることにあるそうです。
その様な理由で、燃焼室やピストンヘッドも溶損するまでの加熱は受けないで済むのですが、冷却水とかエンジノイルで、それなりに冷却することで、最高でも200℃以上になることがないようにされているそうです。アルミは特にですが、温度上昇と共に耐力が低下し、200℃で300%減すると知りますから、その辺りが限界温度となるのでしょう。
なお、高性能エンジンだとか大型車のエンジンなど、熱条件が厳しいエンジンでは、シリンダー下方から真上に吹き出すオイルジェットによる冷却と共に、ピストン内部に冠状の冷却油溝を形成することで、ピストンの過剰昇温を防止しています。
一方、エンジン内部は冷却水で100℃程度までの範囲で制御されております。またエンジンオイル油温も120℃程度までの昇温で留まる様に設計されています。もし、極限の運転状態やトラブルで、冷却水温度で120℃、油温で140℃を越えると、それぞれ問題が生じることになります。それは、冷却水の過剰温度は、ピストンであれば、過剰な膨張により、シリンダーとの隙間がなくなりカジリ(縦キズ)を生じるとか、シリンダーヘッドに熱膨張による歪みを生じ、ヘッドガスケットが押さえきれず吹き飛ぶというトラブルでしょう。油温の過剰温度は、まずは油膜保持性が低下することで、メタル類の焼き付き、エンジン内部のオイル冷却部位の加熱による問題を生じることが予想されます。
この様にエンジン内部は温度境界層という保護層で高温の燃焼ガスから逃れているのですが、ノッキングとか異常燃焼を起こした場合、その衝撃波は温度境界層を破壊し、直接熱を伝えてしまうということです。ですから、極小さい軽い「カリカリもしくはチリチリ」というノッキング音程度なら、直ぐにエンジン破壊に至ることはありませんが、その音が極端に大きくなり出力低下も感じる状態で継続運転しますと、ピストンや燃焼室内の溶損という重大トラブルに発展することがあり得ます。