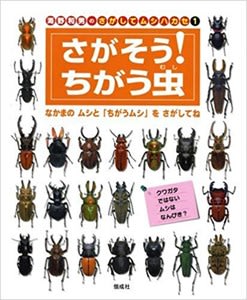良好な水環境の保全と快適な水辺空間の創造をめざす「メダカのいる里づくり」運動の一環として2001年全国メダカフェスを開催しました。
これは、メダカを取り巻く環境が、1999年2月に環境庁(当時)が発表したレッドリストにて絶滅危惧II類 (VU)(環境省レッドリスト)(絶滅の危険が増大している種)になったこともある。
このフェス以後、メダカは2003年5月にレッドデータブックに絶滅危惧種として指定された。
全国メダカフェスティバルの内容について報告する
*********************************************************
2001年(平成13年)5月3日(木) 全国メダカフェスティバルが開催されました。
全国メダカフェスティバル
みんなで守ろう・創ろう!
―メダカの住める環境を―
主催 全国メダカフェスティバル実行委員会
メダカのいる里づくり実行委員会
財団法人丹波の森協会
丹波の森公苑
開催場所 兵庫県氷上郡柏原町 丹波の森公苑
プログラム
10:00 開会
主催者代表あいさつ 全国メダカフェスティバル実行委員会
代表 メダカのいる里づくり実行委員会
委員長 清水 圭一
歓迎あいさつ 丹波の森公苑長 河合 雅雄
10:15 講演 メダカと学問 日本メダカトラスト協会会長・愛知教育大学名誉教授
岩松 鷹司 先生
11:15 活動状況発表 Ⅰ
●日本メダカトラスト協会事務局・社団法人高知県生態系保護協会
13:00 活動状況発表 Ⅱ
●社団法人 大阪自然環境保全協会
●米子地区環境問題を考える企業懇話会
●豊岡六方めだか公園
●宝塚市内小学校代表
●平成10年度自然学習モデル校、春日町立大路小学校
●平成9年度メダカの蘇生モデル地区
篠山市 篠山城址内堀〔発表:篠山青年会議所〕
14:30 円広志さんのトーク
15:00 丹波の森:メダカの宣言
15:10 メダカ放流
15:30 閉会
*******************************************************
最近のメダカの話題
2011年12月に日本のメダカ、実は2種類!という発表を近畿大学大学院農学研究科で環境管理学を専攻する朝井俊亘さん(博士課程3年・水圏生態学研究室)が発表した。
メダカについての環境はまだ十分ではないし、研究すればまだ新発見があるということだ。