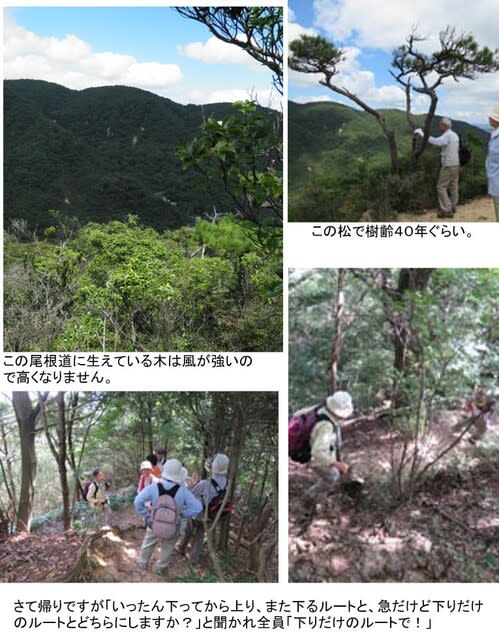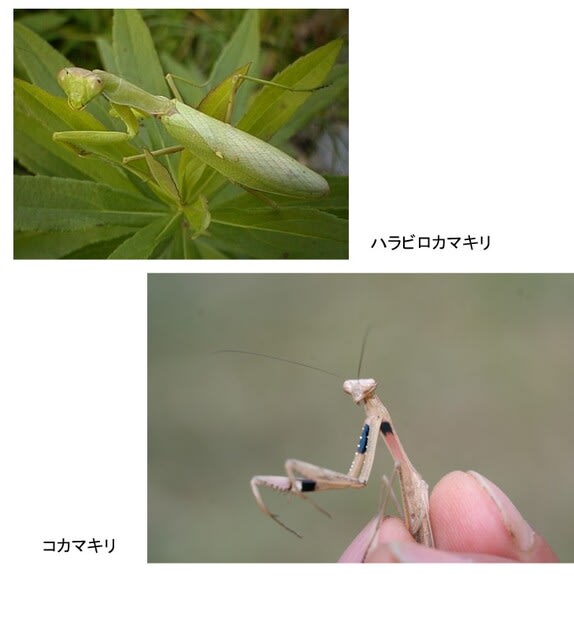アキノノゲシ(キク科)
東南アジアが原産で稲作と共に日本へ渡って来た史前帰化植物。
田や畑のまわり、土手などでよく見られます。
アキノノゲシは、ノゲシが別名でハルノノゲシと呼ばれるので、秋に花を咲かせることからつけられた名前です。
ノゲシ(野芥子)という名前が付きますが、ノゲシ(ハルノノゲシ)とは別でアキノノゲシ属です。
レタス(Lactuca sativa)の仲間で、 レタス、サニーレタス、ニガチシャ、カキチシャ、サラダ菜など同じ仲間になりあます。
初夏までは丈は低く、花を咲かせる頃から急に高くなります。直立して高さ50~200cmになります。
アキノノゲシの花は、一日花で、甲虫、チョウ、ハナアブなど様々な昆虫たちが集まってきます。

きずつけると白い乳液が出ます。
同じキク科でも,白い乳液のあるなしで次のように分けます。
白い乳液の出るタンポポやアキノノゲシを「タンポポ亜科」
白い乳液のでないアキノキリンソウやヨモギやヨメナは「キク亜科」
アキノノゲシには葉に切れ込みがあり、切れ込みのない細い葉を持つものは、ホソバアキノノゲシ(学名: Lactuca indica f. indivisa)と区別されます。