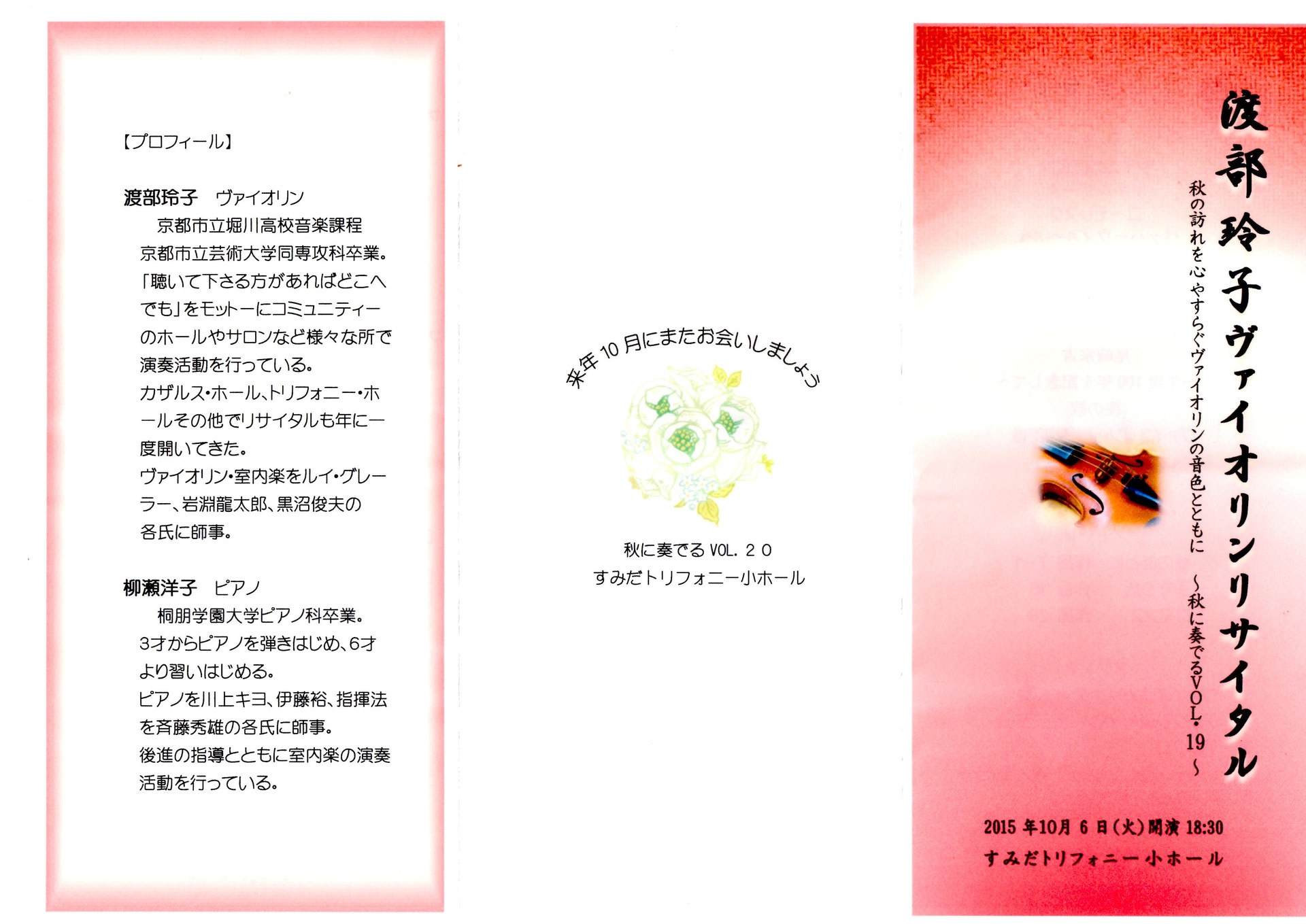ゴールデンウィークの真っ盛り、5月3、4、5日、横浜市野毛町にある「にぎわい座」で、立川志の輔師匠の独演会が催された。
師匠直接のお声掛かりで、和力がゲストとして出演することが決まったのが、2月のことである。
加藤木朗が住まう信州阿智村には、ゆたかな湯量に恵まれた「昼神温泉郷」があり、ホテルや宿が立ち並ぶ。
能舞台をもつ「石苔亭いしだ」は、日替わりで地元演者の芸を披露し、加藤木朗も次男の晟弥(せいや)、次女の野詠(のえ)を伴ってときおり出演する。
昨年のある日、能舞台での出演をおえたら、「よかったですよ」と声をかけてくださったのが志の輔師匠であった。「いつかご一緒しましょう」とおっしゃってくださったそうだ。
それが早くも実現したのである。
「志の輔独演会のチケットは入手がむずかしいよ」と弟の雅義が云っていた通り、3月10日チケット発売と同時に、電話申し込みは30秒ほどで完売になり、和力ファンの何人かは完敗、雅義はインターネットでなんとか三日間のチケットを確保した。インターネット申し込みも30分で完売になったと雅義が云っていた。
わたしと妻は、一人4枚までという購入制限があったチケットを雅義からまわしてもらって、3日の舞台を観ることができた。
舞台の様子は、3日間すべてを観た雅義の記録をここに転載する。

加藤木 雅義の記録
今日から3日間は、横浜にぎわい座です。横浜での初舞台。メジャー師匠との舞台初共演。
立川志の輔師匠の前座として、和力が出演しました。
師匠を聴きにきたお客様が和力をどう受け止めてくださるのか、見どころ満載の舞台でした。
会場では進行を告げるプログラムは渡されません。
見る側として、ぶっつけ本番。さてどんな進み方をするのでしょう。
わたしが知りたかったのは次の3点でした。
① 和力の出番は、独演会のプログラムのどこに来るのか?
② 割り当て時間は何分?
③ 本番で、和力は最初に何の演目をぶつけてくるのか?
でした。
第一日目の和力メンバーは、いつもに増して気合が入っていました。
休憩が終わった後の第二部冒頭で登場。
だんじり囃子でお客様を圧倒しました。小野さん、木村さんの津軽三味線の音色も冴えわたった。
鶏舞のジャンプ力の高さに、隣の座席ではため息がもれていました。
名古屋からわざわざお越し下さった、加藤木教室の生徒さんおふたりは、和力出演中、周囲のみなさんの反応に耳をそばだてていたそうです。
にぎわい座の初日は、以下のプログラムで進みました。
落語30分
落語40分
(休憩)
和力30分
(だんじり囃子、津軽じょんから節、忍者、鶏舞)
落語40分
開演 午後6時半
終演 午後9時10分
和力の出番は30分でしたが、気魄のこもった舞台でした。

にぎわい座、第二日目。
本番中、初日にはなかった出演者紹介をしました。緊張がほぐれてきたのかもしれません。
和力は初日と演目を替えて舞台にのぞんできました。
① 鹿踊り
② 三味線と篠笛の合奏(こきりこ節、砂山)
③ 獅子舞
④ だんじり囃子
以上で、ぴったり30分。出演順は、昨日と同じ。
第一部が終了すると幕が降り10分間の休憩にはいります。
第二部開始。
落語の出囃子が流れ、スルスルと幕があがると鹿踊りの装束に身をかためた朗が後ろ向きに立っています。
見慣れない出で立ちに、「一体何がはじまるの?」という戸惑いの空気が会場に流れます。
和力ファンにはお馴染みでも、志の輔師匠を聴きにきたお客様にとっては異様な風景として映ったに違いありません。
客席にいてもアウエー感が漂います。
鹿踊りが終わって、朗のMCがはいりようやくお客様の戸惑いが少なくなる。
「ここから、私は楽屋にさがりますが、その退場の仕方が大変なので笑わないでくださいね」と、あらかじめ朗の説明。
にぎわい座は寄席風に作られていますので、舞台から楽屋に通じる出入り口は木戸です。噺家さんが通ることだけを想定した高さ一間、幅が半間の小さな空間。
ところが、頭上にササラという飾りを押し立てた「鹿」は優に2メートル半くらいの高さがあります。さてどうやって帰るのか?
「ザリガニが巣に戻るようになります」と予言したとおり、朗は後ろを振り向きお尻から先に木戸に入れて、お辞儀をする格好で楽屋に入っていった。
ササラがハサミのように映り本当にザリガニが巣に帰るような図だったのです。その姿が可笑しいとお客様が喜び会場の空気がなごんだ。
すでに客席は和力のペースです。
富山出身の、志の輔師匠を意識してか、富山県に伝わる「こきりこ節」を演奏し、初日にはなかった獅子舞が舞台で跳ねました。
猫のような仕草で耳をピクピクさせる場面で会場は沸きます。
そして流れるようにだんじり囃子に移り30分の持ち時間、ぴったりと終了したのです。
演目の構成も最高で、短さを感じさせない見応えのある舞台でした。
2階席に陣取ったわが特派員は、最前列のお客様が目の前の手すりに掴まり、演技が進むにしたがい身を乗り出していった、と終演後、語っています。
こちらは1階席。
だんじり囃子が終わったとき、たくさんのお客様が頭上に手をそろえ拍手しているのを目にしました。

にぎわい座三日目
せっかく独演会に来ているのですから、師匠のお噺もレポートします。
3つの演題のうち、第一席は「ハナコ」。3人のサラリーマンが黒毛和牛食べ放題を目当てに温泉宿にいく物語です。
いざ、食事になるときに宿屋の主人が、これから料理するという牛を、生きたまま部屋に連れてきて宿泊客に紹介する。
「名はハナコと申します」。客は驚いて、「名前を言うな。愛情がわいて食べる気がなくなってしまう」と怒りだす騒動を描いて会場の爆笑を誘っていました。
楽日の和力の演目は、
① 荒馬の踊りから、番楽の舞→狐の面を被っての舞
② 津軽じょんから節→忍者
③ だんじり囃子
の3点でした。
第二部。
いつものように幕が開くと、朗が客席から荒馬の装束をつけて登場。登場の仕方が意表を突いて、そして見なれない装束。
昨日に引き続いてお客様は、一体、何が始まるのかとポカンとしています。
朗は口上を述べて舞台に上がり、荒馬の舞。荒馬を脱ぎ捨てて番楽の踊り。すぐに面をつけて狐の舞を披露します。今日は舞の大サービスなのでしょう。
でも、まだ客席は戸惑ったままです。
津軽三味線の独奏→合奏で、ようやくお客様の頭がリズムに乗って小さく揺れ始めます。
こちらは、少しは耳馴染んだ音だったのかもしれません。
客席が和んだところで、だんじり囃子が始まる前に朗がお客様に楽器の説明を始めます。
「長唄などの細い竿の三味線に貼られているのが• • •タマです」。すると、客席は「そうらしい」とうなずく気配。
「津軽三味線は太い竿なので貼られているのは• • •ポチです」「なるほど、そうなのか」と納得するお客様。
イヌネコと表現しないのが、直接的でなく良い感じです。
そして次に朗が指し示したのがこれから演奏する宮太鼓です。
「この太鼓に貼られているのが• • •」…やや間があったので、お客様の頭の中で
「貼られているのは・・・」と反芻するのが見えます。
その間合いをみて、すかさず朗が「ハナコです」と言います。
たった今、聴いた噺と関連づけられたのですから、客席は笑いの渦に包まれます。
最初に戸惑っていた分、この笑いの爆発力は大きなものがありました。
きっと、これも朗の計算のうちだったのかもしれません。
だんじり囃子が終わると、2階席から「イイぞ!」と野太い声が掛かり、
指笛までが鳴った最終舞台でした。
超一流の噺家さんを聴きにきた耳の肥えたお客さんを向こうにまわし、演奏も舞も、そしてトークも冴えて、和力の3日間はこうして幕を閉じたのです。