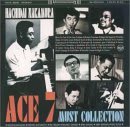柳ジョージ。
レイニーウッドでの活躍を知らない世代の私にとって、
初めて意識したのはゴールデン・カップスの「スーパー・ライブ・セッション」か、
パワーハウスのアルバムか、はたまたストロベリーパスだったか。
そう確実に私の中の柳ジョージのイメージは、ジャック・ブルース並みの
ベースプレイが出来る素晴らしいニューロック・プレイヤー、というものである。
(日比谷野音でロケットベースを持っている写真があるのだがすごく格好良い!)
さて今回は柳ジョージの著書『敗者復活戦』について。
この本は1979年11月15日小学館から780円で発売されたものである。
表の帯文句には、
「一度や二度失敗したってどうってことはないぜ!
柳ジョージが熱く語る”生きる”醍醐味!!」とある。
裏の帯文句には、
「ポール・アンカでロックに目醒める。ビートルズ衝撃をうける。
GS旋風に巻きこまれる。3日でサラリーマン廃業。ロンドン放浪3か月。
レイニー・ウッド結成。2度目の敗北。竜馬に触発される。
ショーケンと出会う。 そしていま・・・・。
30歳。不器用な男、柳ジョージ、魂のメッセージ!!」とある。
「柳ジョージとレイニー・ウッド」での成功を受けて書かれたと思われる本書は、
裏の帯文句を読んでいただければ分かっていただけると思うが、
敗者のように紆余曲折を得てきた酒に弱い不器用な男がレイニー・ウッドで
成功を得る(=敗者復活戦)までの軌跡を描いた自叙伝である。
これが面白かった。時代が面白いというのもあるし、
やはりYOKOHAMA(本書では「横浜」ではなく何故かアルファベット・笑)出身
ということもあるのかも知れない。ニューロックファンにとっては、
ムー~べべズ~パワーハウス~カップスまでの流れとカップスが解散してから
成毛茂と訪れたイギリスでの様子(ハンブル・パイを見て再びやる気が出たという、うらやましい!その他フリートウッド・マックやロッド・スチュワートなどを見たと書いてある)が生々しくて興味をそそられるだろう。
日本のブルースブレーカーズといまや言われるようになった
横浜の最重要バンド「べべズ」の解散秘話やパワーハウスの様子、
またはカップスでの日々なんて全くもって面白い!
カップスのラストライブ(あの沖縄のステージで火事になったという)は、
昨年めでたく劇場公開され7月に3枚組というボリュームでDVD化されることも
決まったゴールデン・カップスの映画『ワン・モア・タイム』で
各メンバーによって真相が語られているが、
1979年当時にも柳ジョージによって語られていたのだ!
しかも映画よりも詳しく書かれている。
ただそれだけでなく人間としての弱みを素直に表現しているところに共感ももて、
非常に面白く読んだ。サラリーマンをやるも机に向かい続ける人生に疑問を感じ、
3日で止めたこと(ちょっと早く止めすぎだと思うが・・・)、結婚しようと思ってた
彼女の父親を前に大事な一言を言いそびれてしまったこと、酒に弱いこと
(お酒自体は凄く呑めると思われるが呑まずにはいられないということ)などなど。
どれも大人になっていく中で誰もが経験する甘酸っぱい思い出である。
彼も一人の人間なんだなと思った。
これを読んでレイニー・ウッドも聞いてみたくなった。
イメージでは売れたメジャーなバンドというのがあって良いイメージがないけど、
ひょっとしたら凄く格好良いのかもしれない。
でもやっぱり私にとっての柳譲治(最初はこの字でした)は、
最初にあげたようなバリバリのニューロック・プレーヤーである。
一番好きなのはゴールデン・カップスでのプレイ。
特にカップスの「ライブ!ザ・ゴールデン・カップス」での、
これでもかとファズがかかったぶっとい超絶ベースプレイは鳥肌ものである。
その前作「フィフス・ゼネレーション」も良い。
今までは私の記憶だと陳信輝のソロ作やストロベリーパスでのプレイなどの
71年からレイニー・ウッドまで、その活動は途切れ
(活動はしていたと思うが音盤化はされていない)、
その間何をやっていたのか分からなかったが最近CDでリリースされた1974年の
『ワンステップ・フェスティバル』で「デイブ平尾&ゴールデン・カップス」に
ギターとして参加した柳ジョージのプレイが聞くことが出来る。
文章ではママリンゴやニューゴールデンカップスなど語られてはいたものの、
初めてそれが音源化された。この意義は大きい。
ちなみにこの時のメンバーは、デイブ平尾(Vo)・柳ジョージ(G,Cho)・
蜂谷吉泰(G,Cho)・加部正義(B)・金沢純(Ds)である。
この後くらいに広島で活躍していたバンド、メイフラワー(後のレイニーウッド)
出会うわけだが、このバンドの元々のリーダーは「上久保ジュン」という。
この間ディスクユニオンの「富士」レーベルからCD化されたニューロックの
最後の砦とも言うべき「ジュン上久保」とは違う人物なのだろうか。
ライナーには「経歴が謎」とあったのだけれど、一体どうなのだろうか。
気になります。もし分かる方がいらしたらご一報下さい。
最後に本書には写真が数枚だが載っていてこれがすごく貴重。
一つは成毛茂と思われる人物と羽田空港のロビーで一緒写っている写真。
もう一つはカップス時代のもので、何かの雑誌で使われたのであろう、
モップス、ハプニングス・フォー、そしてもう一バンド(名前分かりません)、
計四バンドの集合写真。皆さんこれでもかというくらい髪が長い。
実は古本屋で、こんなすごい写真見たことない!と思って
レジへ駆け込んでしまったのである。
この本はそんなに珍しくないと思うので、興味がある方は是非読んでみて下さい。
レイニーウッドでの活躍を知らない世代の私にとって、
初めて意識したのはゴールデン・カップスの「スーパー・ライブ・セッション」か、
パワーハウスのアルバムか、はたまたストロベリーパスだったか。
そう確実に私の中の柳ジョージのイメージは、ジャック・ブルース並みの
ベースプレイが出来る素晴らしいニューロック・プレイヤー、というものである。
(日比谷野音でロケットベースを持っている写真があるのだがすごく格好良い!)
さて今回は柳ジョージの著書『敗者復活戦』について。
この本は1979年11月15日小学館から780円で発売されたものである。
表の帯文句には、
「一度や二度失敗したってどうってことはないぜ!
柳ジョージが熱く語る”生きる”醍醐味!!」とある。
裏の帯文句には、
「ポール・アンカでロックに目醒める。ビートルズ衝撃をうける。
GS旋風に巻きこまれる。3日でサラリーマン廃業。ロンドン放浪3か月。
レイニー・ウッド結成。2度目の敗北。竜馬に触発される。
ショーケンと出会う。 そしていま・・・・。
30歳。不器用な男、柳ジョージ、魂のメッセージ!!」とある。
「柳ジョージとレイニー・ウッド」での成功を受けて書かれたと思われる本書は、
裏の帯文句を読んでいただければ分かっていただけると思うが、
敗者のように紆余曲折を得てきた酒に弱い不器用な男がレイニー・ウッドで
成功を得る(=敗者復活戦)までの軌跡を描いた自叙伝である。
これが面白かった。時代が面白いというのもあるし、
やはりYOKOHAMA(本書では「横浜」ではなく何故かアルファベット・笑)出身
ということもあるのかも知れない。ニューロックファンにとっては、
ムー~べべズ~パワーハウス~カップスまでの流れとカップスが解散してから
成毛茂と訪れたイギリスでの様子(ハンブル・パイを見て再びやる気が出たという、うらやましい!その他フリートウッド・マックやロッド・スチュワートなどを見たと書いてある)が生々しくて興味をそそられるだろう。
日本のブルースブレーカーズといまや言われるようになった
横浜の最重要バンド「べべズ」の解散秘話やパワーハウスの様子、
またはカップスでの日々なんて全くもって面白い!
カップスのラストライブ(あの沖縄のステージで火事になったという)は、
昨年めでたく劇場公開され7月に3枚組というボリュームでDVD化されることも
決まったゴールデン・カップスの映画『ワン・モア・タイム』で
各メンバーによって真相が語られているが、
1979年当時にも柳ジョージによって語られていたのだ!
しかも映画よりも詳しく書かれている。
ただそれだけでなく人間としての弱みを素直に表現しているところに共感ももて、
非常に面白く読んだ。サラリーマンをやるも机に向かい続ける人生に疑問を感じ、
3日で止めたこと(ちょっと早く止めすぎだと思うが・・・)、結婚しようと思ってた
彼女の父親を前に大事な一言を言いそびれてしまったこと、酒に弱いこと
(お酒自体は凄く呑めると思われるが呑まずにはいられないということ)などなど。
どれも大人になっていく中で誰もが経験する甘酸っぱい思い出である。
彼も一人の人間なんだなと思った。
これを読んでレイニー・ウッドも聞いてみたくなった。
イメージでは売れたメジャーなバンドというのがあって良いイメージがないけど、
ひょっとしたら凄く格好良いのかもしれない。
でもやっぱり私にとっての柳譲治(最初はこの字でした)は、
最初にあげたようなバリバリのニューロック・プレーヤーである。
一番好きなのはゴールデン・カップスでのプレイ。
特にカップスの「ライブ!ザ・ゴールデン・カップス」での、
これでもかとファズがかかったぶっとい超絶ベースプレイは鳥肌ものである。
その前作「フィフス・ゼネレーション」も良い。
今までは私の記憶だと陳信輝のソロ作やストロベリーパスでのプレイなどの
71年からレイニー・ウッドまで、その活動は途切れ
(活動はしていたと思うが音盤化はされていない)、
その間何をやっていたのか分からなかったが最近CDでリリースされた1974年の
『ワンステップ・フェスティバル』で「デイブ平尾&ゴールデン・カップス」に
ギターとして参加した柳ジョージのプレイが聞くことが出来る。
文章ではママリンゴやニューゴールデンカップスなど語られてはいたものの、
初めてそれが音源化された。この意義は大きい。
ちなみにこの時のメンバーは、デイブ平尾(Vo)・柳ジョージ(G,Cho)・
蜂谷吉泰(G,Cho)・加部正義(B)・金沢純(Ds)である。
この後くらいに広島で活躍していたバンド、メイフラワー(後のレイニーウッド)
出会うわけだが、このバンドの元々のリーダーは「上久保ジュン」という。
この間ディスクユニオンの「富士」レーベルからCD化されたニューロックの
最後の砦とも言うべき「ジュン上久保」とは違う人物なのだろうか。
ライナーには「経歴が謎」とあったのだけれど、一体どうなのだろうか。
気になります。もし分かる方がいらしたらご一報下さい。
最後に本書には写真が数枚だが載っていてこれがすごく貴重。
一つは成毛茂と思われる人物と羽田空港のロビーで一緒写っている写真。
もう一つはカップス時代のもので、何かの雑誌で使われたのであろう、
モップス、ハプニングス・フォー、そしてもう一バンド(名前分かりません)、
計四バンドの集合写真。皆さんこれでもかというくらい髪が長い。
実は古本屋で、こんなすごい写真見たことない!と思って
レジへ駆け込んでしまったのである。
この本はそんなに珍しくないと思うので、興味がある方は是非読んでみて下さい。