 朝は6時前に目覚めてしまった。部屋のビューバスに横たわり、長々と寛いだが、妻がまだ起きない。外に散歩に出る。
朝は6時前に目覚めてしまった。部屋のビューバスに横たわり、長々と寛いだが、妻がまだ起きない。外に散歩に出る。6:57 ホテルの前には小さいながらビーチがある。釣り人がいる。小舟が沖を行く。
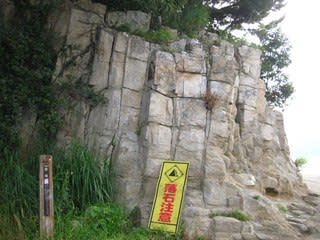 本土とは埋立地と橋を介して繋がっているものの、ここは島だ。その成り立ちは自然観察の対象となるらしい。柱状節理。先ほどは「断層」もあった。
本土とは埋立地と橋を介して繋がっているものの、ここは島だ。その成り立ちは自然観察の対象となるらしい。柱状節理。先ほどは「断層」もあった。 島の南端をめぐっている。この後、海岸沿いをそれ、山道を灯台まで登っていく。朝からセミが盛んに鳴いている。朝風呂に入ったのに汗ばんできてしまった。…さて、ホテルに戻り朝食ビュッフェだ。
島の南端をめぐっている。この後、海岸沿いをそれ、山道を灯台まで登っていく。朝からセミが盛んに鳴いている。朝風呂に入ったのに汗ばんできてしまった。…さて、ホテルに戻り朝食ビュッフェだ。 ホテルからのバスを、平和大通り近くのバス停で降りる。陽射しがかなり強く、セミが大合唱。
ホテルからのバスを、平和大通り近くのバス停で降りる。陽射しがかなり強く、セミが大合唱。9:42 平和大橋を渡る。欄干が独特のフォルムをしている。彫刻家イサム・ノグチのデザイン。昭和27(1952)年完成。
 橋を渡った元安川、そして本川に囲まれた中州一帯が平和記念公園。平和記念資料館を見学する。原爆のむごさ、戦争の愚かさをあらためて実感する。高校の修学旅行でも来たが、その時に比べ、展示の生々しさが弱まっている気がする。人形による被害の再現などはなくなっている。いいのか悪いのか、往時より洗練されている。しかし、ひとつひとつじっくり眺めれば、伝わってくるメッセージはやはり切実だ。
橋を渡った元安川、そして本川に囲まれた中州一帯が平和記念公園。平和記念資料館を見学する。原爆のむごさ、戦争の愚かさをあらためて実感する。高校の修学旅行でも来たが、その時に比べ、展示の生々しさが弱まっている気がする。人形による被害の再現などはなくなっている。いいのか悪いのか、往時より洗練されている。しかし、ひとつひとつじっくり眺めれば、伝わってくるメッセージはやはり切実だ。 原爆死没者慰霊碑。アーチの中を視線が抜けた先に原爆ドームがある。公園の設計は丹下健三。外国人観光客がこの前で笑顔で記念撮影をしている。笑顔じゃないだろ、と思う。
原爆死没者慰霊碑。アーチの中を視線が抜けた先に原爆ドームがある。公園の設計は丹下健三。外国人観光客がこの前で笑顔で記念撮影をしている。笑顔じゃないだろ、と思う。 台座の上で「平和の灯」が燃えている。資料館を振り返る。資料館中央部からここを通り原爆ドームへ、真っ直ぐな軸線が貫いている。8月6日の平和祈念式典に向けて、敷地内にはテントが設営されている。
台座の上で「平和の灯」が燃えている。資料館を振り返る。資料館中央部からここを通り原爆ドームへ、真っ直ぐな軸線が貫いている。8月6日の平和祈念式典に向けて、敷地内にはテントが設営されている。 11:27 原爆ドーム。あの日もこんな風に暑い日だったんだろうか。脇の相生橋を市電が渡る。
11:27 原爆ドーム。あの日もこんな風に暑い日だったんだろうか。脇の相生橋を市電が渡る。 爆心地。この内科医院の上空600mで原爆が炸裂した。一帯は3000~4000℃の熱線と爆風、放射線を受け、ほとんどの人々が瞬時に命を奪われたという。今は近隣のデパート提携の立体駐車場入庫待ちの車で混雑している。
爆心地。この内科医院の上空600mで原爆が炸裂した。一帯は3000~4000℃の熱線と爆風、放射線を受け、ほとんどの人々が瞬時に命を奪われたという。今は近隣のデパート提携の立体駐車場入庫待ちの車で混雑している。 市電の走る相生通りに出る。この背後には、取り壊されて更地になった広島市民球場が。跡地には文化芸術施設やイベント施設が造られるらしい。
市電の走る相生通りに出る。この背後には、取り壊されて更地になった広島市民球場が。跡地には文化芸術施設やイベント施設が造られるらしい。 11:52 炎天下の舗道をとぼとぼと歩き続け、広島城へ。御門橋と表御門。
11:52 炎天下の舗道をとぼとぼと歩き続け、広島城へ。御門橋と表御門。 被爆したユーカリの木。ここは爆心地からおよそ740m。そばの建物群が炎上する中、この木だけ生き残ったという。そして今も齢を重ねている。
被爆したユーカリの木。ここは爆心地からおよそ740m。そばの建物群が炎上する中、この木だけ生き残ったという。そして今も齢を重ねている。 天守閣。原爆で倒壊したが、昭和33(1958)年にコンクリート建築で復元。中は博物館になっている。川(太田川)の流れが幾筋にも別れ、島や砂州が点在していた広島。「天然の堀」が得られることと、川の水運を活用できることが、ここに城の築かれる理由になったのだろうか。
天守閣。原爆で倒壊したが、昭和33(1958)年にコンクリート建築で復元。中は博物館になっている。川(太田川)の流れが幾筋にも別れ、島や砂州が点在していた広島。「天然の堀」が得られることと、川の水運を活用できることが、ここに城の築かれる理由になったのだろうか。 天守閣の中が冷房完備であるわけもなく、暑さで展示物の見学も早回し気味。しかし最上階で外に出ると、吹き抜ける風が思いのほか心地よい。南側、原爆ドーム方面の眺め。
天守閣の中が冷房完備であるわけもなく、暑さで展示物の見学も早回し気味。しかし最上階で外に出ると、吹き抜ける風が思いのほか心地よい。南側、原爆ドーム方面の眺め。 城を出ると、またしても輻射が激しく日陰もないアスファルト、コンクリートが続く。目指す縮景園のすぐ手前で、たまりかねて県立美術館のロビーに逃げ込む。縮景園の庭を見下ろす素敵な空間。何より冷房が効いている。汗を引かせる。
城を出ると、またしても輻射が激しく日陰もないアスファルト、コンクリートが続く。目指す縮景園のすぐ手前で、たまりかねて県立美術館のロビーに逃げ込む。縮景園の庭を見下ろす素敵な空間。何より冷房が効いている。汗を引かせる。 縮景園に入るも、見学前にまずは茶店へ。東屋で白玉クリームあんみつ。屋外でも日陰にいると意外としのげる。まして冷たいものを口にすれば。
縮景園に入るも、見学前にまずは茶店へ。東屋で白玉クリームあんみつ。屋外でも日陰にいると意外としのげる。まして冷たいものを口にすれば。 広島浅野藩初代藩主・長晟が1620年から造成。大火や改修を経て、戦前に広島県へ寄贈される。原爆投下の被害を受けたが、その後、少しずつ復元されていった。
広島浅野藩初代藩主・長晟が1620年から造成。大火や改修を経て、戦前に広島県へ寄贈される。原爆投下の被害を受けたが、その後、少しずつ復元されていった。 木立ちのトンネルは心が休まる。
木立ちのトンネルは心が休まる。 しかしまた町へ出れば、そこは大都市、なんとも非人間的な灼熱空間が広がる。旅の印象として記憶に刻みたくもないので、早足で通り過ぎる。汗が噴き出る。
しかしまた町へ出れば、そこは大都市、なんとも非人間的な灼熱空間が広がる。旅の印象として記憶に刻みたくもないので、早足で通り過ぎる。汗が噴き出る。14:18 京橋川に架かる稲荷橋。爆心地からおよそ1.35km。原爆の爆風でレールが波打ち、川には無数の死体が浮かんだという。広島の町中はどこも、原爆の記憶が刻まれている。
 3連接の大型車両が路上を走るのが広島市電の特徴。
3連接の大型車両が路上を走るのが広島市電の特徴。 14:39 繁華街・新天地に入り、遅い昼食。広島焼きを食べてみようとやってきた。昭和22(1947)年創業の「へんくつや」。
14:39 繁華街・新天地に入り、遅い昼食。広島焼きを食べてみようとやってきた。昭和22(1947)年創業の「へんくつや」。 「お好み焼き そばスペシャル 肉玉・イカ・エビ入り」(1100円)と「お好み焼き 肉玉入り」(700円)。広島のお好み焼きは関西のとは異なり、具と生地を混ぜ合わせず、炒めた具や麺の上に薄い生地をかぶせる。つまり「魚介肉野菜焼きそば・クレープのせ」といった感じ。正直なところ、これは妻とも一致した意見だが、具・麺と生地が一体化していないのは、それぞれをバラバラに食べているようなもので、あまり「お好み焼き」という感じがしなかった。まあ、あまり好みではなかったということ。しかし、何事も一度は経験してみないことにはね。
「お好み焼き そばスペシャル 肉玉・イカ・エビ入り」(1100円)と「お好み焼き 肉玉入り」(700円)。広島のお好み焼きは関西のとは異なり、具と生地を混ぜ合わせず、炒めた具や麺の上に薄い生地をかぶせる。つまり「魚介肉野菜焼きそば・クレープのせ」といった感じ。正直なところ、これは妻とも一致した意見だが、具・麺と生地が一体化していないのは、それぞれをバラバラに食べているようなもので、あまり「お好み焼き」という感じがしなかった。まあ、あまり好みではなかったということ。しかし、何事も一度は経験してみないことにはね。 陽射しから逃れられるアーケードの本通り商店街を歩き、広島の物産を集めた店で、つけ麺や牡蠣の缶詰などをお土産に買う。再び原爆ドームに着き、その名も「原爆ドーム前」停留所から市電に乗る。広島の市電は営業距離、利用者数、車両数いずれも日本一の規模を誇り、本当はもっと乗り回したかったのだが、乗ったのはこの旅でこれが最初で最後となった。広島駅へ向かう。
陽射しから逃れられるアーケードの本通り商店街を歩き、広島の物産を集めた店で、つけ麺や牡蠣の缶詰などをお土産に買う。再び原爆ドームに着き、その名も「原爆ドーム前」停留所から市電に乗る。広島の市電は営業距離、利用者数、車両数いずれも日本一の規模を誇り、本当はもっと乗り回したかったのだが、乗ったのはこの旅でこれが最初で最後となった。広島駅へ向かう。【広島16:17―(のぞみ42号)→20:13東京】










 【東京7:50―(のぞみ13号)→11:49広島12:00―(山陽本線)→12:28宮島口】
【東京7:50―(のぞみ13号)→11:49広島12:00―(山陽本線)→12:28宮島口】 電車に4時間半も揺られてきたのでお腹が空いていた。
電車に4時間半も揺られてきたのでお腹が空いていた。 厳島神社へ向けて参道を歩き出すが、すぐに立ち止まる。広島に来たらこれも食べておかないと。
厳島神社へ向けて参道を歩き出すが、すぐに立ち止まる。広島に来たらこれも食べておかないと。 「生産者が営むカキ料理店」というふれこみの「沖野水産」店頭で焼き立ての牡蠣。1個200円。牡蠣は苦手だが、これは食べやすかった。産地で食べると違うのかな。牡蠣のシーズンは「スペルに<R>のある月」と聞いたことがある。つまり9月から3月。今は旬とは言えないのかも知れないが、僕には充分美味しかった。
「生産者が営むカキ料理店」というふれこみの「沖野水産」店頭で焼き立ての牡蠣。1個200円。牡蠣は苦手だが、これは食べやすかった。産地で食べると違うのかな。牡蠣のシーズンは「スペルに<R>のある月」と聞いたことがある。つまり9月から3月。今は旬とは言えないのかも知れないが、僕には充分美味しかった。 参道商店街の真ん中にある世界一のしゃもじ。長さ7.7m、重さ2.5tだそう。この後、参道商店街の「一松堂」で、しゃもじは買わなかったけど、木のスプーンを2本買った。蓮華としても使えそうな深めの物。
参道商店街の真ん中にある世界一のしゃもじ。長さ7.7m、重さ2.5tだそう。この後、参道商店街の「一松堂」で、しゃもじは買わなかったけど、木のスプーンを2本買った。蓮華としても使えそうな深めの物。 13:53 ご飯を食べたり買い食いをしたりお土産を眺めたり、だいぶ寄り道をしたけど、いよいよ目的地、厳島神社へ。高校の修学旅行以来の訪問。しかし陽射しの強い日だ。砂地の地面からの照り返しも激しい。
13:53 ご飯を食べたり買い食いをしたりお土産を眺めたり、だいぶ寄り道をしたけど、いよいよ目的地、厳島神社へ。高校の修学旅行以来の訪問。しかし陽射しの強い日だ。砂地の地面からの照り返しも激しい。 そこらじゅうに鹿がいるのだが、この暑さで鹿も日陰でぐったり。
そこらじゅうに鹿がいるのだが、この暑さで鹿も日陰でぐったり。 今日の宮島は13:36が満潮時刻。つまりちょうど今頃が一番海面が高い。
今日の宮島は13:36が満潮時刻。つまりちょうど今頃が一番海面が高い。 海の上にいると、心なしか風は感じられるかな。創建は593年。1168年に平清盛が現在の規模に造営した。
海の上にいると、心なしか風は感じられるかな。創建は593年。1168年に平清盛が現在の規模に造営した。 高さ16m、「木造の鳥居としては国内最大級」という海上の大鳥居。根元が地盤に打ち込まれているわけではなく、「置かれているだけ」というのがすごい。自重を支えにして立っている。
高さ16m、「木造の鳥居としては国内最大級」という海上の大鳥居。根元が地盤に打ち込まれているわけではなく、「置かれているだけ」というのがすごい。自重を支えにして立っている。 14:34 神社を出て、この小川を見つけて流れに足を浸したくなり、近くの売店でかき氷を買ってきて休憩。
14:34 神社を出て、この小川を見つけて流れに足を浸したくなり、近くの売店でかき氷を買ってきて休憩。 紅葉谷公園を抜ける。今は深緑が綺麗だけど、その名の通り紅葉も見事だろう。
紅葉谷公園を抜ける。今は深緑が綺麗だけど、その名の通り紅葉も見事だろう。 15:08 弥山を目指し、ロープウェイに乗る。2本のロープウェイを乗り継ぐ。まずは小型のもの。「8人乗り」と書かれているけど、「超小型」なので4人も座れば充分いっぱいという感じ。ましてこの炎天下で、空調なしだからね。
15:08 弥山を目指し、ロープウェイに乗る。2本のロープウェイを乗り継ぐ。まずは小型のもの。「8人乗り」と書かれているけど、「超小型」なので4人も座れば充分いっぱいという感じ。ましてこの炎天下で、空調なしだからね。 山の中腹で30人乗りの大型のものに乗り換える。神社とは島の反対側(四国側)の海が見えてくる。
山の中腹で30人乗りの大型のものに乗り換える。神社とは島の反対側(四国側)の海が見えてくる。 島を17:00に出る船に乗らなくてはならない。逆算すると、帰りは16:15のロープウェイで下山しなくてはならない。今から45分くらいで、ロープウェイの頂上駅から「往復所要1時間」とパンフレットに記載されている弥山山頂までの登山道を行って帰ってこようとしている。なかなか慌ただしい。しかしこれが今日のハイライトイベントである。
島を17:00に出る船に乗らなくてはならない。逆算すると、帰りは16:15のロープウェイで下山しなくてはならない。今から45分くらいで、ロープウェイの頂上駅から「往復所要1時間」とパンフレットに記載されている弥山山頂までの登山道を行って帰ってこようとしている。なかなか慌ただしい。しかしこれが今日のハイライトイベントである。 山頂に近づくにつれ大岩が現れる。不動岩。
山頂に近づくにつれ大岩が現れる。不動岩。 15:47 弥山山頂(535m)。「神社の裏山」感覚ではない、なかなかボリュームのある山。標高500m台という意味では高尾山と変わらない。宮島をなんとなく江の島と似たようなイメージで捉えていたが、かなり違う。
15:47 弥山山頂(535m)。「神社の裏山」感覚ではない、なかなかボリュームのある山。標高500m台という意味では高尾山と変わらない。宮島をなんとなく江の島と似たようなイメージで捉えていたが、かなり違う。 四国側の眺め。
四国側の眺め。 宮島港と広島市街方面の眺め。それにしても暑い。汗をかいたシャツはあとで塩を吹くに違いない。
宮島港と広島市街方面の眺め。それにしても暑い。汗をかいたシャツはあとで塩を吹くに違いない。 神社まで下りると、境内の潮が引いて、先ほどまで海だったところの地面が見えていた。
神社まで下りると、境内の潮が引いて、先ほどまで海だったところの地面が見えていた。 ロープウェイを降りてから桟橋まで急ぎ足で来たので、大汗をかいていた。エアコンの効いた船室のサロン状のソファで休む。しかし、船ならやはり風を感じたいと、デッキに上がる。宮島が早くも遠ざかる。
ロープウェイを降りてから桟橋まで急ぎ足で来たので、大汗をかいていた。エアコンの効いた船室のサロン状のソファで休む。しかし、船ならやはり風を感じたいと、デッキに上がる。宮島が早くも遠ざかる。 17:24 船は今日泊まるホテルの目の前に着く。船で宿に上陸、なかなかない体験だ。広島市街地から離れているこのホテル、夕食もこのホテルの中で完結させなくてはならない。夏季限定のビアガーデンがあったがすでに満席だった。中華料理店が予約できたが、入れるのは20:30から。温泉に入ってもまだ食事まで時間があったので、最上階のバーで1杯。こんな気障なことをしたのは初めてだが、これも同伴者がいるからこそ決意できることか。ウォッカ、カカオ、生クリームのカクテル「バーバラ」で、1時間ほど寛ぐ。生バンドの演奏があって、広島市街地の夜景があって。印象的な夜になった。ほろ酔いで階下の中華料理店に向かう。窓から海の向こうに花火(おそらく呉の花火大会だろう)が見えた。前菜盛り合わせ、薬膳スープ、パプリカと牛肉の細切り炒め、茄子とトマト入り海老のチリソース煮、瀬戸内産スズキの広東風蒸し物、サラダ冷麺、マンゴープリンクリームチーズソース。
17:24 船は今日泊まるホテルの目の前に着く。船で宿に上陸、なかなかない体験だ。広島市街地から離れているこのホテル、夕食もこのホテルの中で完結させなくてはならない。夏季限定のビアガーデンがあったがすでに満席だった。中華料理店が予約できたが、入れるのは20:30から。温泉に入ってもまだ食事まで時間があったので、最上階のバーで1杯。こんな気障なことをしたのは初めてだが、これも同伴者がいるからこそ決意できることか。ウォッカ、カカオ、生クリームのカクテル「バーバラ」で、1時間ほど寛ぐ。生バンドの演奏があって、広島市街地の夜景があって。印象的な夜になった。ほろ酔いで階下の中華料理店に向かう。窓から海の向こうに花火(おそらく呉の花火大会だろう)が見えた。前菜盛り合わせ、薬膳スープ、パプリカと牛肉の細切り炒め、茄子とトマト入り海老のチリソース煮、瀬戸内産スズキの広東風蒸し物、サラダ冷麺、マンゴープリンクリームチーズソース。