さて、新旧のディスクを比較してみます。

左新品、右使用済み
古いほうは若干テカってはいるものの、なんか全然磨り減っているようには見えません。厚みを比べても新品と大して変わりません。変質しているような雰囲気もありません。
直感的に、「なんか、コレ新品交換しても、タコメーターの症状は変わらない気が。。」しました。もともとそういうタコメーターだったんじゃないの?
それでもお手入れは決して無駄ではないので、構わないです!
クラッチの中身は、ディスク7枚(クランク動力側)と金属製プレート6枚(ミッション側)が交互に噛みあい、スプリングの力で張り付く仕組みです。クラッチレバーを操作すると、スプリングが縮んでディスクとプレートの密着が解放され、クランクの動力はミッションへ届かなくなり、クラッチが切れた状態となります。
仕組みを図説すると、次の通りと思われます。

超図解
なぜスプリングが縮むと、クラッチが切れるのかがどうしても理解できず、自分が理解するために書きました。この絵でも分かりにくいです。
クラッチ滑り解消のために交換するのならば、新品部品はディスクとプレートだけでOKです。なお一番外側のクラッチディスクだけ内寸が大きくなっていて、その内側にジャダースプリングというのが入ります。これは発進時のクラッチミートでガガッと衝撃が来るのを緩和するためのものだそうですが(理屈は不明)、ついでなのでこのジャダースプリングならびにスプリングが載るシートも交換することにしました。
それではクラッチセンタに、順番に新品部品を載せていきます。センターロックナットを破壊して外した際に金属粉が飛んでいる可能性があるので、センターや再利用するワッシャ類はパーツクリーナーでよく吹いておきます。清掃後は再度オイルを塗布しましょう。
始めにでっかいワッシャみたいなスプリングシートを載せます。
このシートにはウラとオモテがありますが、マニュアルにその記載はありません。外周のエッジが丸くなっている面と、直角に尖っている面です。

スプリングシート
原状では尖っている面がクラッチセンタの底部と密着するように置かれていたので、そのように組みました。

スプリングシートを取り付け
上の写真のクラッチセンターは、対面(右上)側がエンジンの外側、手前(左下)側がエンジンの内部側を向いているというポジションから、撮影しています。
続いてジャダースプリングを載せます。これは明らかにオモテ・ウラがある形状です。ワッカの断面図は水平「-」ではなく、傾斜「/」があります。マニュアルでもどの面を載せるかしっかり明記されています。

ジャダースプリング。黒っぽい
ジャダースプリングの内周が、先に取り付けたスプリングシートに密着するように置いて下さい。
下の写真に写っているのは外周ですから、当然スプリングシートとの間にスキマが生じています。しかしこれでピッタリくっついている状態なのです。

シートの上に、ジャダースプリングを取り付け
ここからディスクとプレートを載せていきます。ディスクには新しいオイルを塗布することを忘れずに!オイル無しで組み上げると、せっかく交換した新品クラッチディスクがいきなり焼きつくことがあるそうです。
まずクラッチディスクの一番外側の1枚を載せます。このディスクだけ他の6枚と異なり内寸が大きいのですが、このクラッチディスクは上に紹介したシートとスプリングの外側へ載せるためです。
あとは、クラッチプレート(金属)と、クラッチディスクを交互に6枚載せていきます。それぞれ6枚は全く同一の部品です。
下の写真は1+12枚全部を重ねて、クラッチセンターから抜いたものです。プレートの内側の歯に注目してください。

プレートの歯(おもて)
続いて、同じものをひっくり返した写真です。プレート内側の歯の様子を、上の写真と見比べてください。

プレートの歯(うら)
違いに気付きますでしょうか?前者はカドが取れていて、後者はカドが鋭角ですよね。プレートそのものには、明らかに裏と表があるようです。
このこともマニュアルには触れられていません。触れられていない以上は、ウラオモテは特に気にする必要は無いのかも知れませんが、とにかく取り外し前の原状がどうなっていたのかというと、この通りです。分解しながら写真を撮ってあったので、確認することができました。

分解中、クラッチセンターだけを取り外した時の写真
どうでしょう?全部向きが揃っていませんか?カドの取れている方が、外側を向いているようです。
一方のクラッチディスクにはいっさい裏表は無いようなので、特に考えずに組み付けました。
ここまで、かなり分かりにくかったと思うので、図解します。載せる向きに注意してみてください。

1.クラッチセンター

2.スプリングシートを載せる
(マニュアルにウラオモテの記載なし。カドが丸いほうが上に)

3.ジャダースプリングを載せる
(向きはマニュアル通り)

4.ディスク(内径大)を載せる

5.プレートを載せる
(マニュアルにウラオモテの記載なし)

6.残りのディスクとプレートを交互に載せる
(プレートは全部同じ向き)
この通り、組まれていた通りに組み上げました。何度も言いますが、マニュアルで指示の無い部分は、実はどうでも良いことなのかも分かりません。自分には判断が付きかねます。
(つづく)

左新品、右使用済み
古いほうは若干テカってはいるものの、なんか全然磨り減っているようには見えません。厚みを比べても新品と大して変わりません。変質しているような雰囲気もありません。
直感的に、「なんか、コレ新品交換しても、タコメーターの症状は変わらない気が。。」しました。もともとそういうタコメーターだったんじゃないの?
それでもお手入れは決して無駄ではないので、構わないです!
クラッチの中身は、ディスク7枚(クランク動力側)と金属製プレート6枚(ミッション側)が交互に噛みあい、スプリングの力で張り付く仕組みです。クラッチレバーを操作すると、スプリングが縮んでディスクとプレートの密着が解放され、クランクの動力はミッションへ届かなくなり、クラッチが切れた状態となります。
仕組みを図説すると、次の通りと思われます。

超図解
なぜスプリングが縮むと、クラッチが切れるのかがどうしても理解できず、自分が理解するために書きました。この絵でも分かりにくいです。
クラッチ滑り解消のために交換するのならば、新品部品はディスクとプレートだけでOKです。なお一番外側のクラッチディスクだけ内寸が大きくなっていて、その内側にジャダースプリングというのが入ります。これは発進時のクラッチミートでガガッと衝撃が来るのを緩和するためのものだそうですが(理屈は不明)、ついでなのでこのジャダースプリングならびにスプリングが載るシートも交換することにしました。
それではクラッチセンタに、順番に新品部品を載せていきます。センターロックナットを破壊して外した際に金属粉が飛んでいる可能性があるので、センターや再利用するワッシャ類はパーツクリーナーでよく吹いておきます。清掃後は再度オイルを塗布しましょう。
始めにでっかいワッシャみたいなスプリングシートを載せます。
このシートにはウラとオモテがありますが、マニュアルにその記載はありません。外周のエッジが丸くなっている面と、直角に尖っている面です。

スプリングシート
原状では尖っている面がクラッチセンタの底部と密着するように置かれていたので、そのように組みました。

スプリングシートを取り付け
上の写真のクラッチセンターは、対面(右上)側がエンジンの外側、手前(左下)側がエンジンの内部側を向いているというポジションから、撮影しています。
続いてジャダースプリングを載せます。これは明らかにオモテ・ウラがある形状です。ワッカの断面図は水平「-」ではなく、傾斜「/」があります。マニュアルでもどの面を載せるかしっかり明記されています。

ジャダースプリング。黒っぽい
ジャダースプリングの内周が、先に取り付けたスプリングシートに密着するように置いて下さい。
下の写真に写っているのは外周ですから、当然スプリングシートとの間にスキマが生じています。しかしこれでピッタリくっついている状態なのです。

シートの上に、ジャダースプリングを取り付け
ここからディスクとプレートを載せていきます。ディスクには新しいオイルを塗布することを忘れずに!オイル無しで組み上げると、せっかく交換した新品クラッチディスクがいきなり焼きつくことがあるそうです。
まずクラッチディスクの一番外側の1枚を載せます。このディスクだけ他の6枚と異なり内寸が大きいのですが、このクラッチディスクは上に紹介したシートとスプリングの外側へ載せるためです。
あとは、クラッチプレート(金属)と、クラッチディスクを交互に6枚載せていきます。それぞれ6枚は全く同一の部品です。
下の写真は1+12枚全部を重ねて、クラッチセンターから抜いたものです。プレートの内側の歯に注目してください。

プレートの歯(おもて)
続いて、同じものをひっくり返した写真です。プレート内側の歯の様子を、上の写真と見比べてください。

プレートの歯(うら)
違いに気付きますでしょうか?前者はカドが取れていて、後者はカドが鋭角ですよね。プレートそのものには、明らかに裏と表があるようです。
このこともマニュアルには触れられていません。触れられていない以上は、ウラオモテは特に気にする必要は無いのかも知れませんが、とにかく取り外し前の原状がどうなっていたのかというと、この通りです。分解しながら写真を撮ってあったので、確認することができました。

分解中、クラッチセンターだけを取り外した時の写真
どうでしょう?全部向きが揃っていませんか?カドの取れている方が、外側を向いているようです。
一方のクラッチディスクにはいっさい裏表は無いようなので、特に考えずに組み付けました。
ここまで、かなり分かりにくかったと思うので、図解します。載せる向きに注意してみてください。

1.クラッチセンター

2.スプリングシートを載せる
(マニュアルにウラオモテの記載なし。カドが丸いほうが上に)

3.ジャダースプリングを載せる
(向きはマニュアル通り)

4.ディスク(内径大)を載せる

5.プレートを載せる
(マニュアルにウラオモテの記載なし)

6.残りのディスクとプレートを交互に載せる
(プレートは全部同じ向き)
この通り、組まれていた通りに組み上げました。何度も言いますが、マニュアルで指示の無い部分は、実はどうでも良いことなのかも分かりません。自分には判断が付きかねます。
(つづく)

















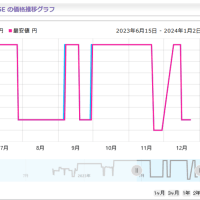







こちらの記事大変参考になりました。
先日からアウターハウジング、インナーハウジングの
段付きを修正しているのですが、ある事に気付きました。
段付きをルーペで(老眼です)確認したら
段付きの端→端の状態が違うようです。
段の片側は滑らかになってるのに対し反対の端は鋭角に。
クラッチプレートってステンレス板の打ち抜きだそうで
そうなれば当然裏面はバリ??と云うか、
角が立った状態になります。
つまりは、この角が立った部位でインナーハウジングを
削って行ったのでは???
と思いました。
今回のOHでは段付きの修正をメインに
フリクションディスク、クラッチプレート、
スプリングの交換のみの予定でしたが
急遽ディスク、プレートのバリ??
いや、面取り作業も組み入れました。
貴重な記事のUPありがとうございます。
また、この記事に出会えたことに感謝いたします^^
35年ぶりのリターンライダーより。
分解清掃。
貴殿のブログ、大変参考になりました。
ありがとうございます😊