 戒名・位牌・仏壇道散策
戒名・位牌・仏壇道散策昨日、父親の墓参りに行きました
父親のお陰で、今の自分の生が有るのかと考えると、感謝した一日でした
近くのお墓で、一人でお参りに来ていた80歳位の女性がお経をあげて
お参りしているのを見ると、お経の力の凄さも感じました

源頼朝の墓石
 墓石
墓石 仏教では、墓石は供養等です
仏教では、墓石は供養等です 平安時代には、供養塔として、支配階級では、五輪塔、宝塔、多宝塔等を建立しました
平安時代には、供養塔として、支配階級では、五輪塔、宝塔、多宝塔等を建立しました 鎌倉~室町時代に、位牌型の板碑として、墓石がつくられるようになりました
鎌倉~室町時代に、位牌型の板碑として、墓石がつくられるようになりました 江戸時代になると、檀家制度が確立し、庶民が墓石を建立しました
江戸時代になると、檀家制度が確立し、庶民が墓石を建立しました 明治時代に、家制度の確立で、墓は家単位で建立され「○○家先祖代々之墓」の形になりました
明治時代に、家制度の確立で、墓は家単位で建立され「○○家先祖代々之墓」の形になりました以前は、墓石に、個人名前を刻んでいました、その為各家庭には数箇所のお墓がありました
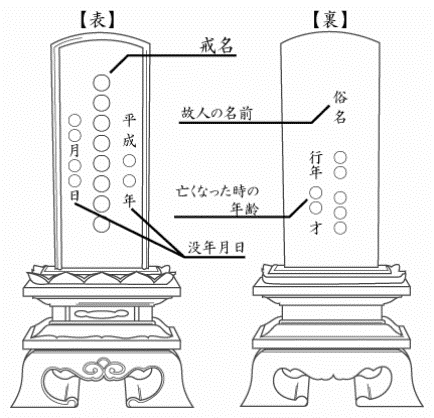
戒名の記載方法(引用)
 戒名
戒名 仏教では、受戒した者に与える名前で、仏門に入った証で、戒律を守るしるしとして与えられます
仏教では、受戒した者に与える名前で、仏門に入った証で、戒律を守るしるしとして与えられます 日本では、死後は成仏するという思想のもと、故人に戒名を授けました
日本では、死後は成仏するという思想のもと、故人に戒名を授けました 戒名と名字
戒名と名字  僧は俗姓を棄てて出家していますので、俗名の名字は使わないのが普通です
僧は俗姓を棄てて出家していますので、俗名の名字は使わないのが普通です 名字+戒名の呼び方が一般的に成ったのは、戦国時代に入ってからです
名字+戒名の呼び方が一般的に成ったのは、戦国時代に入ってからです 武田信玄・上杉謙信・大友宗麟など、名字+戒名の呼び方で名乗ったいました
武田信玄・上杉謙信・大友宗麟など、名字+戒名の呼び方で名乗ったいました 明治維新以降、名字の使用が義務付けられる、僧は名字+戒名で戸籍登録を行いました
明治維新以降、名字の使用が義務付けられる、僧は名字+戒名で戸籍登録を行いました
位牌
 位牌
位牌 内位牌は、臨終後すぐに製作され、葬儀の際に用いる白木の簡素な位牌です
内位牌は、臨終後すぐに製作され、葬儀の際に用いる白木の簡素な位牌です  野位牌は、墓石に文字を刻むまでの間にお墓に置く位牌です
野位牌は、墓石に文字を刻むまでの間にお墓に置く位牌です 本位牌 四十九日の法要までに、内位牌から作り替えられる位牌です
本位牌 四十九日の法要までに、内位牌から作り替えられる位牌です
仏壇
 仏壇
仏壇 インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、神聖な場所として「神」を祀っていました
インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、神聖な場所として「神」を祀っていました風雨をしのぐのに、土壇に屋根が設けました、これが寺院の原型で、それを受けたのが仏壇です
 仏を祀る壇は、仏壇を指し、寺院の仏堂においても、仏像を安置する壇も仏壇です
仏を祀る壇は、仏壇を指し、寺院の仏堂においても、仏像を安置する壇も仏壇です 日本語で「仏壇」と言えば、家庭内に安置するものを示します
日本語で「仏壇」と言えば、家庭内に安置するものを示します 江戸時代、寺院を菩提寺と定めその檀家になることが義務付けられました、
江戸時代、寺院を菩提寺と定めその檀家になることが義務付けられました、その証として、各戸ごとに仏壇を設け、朝・夕礼拝する習慣が確立しました

























