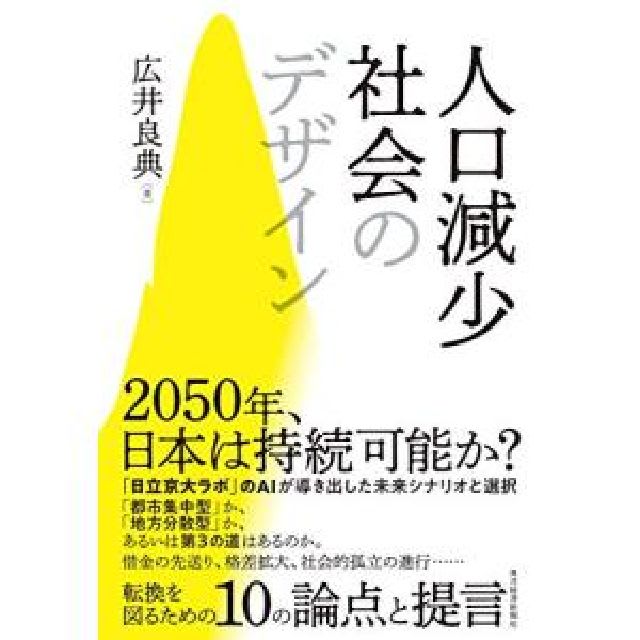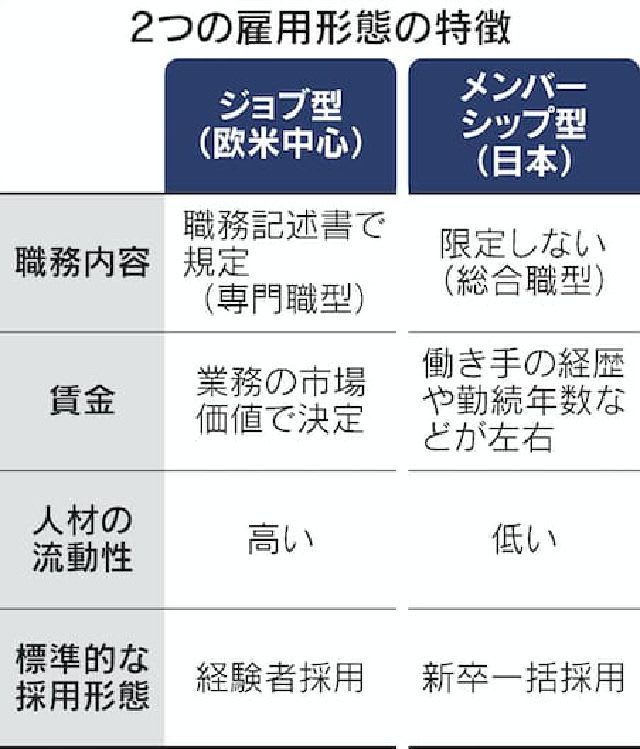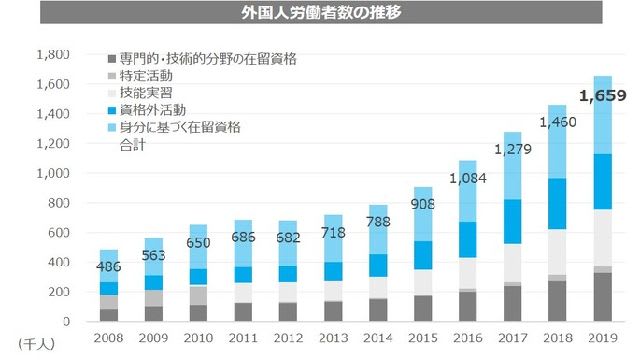🌸日々のリセット術2
⛳3つのポイントで体の調子をチェックする
☆多くの人は「悪い流れ」を意識しないまま過ごす
*自分の調子をチェックすることが大切
①よく眠れているか
②食欲はあるか
③お腹の調子はどうか
*自分の調子をチェックすることが大切
①よく眠れているか
②食欲はあるか
③お腹の調子はどうか
☆毎朝この3点を意識的にチェックするだけで
*自分の「悪い流れ」に気づくことができる
*「リセットのきっかけ」をつくることができる
⛳朝は「リズム感のある曲」を聴く
☆音楽は、自律神経を整えるのに効果的
☆音楽は、自律神経を整えるのに効果的
*コンデイショニングに役立つことは多くの研究で立証されている
☆朝、交感神経を高めて「活動モード」に入るとき
☆朝、交感神経を高めて「活動モード」に入るとき
*「リズム感のある曲」がおすすめです
☆夜寝るとき「歌が入つていないゆつくりした曲」を聴く
*自然に副交感神経が高まつてきて「休息モード」に入る
⛳意識的に「ウキウキする予定」を入れる
☆介護の問題は日本社会全体が抱える大きな課題のひとつ
*「介護疲れ」を訴える人も増えている
☆介護の問題は日本社会全体が抱える大きな課題のひとつ
*「介護疲れ」を訴える人も増えている
☆気分と自律神経は密接に関係している
*「ウキウキする予定」が入っていると
*当日、そこへ向かう日々の生活での気分も変わってくる
*当日、そこへ向かう日々の生活での気分も変わってくる
*意識的に「ウキウキする予定を入れる」習慣も必要
(「ショツピングヘ行く」等何でもOKです)
*そうした予定を意識的に、定期的に入れていくことです
(「ショツピングヘ行く」等何でもOKです)
*そうした予定を意識的に、定期的に入れていくことです
☆漫然と日々を過ごしていると
*心身ともに「悪い流れ」から抜け出せなくなってしまう
☆「ウキウキする予定」があればリセットできる
*「未来を楽しみにすること」
*「未来を楽しみにすること」
*心身のコンデイショニングで大事な要素です
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『リセットの習慣』
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『リセットの習慣』