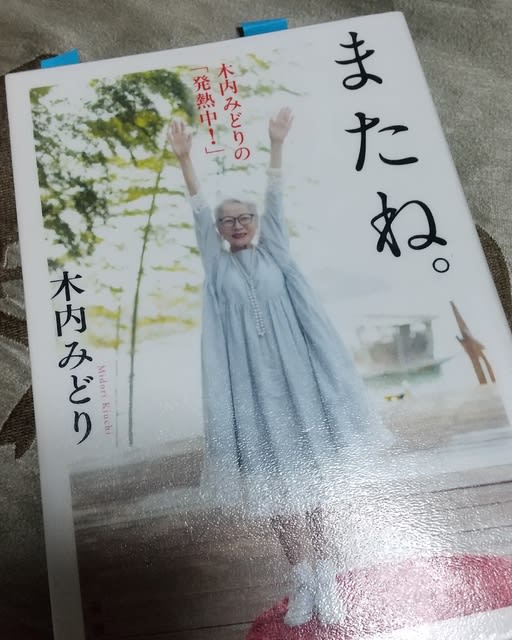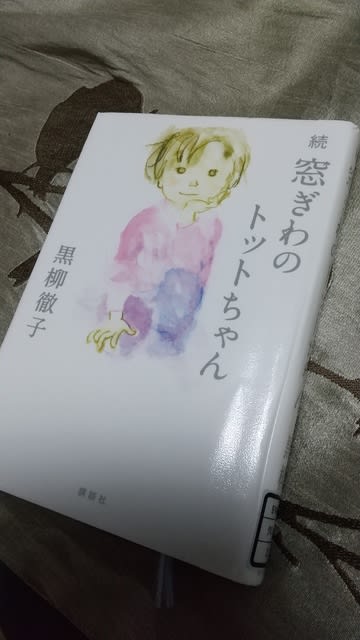いくつか仕事抱えていますが、
昨日は小学校の一学期の終業式が行われ、
今日から夏休み!さっそく昨日の帰り道に
県立図書館に寄って本を借りて来ました。
それがこの5冊。本を選ぶのにも結構時間がかかりますが、
その時間もまた楽し。猛暑の中の涼しい図書館は天国かも。
夏休みの夜は、時間に追われることも少なくなるので
いつもより読書が楽しみです。

夏休みにしたいことのもう一つはガーデニング。
荒れ放題になっているお花たちを少しでも整理していきたい。
こちらはペチュニア。春に苗を買って育てていましたが、
どんどん痩せて枯れかかって来たので、
思い切って短く茎を剪定して肥料を与え、
置き場所も玄関先からベランダへ移動させました。
すると、どうでしょう!
どんどん葉と花芽が出て来て、見事な株となりました。
これほど見事に生き返った鉢は珍しいので
とてもうれしいペチュニアの花です。