
2018年を迎えました。
新しい一日を、いかがお過ごしでしたか?
元旦のご挨拶は普通太陽ですが、遅くなってしまい月になりました。
そして、今夜の月は2018年のスーパームーンです♪
大きなお月様に見守られて昨年を振りかえると、2017年は私的分野において特に大きな変動がありました。
3月に、母が我が家に来ることを決意し、実家を手放す覚悟を決めました。
5月には、次男に女の子が生まれ、私は2男2女のおばあちゃんになりました。
6月に母は我が家に居を移し、同居生活が始まりました。
8月に実家売却の契約が成立し、下旬には子どもたち家族が集まってわが母の歓迎会をしたものの、母は疲れが出て寝込み、高齢者の体調管理に関する認識が甘かったことを反省しました。
12月には舅の七回忌。まだ1軒残っている空き家と向き合っています。
後半の私生活は、ひたすら母の体調の変化と向き合い、施設にいる義母の「ここを出たい帰りたい」コールに付き合いながら、高齢者と幼子とに向き合うスリルと楽しさを味わってきました。
一方で、母が家を手放したということは私にとっても故郷が無くなったということで、その喪失感との闘いでもありました。
そんな私生活に翻弄されながら、仕事やボランティアでは
「活動を一つ一つ吟味して、自分自身でしっかり取り組んでいくこと、サポートをすること、他の人を信じて委ねることを整理する」
ことを試みました。
その結果、
・みんなの広場の仕組みや運営形態について具体化し、
・社会福祉法人の公益活動も具体的にモデル取り組みが始まり、
・子どもたちの居場所は具現化し、困り感の実態把握もいくらかできたように思います。
サポートする活動もそれなりに頑張りました。
あと一歩も二歩も不足しているのは、「他の人を信じて委ねる」ということです。
それは押しつけるのではなく、私がやるよりも他の人がやったほうが上手くいくことから自ら手をひく、ということです。
なぜそれがうまくできなかったのだろう?
思うに、昨年は私生活では喪失と向き合う年でしたから、「これ以上の喪失感からの逃避」だったのかもしれません。
手放したくないという・・・。
周囲にとっては、迷惑なことだったのではないでしょうか。
2018年は、踏まれ利用されてもびくともしない橋になろうと、昨日(2017年の大晦日に)決めました。
昨年は試練の年ならば、今年は清算の年にしたいと思います。
質量ともに、身軽になることを目指します。
さて、できるかな(^^)
今年もどうぞよろしく願い申し上げます。



















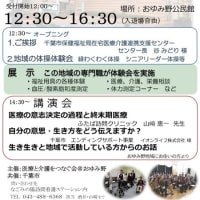

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます