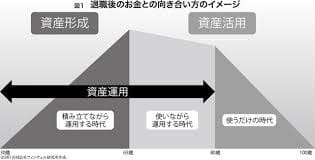日本経済新聞の書籍紹介の欄で書評家の東えりかさんが取り上げていました。
前野ウルド浩太郎さんの著作は初めてです。本書は、7年前に出版し新書大賞を受賞した「バッタを倒しにアフリカへ」の続編とのこと、エネルギッシュなタイトルも刺激的です。
期待どおりインパクトのあるエピソードが数多く紹介されていましたが、その中でも特に印象に残ったところをいくつか書き留めておきます。
まずは、「論文作成の現実」についてです。
学術論文では当然なのでしょうが、記述内容はどんなに些細なことであってもすべて実際に確認されていなくてはならないという “探求への真摯さの程度” には改めて驚かされました。「卵母細胞は毎日、徐々に大きくなる」「メスは自力でオスを蹴っ飛ばすのに苦労する」といった一行にも満たない記述の裏には、解剖や実験にもとづく測定数値があり、それを得るために多大な時間と労力を費やしているのです。
このあたり前野さんはユーモアたっぷりに紹介していますが、現実の作業は、相手が「生き物」だけに想像以上に厳しいものだったでしょう。
こういった前野さんの研究に向かう真摯な姿勢は、念願の論文掲載後、研究者たちからの反応を期待する姿にも表れていました。
(p537より引用) また、学会やセミナーなどで研究を紹介すると、色んな質問を頂戴できるようになった。論文を発表するだけではいけないのだ。もっと自分から話しかけていかなければ孤独感は拭い去れない。自分が行動しなければ、自分を満足させることはできない。私は甘えていただけだった。
自分の研究を多くの人たちからの声を受けて磨き上げ、さらに高みにある次なる未知を解明していこうという前向きな情熱は素晴らしいものです。
しかし、本書を読んで最も感じ入ったところですが、前野さんの読者を楽しませるテクニックはかなりのものですね。
話のテンポの絶妙さやユーモアの挟みどころも見事ですし、さらには、特定年齢層のマニア(オタク?)向けに「特級呪物」「ガンダムRX78-2」といったアニメやコミックの小ネタをあちこちに埋め込む遊び心もなんとも心憎い演出だと思います。
まったく研究者にしておくには何とも惜しい逸材ですね。