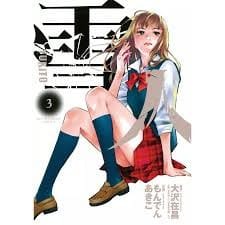いつも利用している図書館の新着本リストを見ていて、何の工夫もないベタなタイトルですが、ちょっと気になって手に取った本です。
歳をとるにつれて、自分の好みの音楽の原点は “歌謡曲” なんだと感じることが増えましたね。もちろん、昭和歌謡が生まれた当時は私の祖父母の時代ですが、私が幼いころは昭和真っただ中、テレビの “歌番組” の最盛期でしたから、本書で語られている時代感はよくわかります。
その中から、特に印象に残ったところをいくつか覚えとして書き留めておきます。
まずは、「第一章 昭和歌謡の夜明け―昭和三年~一三年(一九二八~三八)」、歌謡曲黎明期の代表的作詞家西條八十の気概を紹介したくだりです。
芸術性を追及する詩を書いていた西條は関東大震災時の避難所で大衆に支持された歌の力に感じ入ります。
芸術路線から大衆路線に舵を切った西條の代表曲のひとつが「東京行進曲」ですが、当時この曲が流行るにつれ非難の声が上がりました。
(p25より引用) それは昭和四年八月にJOAK(東京放送局)で伊庭孝が「民衆の趣味の堕落」だと痛罵したことにはじまる。詩人の室生犀星は「こうも詩を弄んでいるものもあるかと軽蔑した」と書き、白鳥省吾は「時代相の俗悪に帰した西條八十の押しの強さに呆れざるを得ない」という。
しかし、西條の心は揺らがなかった。彼らと西條には、大衆から支持される作品を作るか、有識者から高評価される芸術作品を作るか、という意識の差があらわれていた。
そして、戦時下、日本の流行歌も戦意高揚という国策に沿った泥流に文字通り流されていきます。
「第三章 暗い戦争と明るい歌謡曲――昭和一六年~二〇年(一九四一~四五)」で紹介された、「露営の歌」「若鷲の歌」等で有名な当時の代表的作曲家古関裕而にまつわるエピソードです。
(p156より引用) しかし、内務省の検閲や軍部の意向があるため、古関も作曲をする上で工夫していた。古関は「あの時代はですね…大変でした。自分達の意志ではね、どうにもならない時代でした。検閲とか軍の掟が厳しかったですからね。歌手の方達もそうだったと思いますけれど。軍の命令は絶対でした」「自分の意志は捨てて、作曲していましたよ。僕も考えましてね、依頼されたものは勇ましい本筋である行進曲風と哀調を帯びた短音階物と、二種類作って出していましたけど」と語っている。
こういった昭和初期の歌謡史の概観に続いて、私も同時代を経験した昭和中期以降の考察に刑部さんの論は進みます。
その中で私が最も納得感を得たのが、「第七章 歌謡曲の栄光から斜陽―昭和五〇年~六三年(一九七五~八八)」において “昭和歌謡における編曲家の役割” に言及しているところでした。
(p316より引用) 昭和歌謡史を振り返ると、ともすれば忘れられてしまうのが編曲家の存在である。編曲家の大きな仕事は前奏、間奏、後奏など、歌唱メロディーではない部分を作曲することと、全体の楽曲に使う楽器編成のアレンジである。つまり、作曲された同じ曲であっても、編曲家の匙加減で、「演歌」、歌謡曲、フォークへと変幻自在にすることができる。
“編曲” の二大巨頭として紹介されている萩田光雄さん、船山基紀さんが手がけた渡辺真知子さんの「迷い道」、久保田早紀さんの「異邦人」、あみんの「待つわ」とかの楽曲を思うに、編曲の影響の絶大さは、まさに得心がいきますね。
あと、コラムで紹介された面白いエピソードの中で大いにウケたのが “国家的イベントにまつわる音頭の悲劇” です。
昭和39年(1964年)の東京オリンピックに向けて作られ、三波春夫さんが歌って大ヒットした「東京五輪音頭」、その二匹目のドジョウを狙った “音頭モノ” が次々に登場しました。橋幸夫さん、三沢あけみさんによる「宇宙博音頭」(昭和53年(1978年))、川崎英世さん、小川真由美さんの「名古屋オリンピック音頭」(昭和56年(1981年))、五木ひろしさんの「科学万博音頭」(昭和59年(1984年))、さらには原田直之さん、菊池恵子さんの「ソウルオリンピック音頭」(昭和63年(1988年))???、すべて大失敗。
真剣に企画した関係者の方々には失礼ではありますが、あまりにも安直!、この桁外れにズレまくったセンスは超絶でしたね。
さて本書を読んでの感想です。
刑部さんが「はじめに」で「本書は日本史の歴史研究者が書く初の昭和歌謡史本である」と宣言しているとおり、想像していたよりもずっと密度の濃い内容でした。まあ、正直なところ “歴史研究者ならでは” という驚きまでには至らないまでも、それぞれの歌とその当時の世相との連関といった歴史的意味づけの解説は、少々我田引水的なところも含めとても興味深いものがありました。
ちょうどNHKで「第22回紅白歌合戦(1971年)」のデジタルリマスター版を録画していたので、今度ゆっくりと観直してみましょう。
総合指揮は藤山一郎さん、トップバッターは、白組 “また逢う日まで” 尾崎紀世彦さん、紅組 “17才” 南沙織さん、お二人とも「初出場」です。