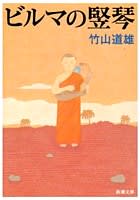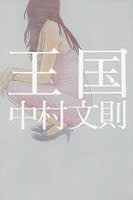ダム建設現場で働く男がセメント樽の中から見つけたのは、セメント会社で働いているという女工からの手紙だった。そこに書かれていた悲痛な叫びとは…。かつて教科書にも登場した伝説的な衝撃の表題作「セメント樽の中の手紙」をはじめ、『蟹工船』の小林多喜二を驚嘆させ大きな影響を与えた「淫売婦」など、昭和初期、多喜二と共にプロレタリア文学を主導した葉山嘉樹の作品計8編を収録。ワーキングプア文学の原点がここにある。
出版社:角川書店(角川文庫)
葉山嘉樹の小説を読んで感じるのは、社会の理不尽に対する怒りだ。
彼自身、労働者として苛酷な作業現場にいただけに、そこにある悲惨な光景をいくつも目にしたのだろう。
それぞれの現場で見てきた、世の不公正を訴えていきたい。そんな強い気持ちがうかがえるようで、目を引いた。
たとえば『セメント樽の中の手紙』。
この小説の中で、一人の男は、セメントのクラッシャーにはまって死んでしまう。
言うまでもなく、惨い死に方だ。
当時は安全対策も取られていなかったろうし、実際こういう事故もあったのだろう。その時代の労働者の一現実を見るようだ。
恋人はその悲しみを手紙に託したが、そこには悲しみと同時に、抑制された怒りも見えるよう。
その手紙を受け取った松戸としても、やりきれない気分になるほかないだろう。だがだからと言って、そこから何かが変わるわけでもない。
ただ残るのは理不尽な現実のみだ。その抑えられたタッチが心に残る。
そのほかにも労働者の現実が、物語に仮託されて描かれている。
『淫売婦』
病気になったためにまるで死体のようになりながらも、劣悪な環境で体を売らねばならない女の姿が惨い。
ある意味生き地獄だが、そんな中でも何かに対して夢見る思いも捨てきれない。
そんな彼らの状況がどこかせつなかった。
『労働者の居ない船』
コレラにかかり看病もされないまま「生きながら腐って」いくことのむごさ、そしてコレラにかかった者は捨てられるように倉庫に落とされることの暴力。
それはさながらホラーのようだが、そのように捨てられた人々のいたのかもしれない。
そんなことを思い、考えさせられた。
『牢獄の半日』
囚人も人としての権利があるというのに、捨て置かれて省みられない。
その事実の重みが忘れがたい作品だった。
『浚渫船』
弱い立場の憤りを描きながらも、権力の前では何もできないのが現実だ。
その真実を見据えながらも、それでも怒らざるをえない思いに満ち満ちていて、心に響いた。
評価:★★★(満点は★★★★★)