毎度の事ながら、他ごとに手を取られて、自分の事をする暇がなくなっていましたが、
すこし時間が出来たので、無理やり工作をする事にしました。
ペルケ式ヘッドホンアンプ、しかしながら、虫シリーズ?という
わけの分からない物の2個目として「タイコウチ」が派生しましたが、我が家の「タガメモドキ」に比べて
何か滑らかさが足りない感じが益々するようになりましたので、違う方向からの
アプローチをしてみることにしました。
題して。。。実はいまだに良い名前を思いつきません。
「トランジスタ貼りあわせ」でもないし「組み合わせ」でもないし。さてどうしたものか。
まぁ、動けばよしなのと、「批判するのは簡単ですが試しもしないのでは話にもならない」
ので、まずは聞いてみてから、ということにしました。

そろそろ、2SC3421と2SA1358の在庫が尽きてきまして、これが最後のトランジスタと
なってしまいました。
2セット分を組みました。
そして、先に2SC1815と2SA1015に組みこんでいた「タイコウチ」の終段を上の物と
交換してみました。
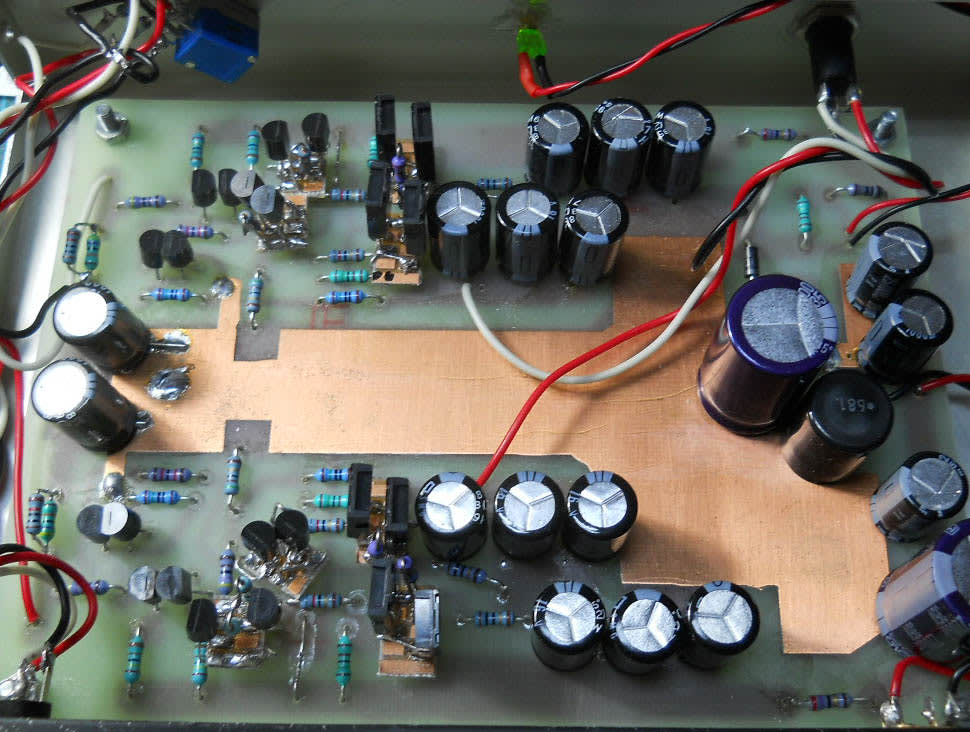
回路的には、前段の2SC1815と2SA1015と同じですが、抵抗が若干違いました。
予想では数十KΩ以下と思っていましたが、さにあらず、270KΩでhFE=90前後となりました。
同じ抵抗値で、2SC3421は若干低めとなり、2SA1358は若干高めとなりますが、
テスターでの測定ではおおむね3以内となっているので、30以上違っていたことを考えますと
僅かな差ではないでしょうか。
さて電源をいれて、定点の出圧測定をしますと、中段、終段のhFEがほぼそろっているせいか、
初段にまで高影響が現れているようでして、左右のそれぞれの箇所の電圧が0.1V以下となり
ました。今までは0.5Vなど平気でずれていたのに、これは愕きです。
「部品の選別の重要性が改めて分かりましたが、終段のNPNとPNPのhFEを合わせる事さえ
難しい状況では考えものです」
音を出してみました。
電解コンデンサを増やした効果もあって、かなり以前より改善されていたのですが、
それを上回る状態となりました。
初段が2SK170なのに、この低音の出方に驚きですし、高域も非常に綺麗に伸びるといった
感じですし、バランスが悪いと「サ行」が走る傾向が出るのですが、それが全く無くなり
無駄ではなかったという印象を受けました。
ただ、つぎはぎ基板の影響も若干出そうなので、これを1枚の基板にする必要を
感じまして、アートワークの修正をする必要が出てきましたが、よりよい結果が見えそうですので
非常に楽しみとなりました。




















