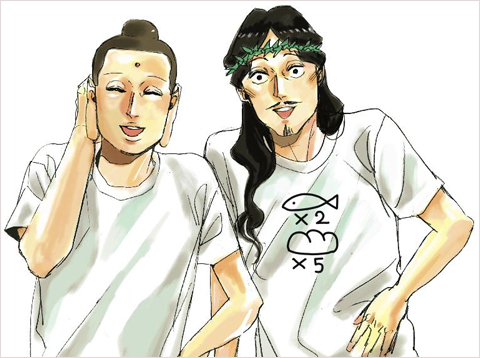日本 この国では
年寄りは 敬うのが 当たり前
子どもは 可愛がるのが 当たり前
女性は 食べさせるのが 当たり前
弱者は 労わるのが 当たり前
人を見下す者は 軽蔑され 支配者権力者は 徳が求められる
多くの人にとっては 我慢は美徳であり 無駄遣いは悪であり 働くことを厭わない
このような国民が 数多く生きる国は 世界でもあまりないものだ
私は この国が 大好きだ
困っている人がいれば 援(たす)けたくなる
援けを求められれば 過去の遺恨は 水に流してしまう
そんな 優しい国民なのに
今の日本は 国として 自信を失っているように思える
今の日本国民は 世界の中をうつろい 漂っているようにも見える
誠に 残念だ
ただ私は この美しき国が 大好きだ
歴史の波間に 消されてしまうには 惜しすぎる美しさだ
もう一肌 二肌 脱ぎ甲斐のある国 それが日本だ