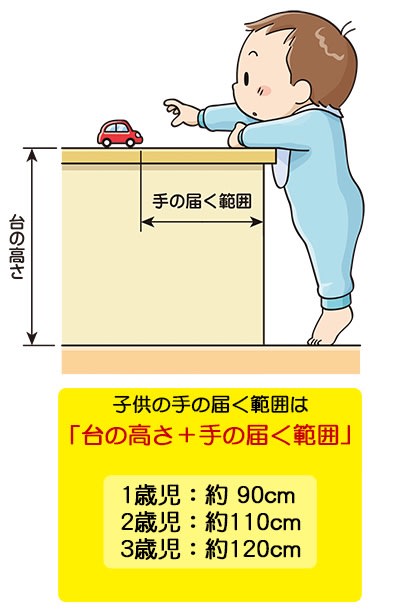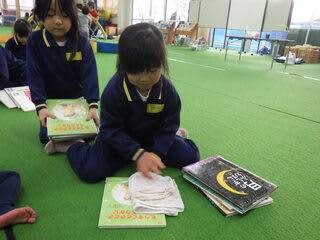元気に登園しましょう
新年度が始まってから1か月近く経ち、こどもたちは新しい環境にも慣れ、友達と元気に遊ぶ姿が見られるようになってきました。
この時期は1日の気温差が大きく、心や体に疲れが出たり、体調を崩しやすい時期でもあります。積極的に外で遊び、規則正しい生活して健康な体づくりを行いましょう。
朝ご飯をしっかり食べて登園しましょう!
朝ご飯を食べると、
①体にエネルギーと栄養が行き渡る ②脳を活発にする
③体温を上げて、体を目覚めさせる ④生活のリズムを作る
などの役割があります。
朝はしっかり朝ご飯を食べてその日1日を元気に過ごしましょう。
ご飯の良い所
①腹持ちがいい ②顎を強くする ③塩分が少ない
パンの良い所
①買ってすぐ食べられる ②カルシウムが取れる ③種類がたくさんある
生活リズムを整えるためにできること
①まずは早起きから
遅く寝てしまっても、翌日は早く起こしましょう。夜も早く眠くなるので、布団に入りやすくなります。
②朝の光でスタート!
カーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。目覚めが促されて、脳も体も活動を始めます。
③日中にしっかり遊ぶ
体を動かしてたくさん遊びましょう。心地よい疲れが夜の眠りを誘います。
④午睡は15時半までに
家で午睡する時も、遅くても15時半までに終わらせましょう。夜の睡眠に影響します。
⑤お風呂はぬるめに
熱いお風呂は、急激に体温が上がって目が冴えてしまいます。お湯はぬるめにするのがポイントです。
⑥入眠前の習慣づけを
毎晩、眠る前に「おやすみの習慣」をつけましょう。絵本を読む、布団に入ってぎゅっと抱きしめるなどをすると、眠りやすくなります。
毎朝の元気チェックを!
こどもたちは、身体の異常を自分で伝えることができません。朝、こどもたちが起きたら抱っこをしたり、着替えをしたりしながら、体調や機嫌のチェックをしましょう。
こどもの健康管理の基本は、「いつもと違う状態」に気付くことです。そのためには、「いつもの状態」を把握しておくことが、大切です。常にこどもの様子に気を配り、何か変化や異常が見られたときは、適切な対応ができるようにしていきましょう。
熱や嘔吐・下痢、湿疹・発疹はないですか?鼻水や咳は出ていませんか?顔色・機嫌はどうですか?食欲はありますか?
乳幼児は症状が悪化しやすいものです。毎朝触れ合いながら「見て」「触って」の確認をお願いします。
休むほどではないけれど、どこか調子が悪いときは必ずお知らせください。園でも丁寧に様子を見ていきます。
以下の症状がある場合は、症状が改善するまでご家庭で様子を!
発熱、咳、嘔吐、下痢、蕁麻疹、全身に発疹がある等の症状がある場合は、ご家庭でゆっくりと過ごして、元気になったら登園しましょう。
今週末からゴールデンウィークも始まります。外出の予定を考えられているご家庭も多いのではないのかと思います。
計画には、こどもたちの体力に合わせて無理のないように休息を入れながら、生活リズムを崩さないようにお過ごしください。