

今日の午前に、様子を見にご足労頂きました。

↑いちおう蓮如上人のほうも採寸して頂きました。






住職の娘です。








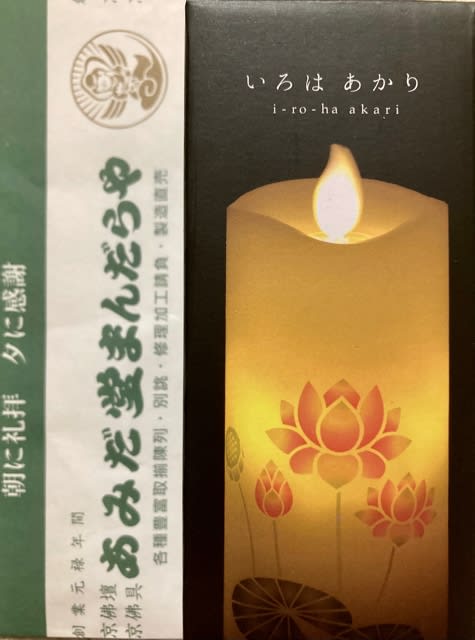
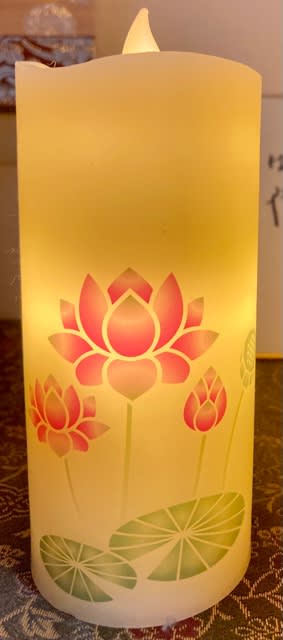
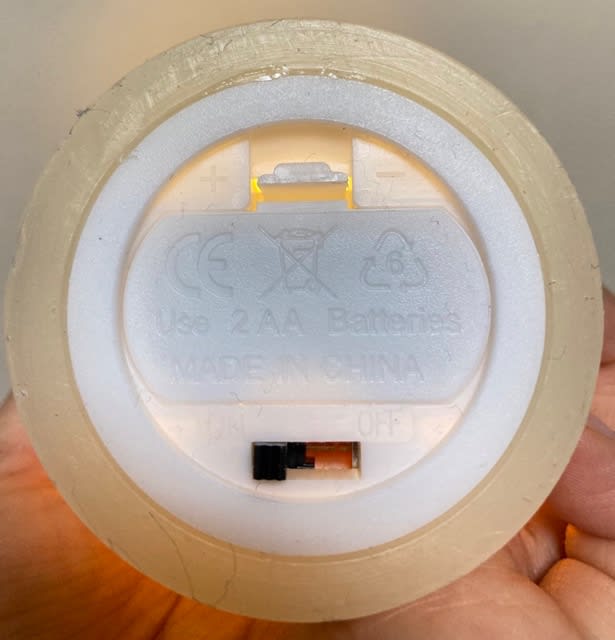
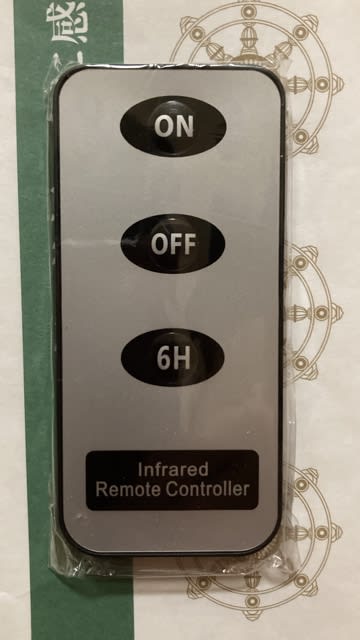
住職の娘です。
この新型コロナの中でも、気をつけるべきことには気をつけて、しかし、お経はいつも通り仏説阿弥陀経(時々、正信偈)をお勤しています。
仏説阿弥陀経は、俗に「小経」とよばれるくらい浄土三部経のなかでは短めのお経です。ちなみに浄土三部経(じょうどさんぶきょう)とは、以下の三種です。
・仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう):大経
・仏説観無量寿経(ぶっせつかんむりょうじゅきょう):観経
・仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう):小経
「無量寿(仏・如来)」とは阿弥陀仏(如来)の別称でもあるので、三部すべて阿弥陀仏に関して書かれたお経であります。
まぁ、短めのお経といっても読経時間10分!とは参りません。
早口言葉のような高速で読経してもよいなら、いい線いくかも?程度です。
ただ、そんな「はやく終わらせたい」気持ち満々のお経は、み仏の心にも、人の心にも沿っているとは思えません…娑婆のワタクシの都合で必要なときはあるかもしれませんが。汗
率直に申し上げれば、お経が長すぎて嫌いになるくらいなら、長くて続けられないなら、意図して「時短」にするのも自然なことで、そんなお経も悪くはないものだと考えています。実際のところ、浄土真宗は天台宗をもととして、仏具などは簡便簡略化し、お経の節なども一般に真似しやすい在家用に変更されてきたものであります。そして、「いつも、みんなで」唱和できることを徹底し実行されたのが、「浄土真宗中興の祖」である蓮如上人です。その根底には、読経を修行としない浄土真宗ならではの考え方。また、お経にかける労力の軽重、回数、時間の長短によって、仏様が人間を区別なさらない、善し悪しをいわれないことが理由になります。毎日、ご仏前に座して心をかけておられるのが、なにより大切で尊いことだと思われます。
時々、「短めのお経はありませんか?」とか「ええとこだけ、お願いしますわ」と言われることがあります。私自身、そうおっしゃるお気持ちはよくわかります!しかしその際に、私がお返しできるのは「浄土真宗で、文言の数が少ないのは『重誓偈(じゅうぜいげ)』というお経です」と申し上げるくらいです。まずもって、「お経」に善し悪し、上下は言えません。お経は、少なくとも日本という国に限定しても、1000年以上の時を超えて、今、私たちのもとへ届いた「み仏の願い」のエッセンスです。このエッセンスをわからないなりに自らがよんで耳にして、繰り返すことで、そのみ仏の願いを自身の心を少しずついただいてゆく。ついでに、読経する私の声が、誰か近くで耳にする方へ、み仏の願いを間接的にお伝えするという意義ある行為だと考えています。現在制定されている浄土真宗のお経が、既にある程度有意義に凝縮されているのに、浅学な私の都合で「中略」とできるはずもありません。ですから、「ええとこを」とか「有り難い部分だけ」というお経のリクエストはご勘弁ください。
特に、年回忌法要などの仏事の場合はおよそ定石のお経などが、宗派で決められております。いくら施主様にお願いされたとしても、しがない一僧侶としては「えー、ちょっとそれは難しいです~(笑)」といって、読経をスピードアップさせていただくくらいが関の山なのです。
そして、日常的にお勤めする「短めのお経」と申しますと、先にあげた「重誓偈(じゅうぜいげ・じゅうせいげ)」になります。これは、浄土三部経の大経『仏説無量寿経(上巻)』から五言四十四句を抜粋した内容です。節もなく、所謂「棒読み」で最初から最後までお唱えします。浄土真宗において、この大経は最も重要なお経と位置づけられており、この抜粋部分自体が非常に意義深い場面であり文言でありますので、短めのお経(笑)では、こちらをオススメしたいと思います。
南無阿弥陀仏
