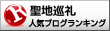ウナギの完全養殖が成功したというニュースは、この春、報じられたものだが、今日は土用の丑の日。朝のニュースで再び取り上げられていたのを、二回も聞いた。
養殖といえば、和井内貞行。明治時代、生き物が棲まない清流であった十和田湖で、たいへんな艱難辛苦の末、ヒメマスの養殖を成功させた。団塊の世代の道徳の教科書には、必ず載っていたらしい。
とはいえ、私が和井内貞行を知ったのは、今から十数年前、京橋のフィルムセンターで伊藤大輔監督の『われ幻の魚を見たり』を観て以来である。
道徳の教科書が採り上げる偉人伝は、各時代の治世者の思惑を映して、いろいろ変わる。日頃何かとお世話になっている団塊の世代である恩人夫妻に、お茶を飲みながらその映画鑑賞模様をレポートしたら、あら懐かしい!ということになり、その面子での飲み会を以後「和井内会」と命名するに至った。
昭和40年代の小学校の道徳の教科書には、和井内貞行はもう載っておらず、タイタニック号から救出された一人の日本人に関する逸話が載っていたように記憶している。
今や、学校では、道徳の授業自体が無くなってしまったそうだけれど。いくら自由とはいえ、無垢なるものに道を示さなくちゃ、無軌道になる一方でしょうにねぇ…。
和井内貞行を大河内傳次郎。小夜福子が内助の功を発揮させる奥方役で、いつも夜なべ仕事にお裁縫をしている。
「オドサンは、この針のようなもので、私はその針に通した糸のようなもんだ。オドサンのあとをどこまでもついて行きます」というような意味のことを南部弁で言って、養殖に失敗し八方塞がりになるたびに、大河内和井内を励ますのだった。
しかし、ストーリーがあまりにも辛気臭く進行していくので、途中、私の前に座っていた妙齢のお嬢さんが席を立って出て行ってしまったほどだ。
戦前から子役でおなじみの片山明彦が、日露戦争に出征する長男の役をやっていた。
いつものように、放流したヒメマスが戻ってこないか湖を見張っていた大河内和井内のもとに、長男の戦死公報が届く。湖のほとりの見張り台で失意のどん底にいる和井内の眼に、きらめいて増幅していく湖のさざ波が映る…長男の英霊が導くかのようにヒメマスもまた、十和田湖に戻ってきたのだった。
生き物が棲まないと言われた十和田湖で、初めて養殖が成功した瞬間である。
もはや、観客は、ここに至るまでの地味なエピソードの長回し、辛抱を要する延々たる鑑賞時間をすっかり忘れて、滂沱の涙。伊藤大輔監督はやっぱり偉大だ、と思い直すのだった。
大河内傳次郎は、私が生まれた年に亡くなったので、当然、リアルタイムでは観ていない。しかし、映画というのはそういうところが実に有難くどえらいもんで、同時代に生きた者にしか分からない舞台での芝居と違って、フィルムのなかに閉じ込められた時代の空気を、銀幕が再現してくれる。
映画をライヴとして観ていたい私は、よっぽどのことがない限り、一作品を一回しか観ない。
そんなわけで、昭和後期から平成ひとケタ時代、十代後半から三十代前半にかけて、昭和時代の映画黄金期の、いわゆる古い日本映画を浴びるように、際限なく観ていた。
大河内傳次郎は、昭和の多くの家庭で愛されていた俳優で、彼の死後生まれ育った子供世代にも、彼に対するシンパシィがいつの間にか醸成されていた。
日本テレビの「笑点」で、林家木久扇が持ちネタにしている物まね。
「ホノホノ方…」は忠臣蔵の長谷川一夫・大石内蔵助。「ごぉくろうさぁまぁ…」は木久蔵の師匠・彦六の正蔵師匠。そして「シェイは丹下、名はシャジェン」が、われらが大河内の丹下左膳である。
私の大河内びいきが形となったのは、切れ切れのフィルムでしか残っていなかった『大菩薩峠』の御簾斬りシーン。大河内机龍之介の着物の裾が映っただけで、ものすごく怖かった。凄み、というのは人の形相を写さなくとも表現し得るのである。着物の裾が、とにかく怖かったのだ。
対極上にあるけれど、清水宏監督の『小原庄助さん』も、大河内が大河内らしくて、大好きな作品だ。
もう二十年以前になるが、嵯峨野の青竹の林を抜けて、初めて大河内山荘を訪れたとき、あまりに懐かしい、記憶のなかの昭和の家がそこにあって、私は思わず泣いてしまった。そしてまた、大河内が心血注いで丹精した屋敷内を手放すことなく、維持し続けている、そのご遺族の心遣りにも。
どんなに栄華を誇った映画スターでも、本人が亡くなるとその資産はちりぢりバラバラになってしまう。グロリア・スワンソンが出ていたあの怖い映画が表徴するように、無残に散逸してしまう。
しかし、大河内山荘は違った。それを、遺族が、故人が愛した庭を守っている、そのこころざしに、どうしても私は、あの懐かしい昭和の面影が残っている山荘を訪れるたび、それを想い起こしては泣いてしまうのだ。
養殖といえば、和井内貞行。明治時代、生き物が棲まない清流であった十和田湖で、たいへんな艱難辛苦の末、ヒメマスの養殖を成功させた。団塊の世代の道徳の教科書には、必ず載っていたらしい。
とはいえ、私が和井内貞行を知ったのは、今から十数年前、京橋のフィルムセンターで伊藤大輔監督の『われ幻の魚を見たり』を観て以来である。
道徳の教科書が採り上げる偉人伝は、各時代の治世者の思惑を映して、いろいろ変わる。日頃何かとお世話になっている団塊の世代である恩人夫妻に、お茶を飲みながらその映画鑑賞模様をレポートしたら、あら懐かしい!ということになり、その面子での飲み会を以後「和井内会」と命名するに至った。
昭和40年代の小学校の道徳の教科書には、和井内貞行はもう載っておらず、タイタニック号から救出された一人の日本人に関する逸話が載っていたように記憶している。
今や、学校では、道徳の授業自体が無くなってしまったそうだけれど。いくら自由とはいえ、無垢なるものに道を示さなくちゃ、無軌道になる一方でしょうにねぇ…。
和井内貞行を大河内傳次郎。小夜福子が内助の功を発揮させる奥方役で、いつも夜なべ仕事にお裁縫をしている。
「オドサンは、この針のようなもので、私はその針に通した糸のようなもんだ。オドサンのあとをどこまでもついて行きます」というような意味のことを南部弁で言って、養殖に失敗し八方塞がりになるたびに、大河内和井内を励ますのだった。
しかし、ストーリーがあまりにも辛気臭く進行していくので、途中、私の前に座っていた妙齢のお嬢さんが席を立って出て行ってしまったほどだ。
戦前から子役でおなじみの片山明彦が、日露戦争に出征する長男の役をやっていた。
いつものように、放流したヒメマスが戻ってこないか湖を見張っていた大河内和井内のもとに、長男の戦死公報が届く。湖のほとりの見張り台で失意のどん底にいる和井内の眼に、きらめいて増幅していく湖のさざ波が映る…長男の英霊が導くかのようにヒメマスもまた、十和田湖に戻ってきたのだった。
生き物が棲まないと言われた十和田湖で、初めて養殖が成功した瞬間である。
もはや、観客は、ここに至るまでの地味なエピソードの長回し、辛抱を要する延々たる鑑賞時間をすっかり忘れて、滂沱の涙。伊藤大輔監督はやっぱり偉大だ、と思い直すのだった。
大河内傳次郎は、私が生まれた年に亡くなったので、当然、リアルタイムでは観ていない。しかし、映画というのはそういうところが実に有難くどえらいもんで、同時代に生きた者にしか分からない舞台での芝居と違って、フィルムのなかに閉じ込められた時代の空気を、銀幕が再現してくれる。
映画をライヴとして観ていたい私は、よっぽどのことがない限り、一作品を一回しか観ない。
そんなわけで、昭和後期から平成ひとケタ時代、十代後半から三十代前半にかけて、昭和時代の映画黄金期の、いわゆる古い日本映画を浴びるように、際限なく観ていた。
大河内傳次郎は、昭和の多くの家庭で愛されていた俳優で、彼の死後生まれ育った子供世代にも、彼に対するシンパシィがいつの間にか醸成されていた。
日本テレビの「笑点」で、林家木久扇が持ちネタにしている物まね。
「ホノホノ方…」は忠臣蔵の長谷川一夫・大石内蔵助。「ごぉくろうさぁまぁ…」は木久蔵の師匠・彦六の正蔵師匠。そして「シェイは丹下、名はシャジェン」が、われらが大河内の丹下左膳である。
私の大河内びいきが形となったのは、切れ切れのフィルムでしか残っていなかった『大菩薩峠』の御簾斬りシーン。大河内机龍之介の着物の裾が映っただけで、ものすごく怖かった。凄み、というのは人の形相を写さなくとも表現し得るのである。着物の裾が、とにかく怖かったのだ。
対極上にあるけれど、清水宏監督の『小原庄助さん』も、大河内が大河内らしくて、大好きな作品だ。
もう二十年以前になるが、嵯峨野の青竹の林を抜けて、初めて大河内山荘を訪れたとき、あまりに懐かしい、記憶のなかの昭和の家がそこにあって、私は思わず泣いてしまった。そしてまた、大河内が心血注いで丹精した屋敷内を手放すことなく、維持し続けている、そのご遺族の心遣りにも。
どんなに栄華を誇った映画スターでも、本人が亡くなるとその資産はちりぢりバラバラになってしまう。グロリア・スワンソンが出ていたあの怖い映画が表徴するように、無残に散逸してしまう。
しかし、大河内山荘は違った。それを、遺族が、故人が愛した庭を守っている、そのこころざしに、どうしても私は、あの懐かしい昭和の面影が残っている山荘を訪れるたび、それを想い起こしては泣いてしまうのだ。