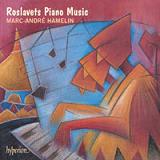 Roslavets Piano Music
Roslavets Piano MusicMarc-Andre Hamelin(P)
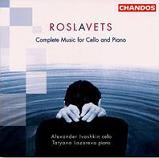 ROSLAVETS
ROSLAVETSComplete Music for Cello and Piano
Alexander Ivashkin(Vc)
Tatyana Lazareva(P)
ニコライ・ロスラヴェッツ(1881-1944)はウクライナに生まれた。1886年からクルスクの音楽学校で音楽の勉強を始め、幼い頃から地元のローカルバンドでヴァイオリンを演奏していた。1902年からモスクワ音楽院でヴァイオリンと作曲を学び、バイロンの詩劇に基くカンタータ「天国と地獄」で銀メダルを獲得した。1912年に音楽院を卒業してからロスラヴェッツはロシアの前衛芸術家たちと交流するようになり、マレーヴィチとも親交を結ぶ。1915年と1916年にはロシア未来派の雑誌に楽曲が掲載され、ロスラヴェッツはモソロフやルリエーとともに、前衛的な音楽家として知られるようになった。1917年のロシア革命後はウクライナの音楽院で指導的な役割を果たし、1924年にモスクワに戻ってからは国立出版局で「音楽文化」という雑誌の編集に携わり、ACM(現代音楽協会)の中心的な存在の一人としても活動した。
1927年の革命10周年を記念するセレモニーではカンタータ「十月」が演奏されるなど、ロシア革命を歓迎し、革命とともに歩んでいたはずのロスラヴェッツであったが、スターリンの台頭以降はRAPM(ロシア・プロレタリア音楽家協会)からブルジョワ的であるとか、反革命的であるとか、あるいは人民の敵であるとして攻撃されるようになった。1930年にそれまでの芸術活動を自己批判するよう強要され、モスクワを追われたロスラヴェッツは、タシケントでウズベク国立劇場の指揮者兼作曲家やウズベク放送局のディレクターを勤めた。1933年にモスクワに戻ってからも放送局のプロデューサーや軍楽隊やジプシー・アンサンブルの指導者といった重要でないポストをあてがわれ、不遇のままその生涯を終えた。
ロスラヴェッツはスクリャービンの後期様式の影響を受けながら独自の音体系を確立するに至った。それは「合成和音」と呼ばれ、十二音技法に類似していることからロスラヴェッツは「ロシアのシェーンベルク」と呼ばれたこともあった。この合成和音について高橋悠治は次のように書く。
「かれの命名した合成和音(Synthetakkord)とは、平均律の十二半音についての二進法的(イエスかノーの)決定である。唯一の十二音和音の部分集合として、八音以上から成る合成和音の表が作成され、選ばれた和音は移置によって変型される。後には移置される音度の集合が、合成和音自体と対応するという方法がとられる」
また、高橋悠治はロスラヴェッツについて、スクリャービンと対比させながら次のように書く。
「作曲家ではなくて音響組織家と自称したロスラヴェッツは、スクリャービンのように神秘主義イデオロギーや、特定の和音への偏愛を持たなかった。一見スクリャービンと区別しにくいピアノ曲でも、音響に対してはより客観的であり、多彩である」
ロスラヴェッツはこの合成和音に作品の全和声構造を決定させた。この新しい音体系は明晰で合理的なものであり、ロスラヴェッツはこの音体系によって音楽の源泉をインスピレーションに求める観念主義をのりこえようとした。ロスラヴェッツは「創造行為とは、何か神秘的な『トランス』でも『神からの』『啓示』でもなく、『無意識のもの』(意識下にあるもの)を意識した形にするために、人間の知性を最大限に集中させた瞬間である」と考えていた。
→F.マース「ロシア音楽史」(春秋社)
→高橋悠治「ことばをもって音をたちきれ」(晶文社)










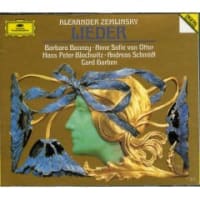
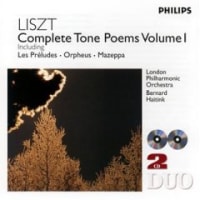
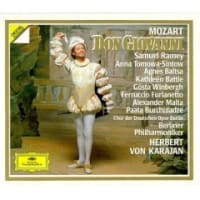
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます