 Ivan WYSCHNEGRADSKY
Ivan WYSCHNEGRADSKY24 PRELUDES Op.22 INTEGRATIONS Op.49
Henriette PUIG-ROGET(P)
藤井一興(P)
20世紀初頭のロシアの前衛的な音楽家たちは調性音楽からの脱却と新たな音素材の確立をめざしてさまざまな実験をおこなった。スクリャービンの音楽を広く知らしめることに功績のあった当時の音楽学者レオニード・サバネーエフも「音楽が独自の音楽素材を刷新して初めて、新しいイデオロギーを表現することができる」と主張していた。騒音の導入や新しい記譜法、合成和音などによるシステマティックな作曲法などとともに、半音のさらに半分の音程である四分音などの微分音を用いることによって和声を拡大する音楽的実験もマチューシンやルリエーなど、当時の前衛的な音楽家たちが深い関心を寄せたものであり、1923年にはゲオルギイ・リムスキー=コルサコフによって「ペトログラード四分音音楽協会」が組織された。
ニコライ・クリビーンは1908年に「生の基盤としての自由芸術―調和と不調和」を書いた。彼は1908年に印象派グループを組織し、翌年解散した後に1910年に発足する「青年同盟」の結成に貢献、以降は「青年同盟」の周辺で活動した。1914年にイタリア未来派のマリネッティをロシアに招いたのはクリビーンであった。
クリビーンは神智学やスクリャービン、あるいはカンディンスキーが主張していた音と色彩の関係論に関心を抱いていた。彼は人間の生は「調和と不調和の相互関係の戯れおよび両者の闘争によって条件づけられている」とし、次のように書いた。
「私は自分の研究にもとづいて、音楽の音階におけるのと全く同様に、スペクトルにおける、色階における協和性と不協和性を決定することが可能だと確信した。
こうしたことを前提として、私はスペクトルにおける隣接色の結合と、音階における隣接音の結合が、生および芸術に対して持つきわめて特殊な意味に注意を促してきた。ちなみに私が階調というのは、間隔のせまい階調のことである……
そこで次のように言えるだろう。つまり、私が「密接な結合」と呼ぶこうした現象、およびそうした密接な結合の操作によって、あらゆる種類の自然像および主観的経験の像を、絵画や音楽や他のあらゆる芸術部門において描き出すことが可能である、と」
またクリビーンは「自由な音楽」と題された論考も書いた(これは1912年に発行された「青騎士」にも掲載された)。そのなかでクリビーンは従来の全音階や半音階よりもさらに感覚の狭い階調である微分音の使用によって、着想に完全な自由が与えられ、音楽の描写力が拡大し、自然の音を真似たり、人間の心の動きを描写することがより完全にできると主張した。
「自然の音楽――光、雷、風のざわめき、水のたてる音、鳥達の歌――は、どんな音を選ぼうと自由だ。ナイチンゲールは、現在の音楽の楽譜どおりに啼くばかりでなく、自分に心地よいあらゆる啼き方をする。
自由な音楽は、自然の音楽や自由の芸術すべてと同じく自然の法則にしたがう。
自由な音楽の芸術家は、ナイチンゲールと同じく、全音と半音に限定されることはない。1/4音や1/8音もつかい、音を自由に選択して音楽にする」
「狭い結びつきの振動、その進行、そのさまざまな演奏によって、光や色や生きとし生けるものの描写が、通常の音楽の場合よりはるかに容易に可能となる。抒情的気分の獲得も、もっと簡単になる。
狭い結びつきによって、さまざまな特別の色彩面から成る音楽的な形象も創造され、これらの色彩面は、新しい絵画に似て、流れゆく和声とひとつに溶け合う」
こうした微分音を用いた音楽を生涯をかけて追求したのがイヴァン・ヴィシネグラツキー(1893-1979)であった。
ヴィシネグラツキーはペテルブルクに生まれた。彼が音楽に関心を抱いたのは17歳の頃で、大学では数学や法学を学びながら、銀行家でアマチュア音楽家でもあった父親から手ほどきを受けた後、1911年にペテルブルク音楽院に入学し、ニコラス・ソコロフの下で、和声学と作曲、管弦楽法を学んだ。ソコロフを通じてスクリャービンの音楽を知り、それに深く影響を受けたヴィシネグラツキーは、「宇宙の意識」に表現を与えようと試みた。1916年から1917年にかけて作曲されたオラトリオ「存在の一日」は「人間の意識ががもっとも原始的な形式から宇宙の意識という最終段階へと成長することの反映を意図」したものであった。ヴィシネグラツキーにとって、このような意識の発展を音楽的にとらえるために和声を拡大することが必要となり、四分音や十二分音といった微分音を用いた作曲を試みることになった。1918年の「四つの断片」作品5はその最初の作品である。
ロシア革命後の混乱を避けるため、ヴィシネグラツキーは1920年にパリに亡命した。1922年から1923年の間はベルリンに滞在し、数人の仲間と共同研究を進めながら四分音ピアノの試作をおこなったりもした。この共同研究は1926年に中断され、ヴィシネグラツキーはパリに戻ったが、四分音ピアノの開発には引き続き取り組んで1929年に完成した。1934年には1オクターヴ内にある24の音を体系的に使用した「24の前奏曲」作品22を作曲し、1967年にはトーン・クラスターを多用した「アンテグラシオン」作品49が作曲された。
ヴィシネグラツキーにはメシアンのような支持者もいたが、彼の作品が演奏される機会も生前は少なかった。
→J.E.ボウルト編著「ロシア・アヴァンギャルド芸術」(岩波書店)
→F.マース「ロシア音楽史」(春秋社)
→カンディンスキー/マルク編「青騎士」(白水社)










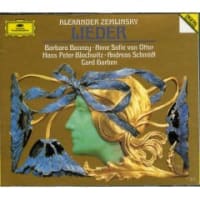
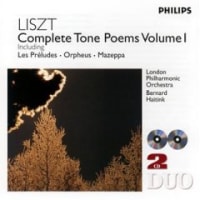
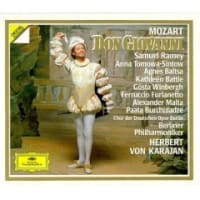
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます