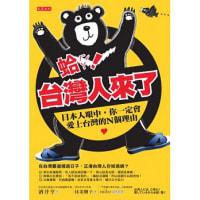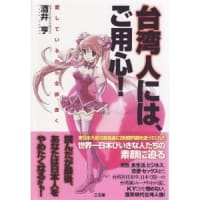最近、中国の堕落ぶりを見て憤慨することしきりだが、俄かに80年代以前のまだまだ清貧だったころを思い出して、ふと「白毛女」とか「紅色娘子軍」とか「東方紅」などを「ようつべ」とか中国産DVDなどで見て、感銘を新たにしている。いずれもその昔、小学生のころにNHKテレビ中国語講座などで紹介されたり(当時の講師は藤堂明保で、テーマ曲も白毛女のテーマ「北風吹」だった)、大学学部時代に見たりした、懐かしいものだ。しかも、それらのビデオを見ていると「反動地主階級および反動国民党を打倒せよ!」というシーンがあるので、共感できるんだな、これがw。
そういえば思い出した、私自身は少なくとも小学生のころの70年代から大学生のころの80年代までは、中国は割りと好きだったのだ。
もちろん、台湾は中国とは別だと昔から思っていたし、スローガン・演出過剰の中共体制には違和感はあったが、今のように中国および中国人は嫌いではなかった。
世論調査でみても、それは日本人一般の感覚でもあったといえる。少なくとも80年代まで、日本人は中国に好感を抱いていた。当時中国を「嫌い」という人は少なかった。
それが、ここまで中国が日本人に嫌われてしまった原因は、はっきりいって中国および中国人そのものが堕落してしまったからにほかならない。
そう思って、60年代以前の様板戯=模範劇を見ると、やはり当時の中国人は貧しいながらも、それなりに理想や思想や道徳に燃えて、凛としたものがあったと思った。
もちろん、中国人の本質は変わらない。嘘つきで、平気で人を騙し、人のものを盗り、散らかす。これは80年代以前にもあった。
また、様板戯でも、反動的地主階級をつるし上げるところは、伝統的な中華の凌遅刑のやり方をそのまま踏襲、増幅したものであり、どこにも革命的なものはなく、どうしょうもない封建的かつ野蛮なやり方である。
しかし、私自身が80年代末期に中国領に入って実際に体験したように、それでも、戦後共産主義思想で染め抜かれた中国では、中国人の中にももっと実直な人は多かったように思う。私は89年、深センに入ったときも、今では考えられないことだろうが、誰も金をちょろまさかず、マジメに応対してくれた。そういう意味では、当時の中国人は貧しかったが、人間的にはまだまだ普通だったといえる。
これは、まだまだ89年までは、毛沢東思想による社会・思想統制のタガが機能しており、思想統制の成果から、中国人の悪い本質がそれほど放出されず、思想によって規律が保たれていたからであろう。
八路軍の「三大規律八項注意」というのがあって、どうせ建前でどこまで本気で守られたのか信じられないが、それでもそれによって国民党よりも支持を集めることに成功したのは事実だから、八路軍はもちろん、戦後人民中国になってからも「三大規律八項注意」はそれなりに機能していたとみるべきだろう。
中国人の本質は変わらない。そこを毛沢東は知っていたがゆえに、徹底的に思想統制し、規律で縛り上げたのだろう。やはり毛沢東は偉大だった。あの中国人たちを道徳的に最低厳律することに成功していたのだから。
ところが、小平がバカだった。それでも80年代はまだ良かった。かなり統制を残したままでの「改革開放」だったから、中国人が欲望に溺れてそれで突っ走ることにはならなかった。
そうした点は、80年代の中国映画にも示されている。当時の中国映画は、芸術的なセンスと思想的な深みが兼ね備えられていて、きわめて質の高いものができた。
ある意味で、78年から89年天安門事件までが、中国人が文革ほどは画一的、統制的ではないものの、それなりに人間とは何かをよく考え、かつ共産主義的道徳と規律もそれなりに機能していたという意味で、中国社会としては最良の時代だったといえるのかも知れない。
中国が今のような堕落をするきっかけになったのは、89年の天安門事件が弾圧で息の根を止められて思想や理想の根を奪い、さらに93年の南巡講話によって「金儲けのためには手段を選ばなくても良い」という破廉恥な考え方が公認されたことで、人間としての最低限のモラルと規律を失い、経済的欲望を開放し、中国人が本質的にもっている利己的で破廉恥な部分を引き出してしまった、つまりパンドラの箱を開けてしまったところに問題の根源がある。
江沢民が品性下劣だったからいかんという中国人もいるが、実際に中国社会を観察すると89年から93年の間が転換期だったといえるようなので、問題の元凶はやはり小平にあったといえそうである。
そういう意味で、改革開放、特に93年の南巡講話は誤りであり、80年代は確かに良かったとしても、80年代がその後の堕落につながったという点では、やはり70年代以前に戻るほうが中国人自身にとっても、人類全体にとっても良いといえるのではなかろうか?
今と比べるなら、あの狂気といえる文革ですら、まだマシだったといえるくらいだ。文革でも特に初期の上海の動きは、多様で、それなりに面白いものがあったからだ。
台湾や日本など西側には、バカの一つ覚えみたいに「中国の民主化」を主張する無知・低脳がいるが、経済的に欲望を引き出した改革開放が、中国人の本性をむき出しにして、ここまで中国社会が堕落したのだから、政治的にも欲望を引き出す民主化なんて行ったら、早い話がたちまち衆愚、愚民政治に陥り、選挙では日本や台湾に戦争を仕掛けようという煽動家が当選するだけだろう。
中国人なんかよりも民度が高く、モラルもある台湾人が、選挙民主主義を通じて、馬英九なるどうしょうもないバカを選んでしまうように、選挙民主主義なるものは、実は制度として信頼に足るものではないことは明らかである。
民主主義が本当に成熟するには、西欧や北欧のように100年以上の試行錯誤や闘争が必要なのだ。
そうではないと、単なる衆愚に陥り、ハンサムだからとか、口がうまいだけだけで、指導者に選ばれてしまう。
それは民主主義の歴史を見てもそうだ。19世紀の米国や英国は、金権が横行し、古代アテネは衆愚政治が横行した。
たかだか市場経済を導入しただけで、ここまでモラルが底割れして、欲望むき出しの堕落社会となった中国に、民主主義など不可能だろう。もし選挙ができたとしても、ヒトラーみたいなのを生み出すだけだろう。
事実、同じように共産主義政治から転換したロシアが、市場経済と民主主義を導入しても、結局、市場経済はマフィア経済となり、民主主義は根付かずにすぐに独裁政治に逆戻りしてしまったではないか。
韓国と台湾ですら民主主義がまともに機能できているか微妙なところ。それを中国に輸出しようなんて、はっきりいって狂気の沙汰であり、中国人の本質をわかっていないとしか言いようが無い。民主主義は結果であって、手段ではない。
しかも、今の中国のブルジョア経済・文化にしたところでたいしたレベルではない。ブルジョア文化なら、米国に勝るものはない。中国がブルジョア経済や文化を使って米国と張り合っても無意味である。誰も中国なんか尊敬しない。中国が米国と対等に戦い、世界から尊敬を受けたいなら、はっきりいって毛沢東思想しかない。そしてそれこそ中国の風土と特性に合致し、中国人の本質にも沿った正しいあり方である。
今後の中国に必要なのは、民主化でも経済成長でもなく、毛沢東思想による武装と統制である。堕落したブルジョア文化をすべて追放し、思想闘争を内部で戦わせ、日々の生活は自力更生、内向きで、清貧に生きていくべきである。
それこそが、中国社会を腐敗と堕落と崩壊から救い、中国を米国の二流の模倣でなく、中国独自の特色と個性によって、世界、特に第三世界から尊敬を勝ち取り、米国的新自由主義とは異なる道を示すことになるだろう。
物質的に貧しいことは悪いことではない。問題は今の中国は物質的にもたいしたことがないくせに、精神的に徹底的に貧しくなっていることである。これではいつまでたっても、物質的には豊かな米国を凌駕することなんかできない。中国は中国独自の基準と思想を打ち出して戦うべきなのだ。
そういえば思い出した、私自身は少なくとも小学生のころの70年代から大学生のころの80年代までは、中国は割りと好きだったのだ。
もちろん、台湾は中国とは別だと昔から思っていたし、スローガン・演出過剰の中共体制には違和感はあったが、今のように中国および中国人は嫌いではなかった。
世論調査でみても、それは日本人一般の感覚でもあったといえる。少なくとも80年代まで、日本人は中国に好感を抱いていた。当時中国を「嫌い」という人は少なかった。
それが、ここまで中国が日本人に嫌われてしまった原因は、はっきりいって中国および中国人そのものが堕落してしまったからにほかならない。
そう思って、60年代以前の様板戯=模範劇を見ると、やはり当時の中国人は貧しいながらも、それなりに理想や思想や道徳に燃えて、凛としたものがあったと思った。
もちろん、中国人の本質は変わらない。嘘つきで、平気で人を騙し、人のものを盗り、散らかす。これは80年代以前にもあった。
また、様板戯でも、反動的地主階級をつるし上げるところは、伝統的な中華の凌遅刑のやり方をそのまま踏襲、増幅したものであり、どこにも革命的なものはなく、どうしょうもない封建的かつ野蛮なやり方である。
しかし、私自身が80年代末期に中国領に入って実際に体験したように、それでも、戦後共産主義思想で染め抜かれた中国では、中国人の中にももっと実直な人は多かったように思う。私は89年、深センに入ったときも、今では考えられないことだろうが、誰も金をちょろまさかず、マジメに応対してくれた。そういう意味では、当時の中国人は貧しかったが、人間的にはまだまだ普通だったといえる。
これは、まだまだ89年までは、毛沢東思想による社会・思想統制のタガが機能しており、思想統制の成果から、中国人の悪い本質がそれほど放出されず、思想によって規律が保たれていたからであろう。
八路軍の「三大規律八項注意」というのがあって、どうせ建前でどこまで本気で守られたのか信じられないが、それでもそれによって国民党よりも支持を集めることに成功したのは事実だから、八路軍はもちろん、戦後人民中国になってからも「三大規律八項注意」はそれなりに機能していたとみるべきだろう。
中国人の本質は変わらない。そこを毛沢東は知っていたがゆえに、徹底的に思想統制し、規律で縛り上げたのだろう。やはり毛沢東は偉大だった。あの中国人たちを道徳的に最低厳律することに成功していたのだから。
ところが、小平がバカだった。それでも80年代はまだ良かった。かなり統制を残したままでの「改革開放」だったから、中国人が欲望に溺れてそれで突っ走ることにはならなかった。
そうした点は、80年代の中国映画にも示されている。当時の中国映画は、芸術的なセンスと思想的な深みが兼ね備えられていて、きわめて質の高いものができた。
ある意味で、78年から89年天安門事件までが、中国人が文革ほどは画一的、統制的ではないものの、それなりに人間とは何かをよく考え、かつ共産主義的道徳と規律もそれなりに機能していたという意味で、中国社会としては最良の時代だったといえるのかも知れない。
中国が今のような堕落をするきっかけになったのは、89年の天安門事件が弾圧で息の根を止められて思想や理想の根を奪い、さらに93年の南巡講話によって「金儲けのためには手段を選ばなくても良い」という破廉恥な考え方が公認されたことで、人間としての最低限のモラルと規律を失い、経済的欲望を開放し、中国人が本質的にもっている利己的で破廉恥な部分を引き出してしまった、つまりパンドラの箱を開けてしまったところに問題の根源がある。
江沢民が品性下劣だったからいかんという中国人もいるが、実際に中国社会を観察すると89年から93年の間が転換期だったといえるようなので、問題の元凶はやはり小平にあったといえそうである。
そういう意味で、改革開放、特に93年の南巡講話は誤りであり、80年代は確かに良かったとしても、80年代がその後の堕落につながったという点では、やはり70年代以前に戻るほうが中国人自身にとっても、人類全体にとっても良いといえるのではなかろうか?
今と比べるなら、あの狂気といえる文革ですら、まだマシだったといえるくらいだ。文革でも特に初期の上海の動きは、多様で、それなりに面白いものがあったからだ。
台湾や日本など西側には、バカの一つ覚えみたいに「中国の民主化」を主張する無知・低脳がいるが、経済的に欲望を引き出した改革開放が、中国人の本性をむき出しにして、ここまで中国社会が堕落したのだから、政治的にも欲望を引き出す民主化なんて行ったら、早い話がたちまち衆愚、愚民政治に陥り、選挙では日本や台湾に戦争を仕掛けようという煽動家が当選するだけだろう。
中国人なんかよりも民度が高く、モラルもある台湾人が、選挙民主主義を通じて、馬英九なるどうしょうもないバカを選んでしまうように、選挙民主主義なるものは、実は制度として信頼に足るものではないことは明らかである。
民主主義が本当に成熟するには、西欧や北欧のように100年以上の試行錯誤や闘争が必要なのだ。
そうではないと、単なる衆愚に陥り、ハンサムだからとか、口がうまいだけだけで、指導者に選ばれてしまう。
それは民主主義の歴史を見てもそうだ。19世紀の米国や英国は、金権が横行し、古代アテネは衆愚政治が横行した。
たかだか市場経済を導入しただけで、ここまでモラルが底割れして、欲望むき出しの堕落社会となった中国に、民主主義など不可能だろう。もし選挙ができたとしても、ヒトラーみたいなのを生み出すだけだろう。
事実、同じように共産主義政治から転換したロシアが、市場経済と民主主義を導入しても、結局、市場経済はマフィア経済となり、民主主義は根付かずにすぐに独裁政治に逆戻りしてしまったではないか。
韓国と台湾ですら民主主義がまともに機能できているか微妙なところ。それを中国に輸出しようなんて、はっきりいって狂気の沙汰であり、中国人の本質をわかっていないとしか言いようが無い。民主主義は結果であって、手段ではない。
しかも、今の中国のブルジョア経済・文化にしたところでたいしたレベルではない。ブルジョア文化なら、米国に勝るものはない。中国がブルジョア経済や文化を使って米国と張り合っても無意味である。誰も中国なんか尊敬しない。中国が米国と対等に戦い、世界から尊敬を受けたいなら、はっきりいって毛沢東思想しかない。そしてそれこそ中国の風土と特性に合致し、中国人の本質にも沿った正しいあり方である。
今後の中国に必要なのは、民主化でも経済成長でもなく、毛沢東思想による武装と統制である。堕落したブルジョア文化をすべて追放し、思想闘争を内部で戦わせ、日々の生活は自力更生、内向きで、清貧に生きていくべきである。
それこそが、中国社会を腐敗と堕落と崩壊から救い、中国を米国の二流の模倣でなく、中国独自の特色と個性によって、世界、特に第三世界から尊敬を勝ち取り、米国的新自由主義とは異なる道を示すことになるだろう。
物質的に貧しいことは悪いことではない。問題は今の中国は物質的にもたいしたことがないくせに、精神的に徹底的に貧しくなっていることである。これではいつまでたっても、物質的には豊かな米国を凌駕することなんかできない。中国は中国独自の基準と思想を打ち出して戦うべきなのだ。