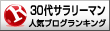本当は昨日もこれをやりたかったんだけど、
SOPHIAの記事を書いていたら熱が入ってかなり時間がかかったもので…
で、今日頑張っているわけ。
これまで
・自分のこれまでとドビュッシ-の関係
・生誕150周年イベント
・作曲家別名曲解説ライブラリ
・西洋音楽史
から書いてきたものの、要求文字数が1500であることが判明し、
各楽章について多少なりとも言及しないといけないこと、
これまでその辺りの記述はしていないことからその辺りの補稿をする。
--! (この部分は蛇足かな?)
旋律のない音楽、和声のない音楽はあるがリズムのない音楽はない、と
芥川也寸志は口にしている("音楽の基礎",ISBN4-00-414057-9 P87)。
これをヒントに、まずは各楽章のリズムに関する記述だけしておく。
テンポの変化は段階的にやるものなので定量化するのが難しく、
拍子の変化からのアプローチ。
--!
各楽章毎の拍子の変化回数は、
1楽章:14回 2楽章:2回 3楽章:0回
であり、1楽章の拍子の変化が目まぐるしいことに特徴がある。何故か。
…1楽章の題名は「海の夜明けから真昼まで」 (De l'aube à midi sur la mer)
であった。題名を見ると、どうやら6時間(?)くらいの時間経過を音楽で表現することになっている。
時間経過を曲のサブタイトルに据えるというのは結構変わった話であり、
他の楽章の題名は、特に時間の経過を明言したものではない。
このあたりにヒントがありそうである。
ということで譜面を見ていくと、確かに時間経過といえばそうなのだが、
直接拍子が変わったときに行われているのは"場面転換"である。
1楽章では時間の経過の結果生じた情景の転換のために拍子を変える傾向があり、
夜明けから昼間までの時間経過を表現するために13回拍子が変わった、と言ってよい。
他の楽章では同一拍子内で転調が何度も行われているが、
1楽章では転調する場所は必ず拍子の変化とセットである。
※但し、1小節限定で拍子が変わっている場所も4箇所あって、
これは同場面内での"ゆらぎ"を表現したものと思われる。
一楽章「海の夜明けから真昼まで」 (De l'aube à midi sur la mer)
6/4(1)→4/4(6)→6/8(31)→9/8(67)→6/8(68)→4/4(84)→6/8(100)→
12/8(101)→6/8(110)→12/8(111)→6/4(122)→4/4(132)→2/4(139)→3/4(140)→4/4(141) 13回
しばらくは海は穏やか。夜明けとともに海も目覚め、ゆったりした大波にさざ波が乗り
その後の高波を予感、期待させるように徐々にエネルギーを高めていくが、一旦は静まる。
その後、(4divのチェロによる)恐らくは表紙の画から着想された高波のうねり、エネルギーの奔流が提示される。
その後波のエネルギーは一旦静まるが、時間経過とともに、太陽の高さとともに海の持つエネルギーが高まっていき、
見ている人の心を呑み込んでいく。曲の終わりでは波は止み、
陽の眩しい煌きを放ちながら、海はまた雄々しい全体像へ回帰していく。
1楽章「波の戯れ」 (Jeux de vagues)
3/4(1)→3/8(9)→3/4(36) 2回
2楽章で流れている音楽は"波の戯れ"というサブタイトルの縛りで解釈するのが難しい曲である。
実際、私達の練習(合奏)中に、良く"ここで水の精が出てきました!"というような言葉が飛交うこともあり、
題名以外の想像の余地が良く残されている。最初に述べたようなドビュッシー自身の"幻想"が
最も良く発揮されているように思われる。
我々が想像力を働かせるだけの自由度を持った、ムーディなサウンドのみが提示されている。
しかし、その雰囲気とは、途中まではきらびやかなものではなく、どちらかと言えば不気味なもの。
多分、この標題を見ないで私が曲に題名をつけろと言われたら、
"うっかり洞穴に入って彷徨い歩いていたら怖い妖精に会いました"とか言ってしまいそう。
彷徨っているイメージはコーラングレの主旋律(全音音楽的な動き)の印象。
但し、後半、フルートとオーボエのユニゾンから始まり
オケ全体へ波及する盛り上がりはこの曲の中でも最も豪華で美しいものと思う。
他、曲の作りでアプローチするため、少し自分のパートの話をしたい。
筆者はVcパートだが、この楽章はパート内の上下での完全5度の和音が多用されていて、
曲の前半のおどろおどろしいムードを支配しているのか、と感じることが多々ある。
※本当は、"オケ全体で従来の作曲技法では禁則とされている平行5度が多発している、という、
ドビュッシーの曲のアナリーゼでは必ず書かれるテキストを書こうと思ったが、
スコアを見た印象では、5度の動きが多いのは低弦だけだったので、パートの話に落とさざるを得なかった。
3楽章「風と海の対話」 (Dialogue du vent et de la mer)
2/2(1) 拍子の変更なし
サブタイトルでは"対話"とあるけれど、大きくは前半が"不和"で、後半は"融和"と考えてもらった方が
分かりやすいと思われる。大筋は、
(前半)嵐の予兆→荒れる海→嵐の到来を描写
(後半)嵐が止む→静謐な時間が(木管の動きで)続く→海のエネルギーが再び高まる
→大洋礼賛と言わんばかりの盛り上がりで曲を締める。
後半の音楽にどのように風が関係しているのか、あれこれ考えてみたものの
筆者の頭では良い感じのイメージが浮かばなかった。
3曲目(ここまで書いて、"楽章"の表記が正しくないことに思い至る)は
拍子の変更もなく、曲の速度も全体的に速めで、3曲の中では最も直線的である。
以上、随分と大雑把な部分もあるが、解説文を書いている以上は
ある程度はここに書いた通りの音楽がお客様の頭の中にも想起されることを願う。
◇
Wikipedia中の曲紹介から一部引用。
この作品の次作にあたる管弦楽のための『映像』の作曲中にドビュッシーは、
「音楽の本質は形式にあるのではなく色とリズムを持った時間なのだ」と語っているが、
本作はこの言葉を裏付ける「音楽」である。
とある。
これをどう解釈しようかという問題はあるが、
色、リズム、時間という要素は重要なものとして残していることに注目すべきだろう。
ゆえにこの曲の紹介文に色、リズム、時間の話を盛り込むことを考えてみたい。
世に優れた記事は沢山あったけれど、そうは言ってもこの曲ほど隙だらけの曲はこれまで見たことがない。
具体的には、ぐうの音も出ないほどのアナリーゼが世に出回っている曲は特にロマン派以前では
沢山見かけたのだけど、この曲はドビュッシーの描いたムードが強烈であり、
曲紹介を書くつもりがこのムードをどう筆舌に尽くしてやろうかという
情景描写の腕比べのような、少々趣の異なった曲紹介が行われているのであった。
◇
ところで、ここにきて全音のスコアの解説を書いている菅原氏の書いていることが今になって
非常に良く理解できるような状態。これだけ草稿を書いてみたところで、
プロ?の出発点にようやく追いついたような気がする程度か、と少々落胆してしまう部分もないではない。
とはいえ、この菅原明朗という方は、僕はこのスコアで初めて名前を聞いたけれども
日本作曲家界で偉い方のようであり、その方の仰ることに理解が追いついたことを喜ぶべきかもしれない。
(決して難解な言葉を振りかざした衒学的な紹介文ではないけれど。)
これから仕上げに入らなくちゃ。投稿時間は17:35だけど、書き始めは13:20。
やはり、仕上げを意識して完成度を高める作業は容易でない。
SOPHIAの記事を書いていたら熱が入ってかなり時間がかかったもので…
で、今日頑張っているわけ。
これまで
・自分のこれまでとドビュッシ-の関係
・生誕150周年イベント
・作曲家別名曲解説ライブラリ
・西洋音楽史
から書いてきたものの、要求文字数が1500であることが判明し、
各楽章について多少なりとも言及しないといけないこと、
これまでその辺りの記述はしていないことからその辺りの補稿をする。
--! (この部分は蛇足かな?)
旋律のない音楽、和声のない音楽はあるがリズムのない音楽はない、と
芥川也寸志は口にしている("音楽の基礎",ISBN4-00-414057-9 P87)。
これをヒントに、まずは各楽章のリズムに関する記述だけしておく。
テンポの変化は段階的にやるものなので定量化するのが難しく、
拍子の変化からのアプローチ。
--!
各楽章毎の拍子の変化回数は、
1楽章:14回 2楽章:2回 3楽章:0回
であり、1楽章の拍子の変化が目まぐるしいことに特徴がある。何故か。
…1楽章の題名は「海の夜明けから真昼まで」 (De l'aube à midi sur la mer)
であった。題名を見ると、どうやら6時間(?)くらいの時間経過を音楽で表現することになっている。
時間経過を曲のサブタイトルに据えるというのは結構変わった話であり、
他の楽章の題名は、特に時間の経過を明言したものではない。
このあたりにヒントがありそうである。
ということで譜面を見ていくと、確かに時間経過といえばそうなのだが、
直接拍子が変わったときに行われているのは"場面転換"である。
1楽章では時間の経過の結果生じた情景の転換のために拍子を変える傾向があり、
夜明けから昼間までの時間経過を表現するために13回拍子が変わった、と言ってよい。
他の楽章では同一拍子内で転調が何度も行われているが、
1楽章では転調する場所は必ず拍子の変化とセットである。
※但し、1小節限定で拍子が変わっている場所も4箇所あって、
これは同場面内での"ゆらぎ"を表現したものと思われる。
一楽章「海の夜明けから真昼まで」 (De l'aube à midi sur la mer)
6/4(1)→4/4(6)→6/8(31)→9/8(67)→6/8(68)→4/4(84)→6/8(100)→
12/8(101)→6/8(110)→12/8(111)→6/4(122)→4/4(132)→2/4(139)→3/4(140)→4/4(141) 13回
しばらくは海は穏やか。夜明けとともに海も目覚め、ゆったりした大波にさざ波が乗り
その後の高波を予感、期待させるように徐々にエネルギーを高めていくが、一旦は静まる。
その後、(4divのチェロによる)恐らくは表紙の画から着想された高波のうねり、エネルギーの奔流が提示される。
その後波のエネルギーは一旦静まるが、時間経過とともに、太陽の高さとともに海の持つエネルギーが高まっていき、
見ている人の心を呑み込んでいく。曲の終わりでは波は止み、
陽の眩しい煌きを放ちながら、海はまた雄々しい全体像へ回帰していく。
1楽章「波の戯れ」 (Jeux de vagues)
3/4(1)→3/8(9)→3/4(36) 2回
2楽章で流れている音楽は"波の戯れ"というサブタイトルの縛りで解釈するのが難しい曲である。
実際、私達の練習(合奏)中に、良く"ここで水の精が出てきました!"というような言葉が飛交うこともあり、
題名以外の想像の余地が良く残されている。最初に述べたようなドビュッシー自身の"幻想"が
最も良く発揮されているように思われる。
我々が想像力を働かせるだけの自由度を持った、ムーディなサウンドのみが提示されている。
しかし、その雰囲気とは、途中まではきらびやかなものではなく、どちらかと言えば不気味なもの。
多分、この標題を見ないで私が曲に題名をつけろと言われたら、
"うっかり洞穴に入って彷徨い歩いていたら怖い妖精に会いました"とか言ってしまいそう。
彷徨っているイメージはコーラングレの主旋律(全音音楽的な動き)の印象。
但し、後半、フルートとオーボエのユニゾンから始まり
オケ全体へ波及する盛り上がりはこの曲の中でも最も豪華で美しいものと思う。
他、曲の作りでアプローチするため、少し自分のパートの話をしたい。
筆者はVcパートだが、この楽章はパート内の上下での完全5度の和音が多用されていて、
曲の前半のおどろおどろしいムードを支配しているのか、と感じることが多々ある。
※本当は、"オケ全体で従来の作曲技法では禁則とされている平行5度が多発している、という、
ドビュッシーの曲のアナリーゼでは必ず書かれるテキストを書こうと思ったが、
スコアを見た印象では、5度の動きが多いのは低弦だけだったので、パートの話に落とさざるを得なかった。
3楽章「風と海の対話」 (Dialogue du vent et de la mer)
2/2(1) 拍子の変更なし
サブタイトルでは"対話"とあるけれど、大きくは前半が"不和"で、後半は"融和"と考えてもらった方が
分かりやすいと思われる。大筋は、
(前半)嵐の予兆→荒れる海→嵐の到来を描写
(後半)嵐が止む→静謐な時間が(木管の動きで)続く→海のエネルギーが再び高まる
→大洋礼賛と言わんばかりの盛り上がりで曲を締める。
後半の音楽にどのように風が関係しているのか、あれこれ考えてみたものの
筆者の頭では良い感じのイメージが浮かばなかった。
3曲目(ここまで書いて、"楽章"の表記が正しくないことに思い至る)は
拍子の変更もなく、曲の速度も全体的に速めで、3曲の中では最も直線的である。
以上、随分と大雑把な部分もあるが、解説文を書いている以上は
ある程度はここに書いた通りの音楽がお客様の頭の中にも想起されることを願う。
◇
Wikipedia中の曲紹介から一部引用。
この作品の次作にあたる管弦楽のための『映像』の作曲中にドビュッシーは、
「音楽の本質は形式にあるのではなく色とリズムを持った時間なのだ」と語っているが、
本作はこの言葉を裏付ける「音楽」である。
とある。
これをどう解釈しようかという問題はあるが、
色、リズム、時間という要素は重要なものとして残していることに注目すべきだろう。
ゆえにこの曲の紹介文に色、リズム、時間の話を盛り込むことを考えてみたい。
世に優れた記事は沢山あったけれど、そうは言ってもこの曲ほど隙だらけの曲はこれまで見たことがない。
具体的には、ぐうの音も出ないほどのアナリーゼが世に出回っている曲は特にロマン派以前では
沢山見かけたのだけど、この曲はドビュッシーの描いたムードが強烈であり、
曲紹介を書くつもりがこのムードをどう筆舌に尽くしてやろうかという
情景描写の腕比べのような、少々趣の異なった曲紹介が行われているのであった。
◇
ところで、ここにきて全音のスコアの解説を書いている菅原氏の書いていることが今になって
非常に良く理解できるような状態。これだけ草稿を書いてみたところで、
プロ?の出発点にようやく追いついたような気がする程度か、と少々落胆してしまう部分もないではない。
とはいえ、この菅原明朗という方は、僕はこのスコアで初めて名前を聞いたけれども
日本作曲家界で偉い方のようであり、その方の仰ることに理解が追いついたことを喜ぶべきかもしれない。
(決して難解な言葉を振りかざした衒学的な紹介文ではないけれど。)
これから仕上げに入らなくちゃ。投稿時間は17:35だけど、書き始めは13:20。
やはり、仕上げを意識して完成度を高める作業は容易でない。