この前は、小田急線訴訟の多数意見について考えてみたので、今回は、いささか時期はずれではあるが、反対意見や補足意見についてみてみたい。
*****

小田急線訴訟の最高裁判決には、4裁判官の反対意見が付せられている。その反対意見の趣旨は、主文2項(1)~(3)、すなわち、小田急線の高架化事業そのものについてではなく、それに付随して計画された、付属街路事業について、細分化されたそれぞれの付属街路事業野事業地内に不動産を所有しない原告について、原告適格を有しないとした多数意見に反対し、さらに原告適格を有する者を拡張しようという意見である。
簡単にいえば、多数意見が原告適格について画期的な判断をしたのに対して、さらに画期的な判断をすることが良いとする意見ということになる。その要点は,
(1) 付属街路事業とは,鉄道線の効果によって生じる日照阻害を緩和するため,等時間日影線が規制値を満足しないところについて環境空間(環境側道)を設ける事業であり,鉄道線の連続立体交差化事業の一部を構成するものであるから,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可とは,形式はともあれ,実体的には一体の行政処分である。
(2) 本件において,建設大臣は,本件鉄道事業認可のみでその適法要件(都市計画事業の事業千野周辺に居住する住民が都市計画事業により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないこと)に適合することを図っていることが明らかである。
(3) そうすると,本件鉄道事業認可により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるおそれのある上告人らは,本件各付属街路事業認可についてもその取消しを求め,付属街路事業をも構成要素とする連続立体交差化事業の計画内容全他の見直しを迫り,健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという都市計画法で保護された利益の回復を求める利益を有する。
(4) 上告人らに対し,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格のみを認め,本件各付属街路事業認可については原告適格を認めないとすると,仮に上告人らが前者の取消請求訴訟に勝訴しても,取消判決の行政庁に対する拘束力は本件各付属街路事業認可には及ばないから,連続立体交差化事業の計画内容全体の見直しを得ることができない。
というものである。
☆☆☆☆☆

この論理はどんなものであろうか。確かに,鉄道線の高架化に環境側道が必然的に伴うことは避けられないところであろうが,鉄道線の高架化と環境側道は,事業主体を別にしても実施できるものであり,たまたま実施主体が同一であったからといって,それを根拠に「実体的に一体」というのは言い過ぎのように思える。
また,環境側道については,側道としての環境被害(例えば,鉄道高架にはない排気ガスという問題もある。)が生じる可能性があるものであって,これは,付属街路事業認可のみの取消事由とされなければならない。最初から,不可分一体論で原告適格の間口を拡げてしまうと,このような環境側道固有の問題を見過ごす可能性も否定できない。
△△△△△

この点について,藤田補足意見は,行政上のプロジェクトがどのように分節されるかは,一般的に立法者意思に従うべきものであるということと,一審判決が採用した不可分一体論は,事業地内に不動産を所有する者に限って原告適格を認めるという旧判例に従うことを前提として原告適格を拡張する便法であり,今回の判決で原告適格が拡張されたから,そのような便法を採る前提が失われたということを,反対意見に与しない理由として述べている。

また,今井補足意見は,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可が別個の行政処分であることは,原審が確定した事実であるということ,本件各付属街路事業認可の違法性は本件鉄道事業認可の違法性の主張の中で考慮できないわけではないこと,本件各付属街路事業認可には,それ固有の瑕疵があり得ること,本件各付属街路事業認可の違法を本件鉄道事業認可の違法性として主張できないわけではないこと,を理由として,反対意見に与しないと述べている。
藤田補足意見が理論面からの抽象的なアプローチであるのに対し,今井補足意見は訴訟運営という実務面からのアプローチといえるだろう。私としては,今井補足意見が,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可の間で,違法性の主張を相互に融通できるという点の理由が今ひとつ明らかでないこと(ここはなかなか説明しづらいところのように思える。)はあるにしても,穏当なところではないかという気がする。
▽▽▽▽▽

ただ,多数意見が本件鉄道事業認可の取消訴訟の原告適格を認めた一定範囲の近隣住民について,付属街路事業認可の取消訴訟の原告適格を認めなかった理由については,次のように説示されている。

「上告人らは,別紙上告人目録2及び3記載の各上告人らがそれぞれ別紙事業認可目録6及び7記載の各認可に係る事業の事業地内の不動産につき権利を有する旨をいうほかには,本件各付属街路事業に係る個々の事業の認可によって,自己のどのような権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるかについて,具体的な主張をしていない。そして,本件各付属街路事業に係る付属街路が,小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して日照への影響を軽減することを主たる目的として設置されるものであることに加え,これらの付属街路の規模等に照らせば,本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない上告人らについて,本件各付属街路事業が実施されることにより健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認めることはできない。」
※※※※※

この文章は,そのまま裏返して受け取ると,本件各付属街路事業による権利・利益の侵害について具体的な主張をすれば,原告適格を認めるという趣旨である。すなわち,多数意見といえども,付属街路の周辺住民について,一律に本件各付属街路事業認可の取消訴訟の原告適格を否定したわけではないことが明らかである。
極論すれば,多数意見と反対意見の差は,権利・利益の侵害について「具体的な主張」をする必要があると考えるか(多数意見),その必要はないと考えるか(反対意見)という点にあるに過ぎない。
勿論,多数意見に従えば,本件各付属街路事業認可は,それぞれの付属街路の周辺住民が個別に争うことが原則になるだろうし,反対意見に従えば,本件鉄道事業認可がある限り,本件鉄道事業認可を争うことのできる広い範囲の住民に原告適格が認められるという違いはある。
しかし,原告らが,一体化論にこだわるのではなく,本件各付属街路事業が周辺住民に及ぼす影響(健康又は生活環境に係る著しい被害)について,もう少し丁寧な主張をしていれば,多数意見は違っていたかもしれないのである。そう考えると,多数意見と反対意見の違いは,それほど大きなものではなく,実質的には紙一重というところなのかもしれない。

*****

小田急線訴訟の最高裁判決には、4裁判官の反対意見が付せられている。その反対意見の趣旨は、主文2項(1)~(3)、すなわち、小田急線の高架化事業そのものについてではなく、それに付随して計画された、付属街路事業について、細分化されたそれぞれの付属街路事業野事業地内に不動産を所有しない原告について、原告適格を有しないとした多数意見に反対し、さらに原告適格を有する者を拡張しようという意見である。
簡単にいえば、多数意見が原告適格について画期的な判断をしたのに対して、さらに画期的な判断をすることが良いとする意見ということになる。その要点は,
(1) 付属街路事業とは,鉄道線の効果によって生じる日照阻害を緩和するため,等時間日影線が規制値を満足しないところについて環境空間(環境側道)を設ける事業であり,鉄道線の連続立体交差化事業の一部を構成するものであるから,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可とは,形式はともあれ,実体的には一体の行政処分である。
(2) 本件において,建設大臣は,本件鉄道事業認可のみでその適法要件(都市計画事業の事業千野周辺に居住する住民が都市計画事業により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないこと)に適合することを図っていることが明らかである。
(3) そうすると,本件鉄道事業認可により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるおそれのある上告人らは,本件各付属街路事業認可についてもその取消しを求め,付属街路事業をも構成要素とする連続立体交差化事業の計画内容全他の見直しを迫り,健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという都市計画法で保護された利益の回復を求める利益を有する。
(4) 上告人らに対し,本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格のみを認め,本件各付属街路事業認可については原告適格を認めないとすると,仮に上告人らが前者の取消請求訴訟に勝訴しても,取消判決の行政庁に対する拘束力は本件各付属街路事業認可には及ばないから,連続立体交差化事業の計画内容全体の見直しを得ることができない。
というものである。
☆☆☆☆☆

この論理はどんなものであろうか。確かに,鉄道線の高架化に環境側道が必然的に伴うことは避けられないところであろうが,鉄道線の高架化と環境側道は,事業主体を別にしても実施できるものであり,たまたま実施主体が同一であったからといって,それを根拠に「実体的に一体」というのは言い過ぎのように思える。
また,環境側道については,側道としての環境被害(例えば,鉄道高架にはない排気ガスという問題もある。)が生じる可能性があるものであって,これは,付属街路事業認可のみの取消事由とされなければならない。最初から,不可分一体論で原告適格の間口を拡げてしまうと,このような環境側道固有の問題を見過ごす可能性も否定できない。
△△△△△

この点について,藤田補足意見は,行政上のプロジェクトがどのように分節されるかは,一般的に立法者意思に従うべきものであるということと,一審判決が採用した不可分一体論は,事業地内に不動産を所有する者に限って原告適格を認めるという旧判例に従うことを前提として原告適格を拡張する便法であり,今回の判決で原告適格が拡張されたから,そのような便法を採る前提が失われたということを,反対意見に与しない理由として述べている。

また,今井補足意見は,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可が別個の行政処分であることは,原審が確定した事実であるということ,本件各付属街路事業認可の違法性は本件鉄道事業認可の違法性の主張の中で考慮できないわけではないこと,本件各付属街路事業認可には,それ固有の瑕疵があり得ること,本件各付属街路事業認可の違法を本件鉄道事業認可の違法性として主張できないわけではないこと,を理由として,反対意見に与しないと述べている。
藤田補足意見が理論面からの抽象的なアプローチであるのに対し,今井補足意見は訴訟運営という実務面からのアプローチといえるだろう。私としては,今井補足意見が,本件鉄道事業認可と本件各付属街路事業認可の間で,違法性の主張を相互に融通できるという点の理由が今ひとつ明らかでないこと(ここはなかなか説明しづらいところのように思える。)はあるにしても,穏当なところではないかという気がする。
▽▽▽▽▽

ただ,多数意見が本件鉄道事業認可の取消訴訟の原告適格を認めた一定範囲の近隣住民について,付属街路事業認可の取消訴訟の原告適格を認めなかった理由については,次のように説示されている。

「上告人らは,別紙上告人目録2及び3記載の各上告人らがそれぞれ別紙事業認可目録6及び7記載の各認可に係る事業の事業地内の不動産につき権利を有する旨をいうほかには,本件各付属街路事業に係る個々の事業の認可によって,自己のどのような権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるかについて,具体的な主張をしていない。そして,本件各付属街路事業に係る付属街路が,小田急小田原線の連続立体交差化に当たり,環境に配慮して日照への影響を軽減することを主たる目的として設置されるものであることに加え,これらの付属街路の規模等に照らせば,本件各付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない上告人らについて,本件各付属街路事業が実施されることにより健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認めることはできない。」
※※※※※

この文章は,そのまま裏返して受け取ると,本件各付属街路事業による権利・利益の侵害について具体的な主張をすれば,原告適格を認めるという趣旨である。すなわち,多数意見といえども,付属街路の周辺住民について,一律に本件各付属街路事業認可の取消訴訟の原告適格を否定したわけではないことが明らかである。
極論すれば,多数意見と反対意見の差は,権利・利益の侵害について「具体的な主張」をする必要があると考えるか(多数意見),その必要はないと考えるか(反対意見)という点にあるに過ぎない。
勿論,多数意見に従えば,本件各付属街路事業認可は,それぞれの付属街路の周辺住民が個別に争うことが原則になるだろうし,反対意見に従えば,本件鉄道事業認可がある限り,本件鉄道事業認可を争うことのできる広い範囲の住民に原告適格が認められるという違いはある。
しかし,原告らが,一体化論にこだわるのではなく,本件各付属街路事業が周辺住民に及ぼす影響(健康又は生活環境に係る著しい被害)について,もう少し丁寧な主張をしていれば,多数意見は違っていたかもしれないのである。そう考えると,多数意見と反対意見の違いは,それほど大きなものではなく,実質的には紙一重というところなのかもしれない。











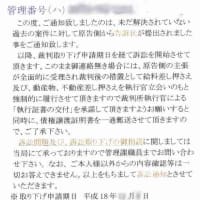
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます