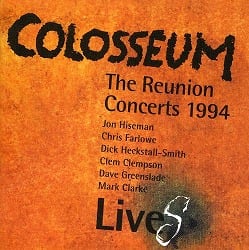NOVALIS 「SOMMER ABENT」(1976)
by Mr.Rapport
プログレ界では過小評価され過ぎのバンドがあまりにも多い。
ドイツのノヴァリスもその一つ。
ノヴァリスはどのアルバムもよく出来ているのだが、みんブロの皆さんにお勧めするとしたら本作。
ギターとキーボードを主軸としたキャッチーなメロディがとにかくいい。
本アルバムは全三曲からなり、一曲目のギターが奏でるメロディなんか、まるでレインボーのインストナンバーを聴いているかのよう。
二曲目はユーライア・ヒープの『7月の朝』と構成・展開まで似ていて、双璧をなす出来といっても過言ではないだろう。
三曲目(LPでいうB面)は組曲形式になっているのだが、これがまた◎。ゆったりとしたテンモネがらも、聴かせるところはちゃんと聴かせてくれ、バックのキーボードがこれまたレインボーの『虹をつかもう』(スタジオ盤)を彷彿させてくれる。
管理人さんが「ロング・リブ~」のファイルNo.766で、「高校時代、ロックを聴く数少ない同級生の中でも、ハードロック派とプログレ派に分かれていた」と記されていた。
自分も例外ではなく、典型的な前者。しかし、その垣根を取っ払ってくれたのがこのアルバムであることを鑑みると、感謝しないではいられないのである。
例によって、YOU TUBEを貼り付けておきました。
レインボーが好きな方にお勧めの一枚です。
http://www.youtube.com/watch?v=Li7wJSpETpE

by Mr.Rapport
プログレ界では過小評価され過ぎのバンドがあまりにも多い。
ドイツのノヴァリスもその一つ。
ノヴァリスはどのアルバムもよく出来ているのだが、みんブロの皆さんにお勧めするとしたら本作。
ギターとキーボードを主軸としたキャッチーなメロディがとにかくいい。
本アルバムは全三曲からなり、一曲目のギターが奏でるメロディなんか、まるでレインボーのインストナンバーを聴いているかのよう。
二曲目はユーライア・ヒープの『7月の朝』と構成・展開まで似ていて、双璧をなす出来といっても過言ではないだろう。
三曲目(LPでいうB面)は組曲形式になっているのだが、これがまた◎。ゆったりとしたテンモネがらも、聴かせるところはちゃんと聴かせてくれ、バックのキーボードがこれまたレインボーの『虹をつかもう』(スタジオ盤)を彷彿させてくれる。
管理人さんが「ロング・リブ~」のファイルNo.766で、「高校時代、ロックを聴く数少ない同級生の中でも、ハードロック派とプログレ派に分かれていた」と記されていた。
自分も例外ではなく、典型的な前者。しかし、その垣根を取っ払ってくれたのがこのアルバムであることを鑑みると、感謝しないではいられないのである。
例によって、YOU TUBEを貼り付けておきました。
レインボーが好きな方にお勧めの一枚です。
http://www.youtube.com/watch?v=Li7wJSpETpE