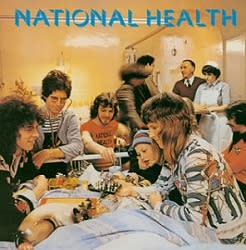Robert John Godfrey 「HALL OF HYPERION」(1973)
by Mr.Rapport
ロックとクラシック(オーケストラ)を融合させた俗にいうクラシカル・ロックは「当たりはずれ」がつきものである。
当たりの典型がニュー・トロルスの「コンチェルト・グロッソ」だとしたら、はずれの典型がジョン・ロードの「ジェミニ組曲」といったところだろう。
いずれに共通するのは、ロックを主軸としてクラシックの要素をふんだんに取り入れていること。
しかし、中にはごく稀に、クラシックを主軸としてロックの要素をふんだんに取り入れたアーティストもいる。
それが今回紹介するRobert John Godfrey(ロバート・ジョン・ゴブトリー)のソロアルバム「HALL OF HYPERION」。
ロバート・ジョン・ゴブトリーとは、イギリスのシンフォニックロックバンド THE ENID(エニド)のリーダーでキーボート奏者。ある意味、ジョン・ロードやキース・エマーソンと並んでクラシカル・ロックの先駆者――草分け的存在といってもいいだろう。
このアルバムをどこで購入したかは失念したが、たぶん、雑誌『フールズ・メート』か何かのレビューを見て、新宿レコードか明大前のモダーン・ミュージックあたりだと思う。
まず、レコード針を落とした第一印象は、「これって前衛クラシックじゃないの?」という失望感がこみあげてくる。しかし、間もなくして「買わなきゃよかった」という感情がだんだんと薄れ、壮麗でダイナミックなサウンドに飲み込まれていく。
確かに基本はクラシック。ロバートのヴォーカルも力強さこそあるものの、ロックというよりもオペラに近い。
しかし、それが主軸であるがゆえに随所で顔を出すロック・エッセンス”が脳を心地よく刺激してくれる。
しかも、壮大なオーケストラの正体がなんと、シンセサイザーとメロトロン群とくれば、ある意味、初期クリムゾンの発展形とも解釈できなくもない。
好みが完全に分かれそうで、この手の音がダメな人からすれば試聴に値しないかもしれないが、一応、YOU-TUBE 貼り付けておきます。
ロックバーで、大音量で聴くというよりも、その昔、中野駅北口にあったクラシック喫茶「クラシック」のような場所で、日曜日の昼下がりにでも聴きたい一枚。

https://www.youtube.com/watch?v=pSp8nJ21KyU
by Mr.Rapport
ロックとクラシック(オーケストラ)を融合させた俗にいうクラシカル・ロックは「当たりはずれ」がつきものである。
当たりの典型がニュー・トロルスの「コンチェルト・グロッソ」だとしたら、はずれの典型がジョン・ロードの「ジェミニ組曲」といったところだろう。
いずれに共通するのは、ロックを主軸としてクラシックの要素をふんだんに取り入れていること。
しかし、中にはごく稀に、クラシックを主軸としてロックの要素をふんだんに取り入れたアーティストもいる。
それが今回紹介するRobert John Godfrey(ロバート・ジョン・ゴブトリー)のソロアルバム「HALL OF HYPERION」。
ロバート・ジョン・ゴブトリーとは、イギリスのシンフォニックロックバンド THE ENID(エニド)のリーダーでキーボート奏者。ある意味、ジョン・ロードやキース・エマーソンと並んでクラシカル・ロックの先駆者――草分け的存在といってもいいだろう。
このアルバムをどこで購入したかは失念したが、たぶん、雑誌『フールズ・メート』か何かのレビューを見て、新宿レコードか明大前のモダーン・ミュージックあたりだと思う。
まず、レコード針を落とした第一印象は、「これって前衛クラシックじゃないの?」という失望感がこみあげてくる。しかし、間もなくして「買わなきゃよかった」という感情がだんだんと薄れ、壮麗でダイナミックなサウンドに飲み込まれていく。
確かに基本はクラシック。ロバートのヴォーカルも力強さこそあるものの、ロックというよりもオペラに近い。
しかし、それが主軸であるがゆえに随所で顔を出すロック・エッセンス”が脳を心地よく刺激してくれる。
しかも、壮大なオーケストラの正体がなんと、シンセサイザーとメロトロン群とくれば、ある意味、初期クリムゾンの発展形とも解釈できなくもない。
好みが完全に分かれそうで、この手の音がダメな人からすれば試聴に値しないかもしれないが、一応、YOU-TUBE 貼り付けておきます。
ロックバーで、大音量で聴くというよりも、その昔、中野駅北口にあったクラシック喫茶「クラシック」のような場所で、日曜日の昼下がりにでも聴きたい一枚。

https://www.youtube.com/watch?v=pSp8nJ21KyU