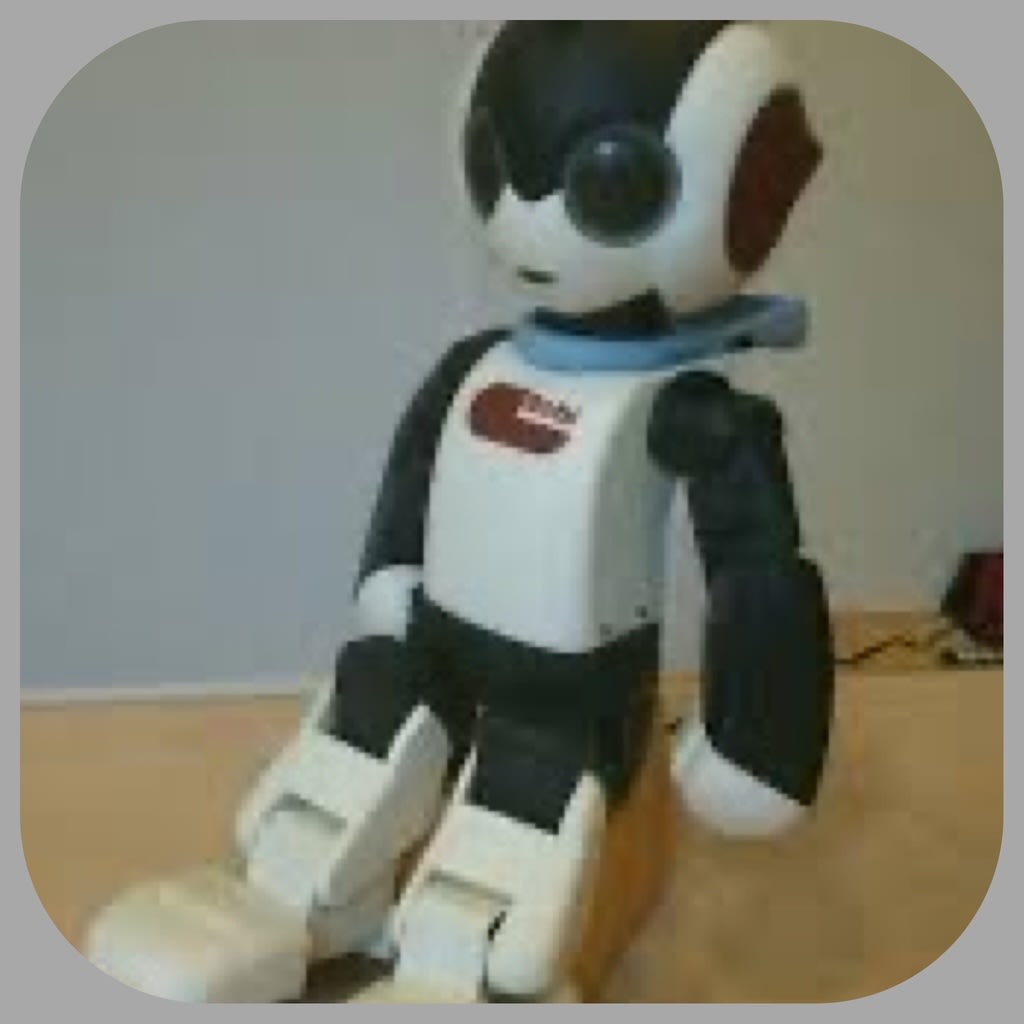教室に観葉植物の鉢植えを置いていました。
担任している一人の女子生徒が、終礼が終わると横に置いていたじょうろで水を汲みにいき、観葉植物に水やりをしてくれていました。
彼女は、私が頼んだのでもなく、誰かから言われたのでなく、自発的に毎日水やりをしてくれていました。
聞くと、「家でも鉢植えに水をやっているから。先生、ちょっとずつだけど大きくなっているよ」と言っていました。
わたしは、彼女に「ありがとう」とだけ言いました。
こういう場面に出くわすと、学校の先生はこのことをとりあげて、クラスの生徒に紹介したり、発表したり、ほめたりすることがあります。
しかし、ここはよく状況を見きわめなければなりません。
彼女は、自発的に始めたのです。植物が大きくなるのが楽しみだったのです。好きだからやっていたのです。
もし、クラスに紹介すれば、好きだからやっている自分の行為を、なぜクラス全員の前で話されなくてはいけないのか。ほめてもらうためにやっているのではない。
この行為を続けると、ほめてもらうためにやっていることと、まわりから受け取られてしまう。こう思うと、水やりをやめてしまうことになりかねません。
じっさい、思春期の子どもの心理は、このように感じやすく、傷つきやすいこともあるのです。
「いいことは、なんでも、ほかの生徒に知らせて知ってもらわないと」と、大人が勝手に判断して、情報を拡散していくのは、子どもの心に土足で脚を踏み入れていることになります。
このケースでは、大人は「ありがとう。きっと植物も喜んでいると思うよ」だけでいいのです。
子ども本人が自分のやる気で自発的に取り組むことに、ふつう「見返り」など求めません。
ほめてほしい、評価してほしいという気持ちは持っていないのです。ただ、そのやる気で、まわりの人が喜んでいることが、本人に伝われば十分なのです。
子どもの願い、つまり子どもがほんとうにしてほしいことが何であるかをわかっていることは、親にとって必要なことです。
ところで、昨今の社会状況・経済状況では、親が働き収入を得ることはさほど簡単なことではありません。
厳しい雇用情勢があり、仕事では成果を出すように求められ、ストレスがかかる職場の問題に直面する場合もあるでしょう。
家庭のことは気になるが、仕事にエネルギーを傾け、忙しい日々を送り、子どもから離れやすいのです。
それでも、収入を得るのは、わが子を幸せにするためという意識が働きます。
でも、あえて言えば、親は自分が「お父さん」「お母さん」の役割を果たせているかを、一度見つめなおしてもいいと思います。
子どもから見れば、お父さんやお母さんが何かを自分にしてくれるというのは、収入やお金でなく、いっしょにいてくれるとか、相談したいときに応じてくれるということなのです。
私は小学生のとき友だちと農業用水用のため池へ行き、池の樋をおもしろがって引っ張っていると樋が外れ、ものすごい勢いで用水路に水が流れ出しました。あまりの勢いで道路に水があふれ出しました。
直感的に「えらいことをしてしまった」と思いました。
翌日、学校では先生からこっぴどく怒られました。聞くと町内の池守りの人が水中に潜り、抜けた樋をはめてくれたそうです。
家に帰ったら父から叱られるだろうと思っていました。
でも父は「これから気をつけるんだ。いいな」とだけ言って、それ以上は何も言いませんでした。
私はものすごい威厳を感じました。そして、二度とやるまいと心に誓いました。
人によっては、怒らないのはよくないという考え方もあるでしょう。怒ったほうがいい場合もあります。
でも、その時は、父は怒らなかったのです。
私は反省して十分後悔もしていました。それがわかっていたので怒らなかったのでしょう。
そのような判断は、子どもをよく見ている、子どものことをよく知っているからてきるのです。
最近は、夫が育児休暇をとることも少し増えました。
赤ちゃんがワーと泣いています。お父さんがなんでだろうと、戸惑っていると、お母さんはおむつが濡れていると思い、とり替えました。
すると赤ちゃんが泣き止みました。
「ね、泣き止んだでしょ。おむつが濡れていたのよ」
「そうか、そういうものなんだ」
このように、子育ては、お父さんとお母さんが話し合って、会話をしながらやると楽しくなるのです」
「ほら、笑ったね」といっしょに喜ぶ。
このようにして、親は子どもと同じ時間を過ごし、子どものことがわかるようになるのです。
このことは、子どもが思春期になっても、同じです。
忙しくても、相談したいときには応じてくれる。
日々子どものことをよく見ていて、子どものことを知っている親を、子どもは求めているということです。
2000年のシドニーオリンピック女子マラソンで、高橋尚子選手は2時間23分14秒のオリンピック新記録で、金メダルをとりました。
そんな高橋選手を支えたのが、高校時代の中澤正仁陸上部監督から送られた冒頭の言葉でした。
シドニーオリンピック金メダルを手にした高橋選手は、その後も連覇を目指し練習を重ねました。
人は、苦しいときに踏ん張るからこそ、根が伸びるのです。
個性を尊重することが大事だと、多くの親が考えます。
子どもには、個性的に生きてほしいと、願う親や教師も多くいます。
では、子どもが個性的に生きるとはどういうことでしょうか。
スマホを手にもって、ツイッターに投稿する。すると知り合いや読んでいるフォロアーからのメッセージや投稿が届く。
こんなことが、当たり前になり、人間にとって正しいこと、便利なことだと思う。
そんな便利なツールを多く知っていたり、持っていたりするほど、人間関係がうまくいく。
このように考えるようになりました。
しかし、個性というものはそのやりとりにはないのです。
そのようにわかっていることだけをやっているのでは、自分らしさは何も生かされません。
ぜったい確実なことだけをするというのは、わかっていることだけにすがって生活するということで、そこに個性は存在しないのです。
私が校長をしていた時、「ぼくはロボットを研究する」と言って、家でもロボットを作っている中学生がいました。
その子は、高校でもロボットを研究すると、国立高専を志願して、合格して三中を卒業していきました。
このとき、「ぼくはこれに賭けてみる」という意思は「ぼく」にしかできないことです。
その賭け方が「個性」なのだと思います。
それでなにか成果が出てくるときもあるし、出にくいこともあるかもしれない。
その意味では、個性的に生きるということは、ひとつの大事業です。人生の醍醐味はなにかに賭けるということです。
こう考えると、子どもの個性を認めるということは、たいへんなことです。
その中学生の親御さんもわが子の進路をよく決心されたことだと思います。
わが子にとってよかれと思い、あらかじめ答えがわかっているような、安全パイのような確実な進路だけを歩ませようとすることが多いです。
でもそれは、一度しかない子どもの人生を、誰にでも当てはまる最大公約数のなかに入れようとしているとも言えます。
「個性を大切にする」ということは、いい響きをもちますが、その言葉がまことしやかに言われる割には、子どもの個性をみようとしていないのです。
また、個性は数字にかえることができないたいう点もおさえておきたいことです。
中学校での学習で、これが得意だというのは、テストでの数字に表されるので、ある意味わかりやすいのです。
だが、「うちの子は人に優しい」というのは、数字で表すことができないことなので、そのように自信をもって言える親はわが子のことをほんとうに理解しているのです。
子どものほんとうの姿を正しく評価できれば、これほど強い親子関係はないと言えるのでないでしょうか。自分の子どもを誇れるからです。
どの子にもみんな、誇れるところがあると、私は思います。
中学生はときとして友だち関係でトラブルにあい、悩みます。
そのとき、教師はその悩む生徒と面談します。
その生徒は3年生の女子生徒でした。
そして、ひとしきり話をして、帰りぎわにこう言って帰っていきました。
「先生、話をいろいろ聴いてくれて、ありがとうございました」。
その子は、自分のつらい気持ちを聴いてもらい、「ありがとう」という気持ちになり、感謝の言葉を出したのです。
教師はカウンセラーとちがい指導する役割もあります。だから、生徒の話しや思いを傾聴しながら、「こうしたら」とかのアドバイスをしているはずです。
したがって、語った内容よりも聴いた行為が教育的な効果なのだと考えます。
聴くことは英語でhearでなくlistenです。つまり、「聴く」は注意を払い一生懸命きく、いいかえれば能動性をもって、積極的にきこうとすることです。
そもそも、聴くという文字は、書いて字のごとく、相手に「耳」と「目」と「心」を傾けてきくことです。
さらに、生徒が話すことに、「そうだったのか」「つらかったよなあ」「それはよかった」という言葉が重なってくると、生徒とモードというか波長が同じになってきます。
このとき生徒の中には「わかってくれている」とか「受けとめてくれている」という安心感が生まれてきます。
そして対話をする中で、生徒はまとまりのつかない、モヤモヤした気持ちや考えが整理されてくることもあります。また、あらたな気づきが生まれることもあります。
気持ちの活力が戻り、勇気が出てくる場合が多いのです。
教師の指導が生徒に伝わるか、伝わらないかは、その生徒との関係に大きく影響されます。
だからこそ、生徒と教師の間の日頃からの信頼関係がたいへん重要になるのです。
(この点で、親御さんとお子さんは日頃からの関係があるのだから、「能動的に聴く」ことが十分にできやすいと思われます。)
さて、その「能動性をもって聴く」ときには、生徒自身が語る個人的な事実(かりにそれが間違ったとらえかたであったり、思い込みであったとしても)に基づくことがポイントです。
その個人的な事実にはかならず感情がついています。
具体的に言いましょう。
あるひとりの生徒が近づいてきて、先生に言いました。
「先生、来週から、わたし入院します。手術を受けないといけないから」
このとき、先生は一瞬のうちに生徒の心を読んで、
「そうか。手術で入院か。手術するとなると心配だね。不安やね。先生も心配だ」
という本人の不安な気持ちにジャストミートする言葉をかけることができるかどうかです。
ところが、この生徒の不安な心情にそぐわないような
「それは、たいへんだ。授業を休まないといけないな」
と、いきなりそんな言葉を発すると、生徒は「ええ! そこ?」となり、わかってくれてないとなるのです。
人は理屈ではなく、感情で動くことが多いのです。子どもの感情に寄り添うことから、「わかってくれている」となり、「また相談しよう」と次につながるのだと思います。
芥川龍之介は、数々の名作を残しています。
その彼の言葉に次のようなものがあります。
自由は 山巓(さんてん)の空気に似ている。
弱い者には耐えることができない。
山巓にいたると、空気がひじょうに薄く、体力が乏しければ耐えられません。
それと同じように、「自由」はかならずしも楽なものではありません。多くの中学生が自由を求めます。「自由にしたい」と言ったり、思ったりします。
でも自由には責任が伴うのです。
そのことは、次の言葉でも、表されます。
ある教師が卒業していく生徒に贈った言葉です。
「今まで自由を求めてきたきみは、あすから自由のたいへんさを思い知るだろう」



今の社会には様々な問題がりますが、その中でも最も大きな問題は、人の価値を何かができることで決めようとすることだと思います。
「性的少数者は生産性がない」と、おととし月刊誌の中で持論を書いた国会議員がいました。
また、津久井やまゆり園では「重度障害者は生きていてもしかたがない」という主張をした犯人から何人もの人が命を奪われました。
また、最近の文部科学省の教育政策が、次代の社会に有能な人を育てるという目的を重要視しています。
これも、広い意味では児童生徒が「何かができる人」になるように求めていると考えられると思います。
人間の価値を、何かができること(=生産性)できめることは大きな誤りです。誰もが働くことができるのではありません。
障害者、高齢者、病気の人などに価値がないのではなく、さまざまで多様な人が暮らしていけるのが健全な社会です。
人は生きていること自体に価値があり、尊いのです。
子育てに関しても同じです。なにか子どもにできないことや課題があっても、その子が存在していることが尊く、「ありがたい」のです。
この考えに立った時、子どもが行ったことやしてくれたことに対して、大人は「ありがとう」ということは自然なことです。
私が以前の職場に中学生につねに「ありがとう」という同僚の先生がいました。
その先生を慕ってたくさんの生徒が集まってきたのを、今、思い出します。