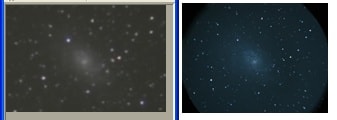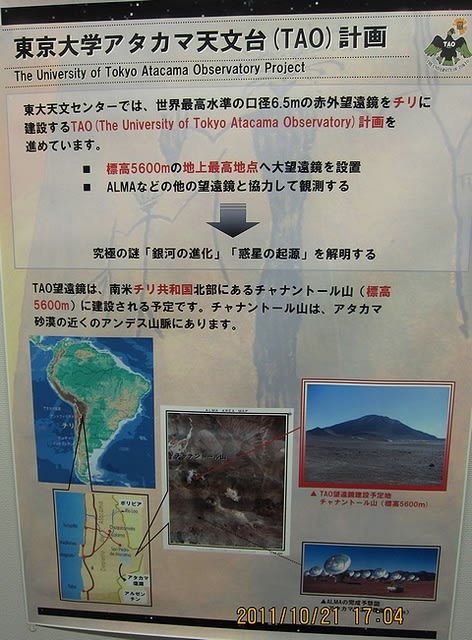さて、10月末の新月期は土日の雲り空の予報を避けて仕事後の
金曜日の夜に出撃したが、時間はどんどん過ぎていく。
M42の撮影に時間をとられてしまい、M42を取り終えた時点で、
既に2時半。あと2時間ほどしか時間が残っていない。
北の空には、再び北斗七星が昇ってきていた。↓
と言う事で、M42オリオン大星雲を撮った後は、バラ星雲に初挑戦
してみる。一旦望遠鏡をオリオン座のα星ベテルギウスに戻して
そこから、NGC2237バラ星雲を自動導入する。初めて写すので、
16秒で位置確認するが、今ひとつ中心が良く判らない。何となく
恒星が集まってる辺りが中心だろうかと、位置を微調整して64秒で
撮影したのが↓下の絵。

【↑NGC2237 バラ星雲】SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍
LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm 20コマ
撮影日:2011/10/29 02:47-03:30 撮影場所:静岡県駿東郡
Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング
・彩度・レベル・サイズ調整
視野一杯に、バラの花びらを映した様な赤い星雲が写った。
中心辺りに見える散開星団NGC2244が、まるでおしべの様に輝き、
その周りに、幾重にも折り重なる赤いはなびらの様な星雲。
なかなか美しい姿である。(但しバラの花でおしべの見えている
物は少ないが、、)処理後の画像は、元の写りのせいか、画像処理の
せいか、多少花びら部分に黒い部分が目立つのは、まあ、露光時間も
多くないので、仕方の無い所だろうか。
(北アメリカ星雲、馬頭星雲の時も似たような感じなのだが、、、)
【2011.11.3再処理画像追加↓】

再処理記事はこちら
撮影しながら、バックモニターを見る限りは、多少光害の光に
埋もれて、淡いながらも、その赤い花びらが大きく写っていて、
液晶上で見ていても、なかなか心躍る物がある。
さて、バラ星雲を映し終えた時点で3時半。急いでアイピースを
変更して、次なるターゲットへ。次のターゲットは、『光害地では
難しい銀河を写したい』の思いと、近くのNGC3628と合わせて、
『笑ったピエロの顔』の様子を見てみたいとの思いから、上り始めた
しし座の足もとのM65/M66を狙う。しし座のα星レグルスを基準星に入れ
導入目標は3天体の中心辺りを狙わないといけないので、『天体指定』
ではなく『赤径・赤緯』で入力できる様、撮影の間に3天体の位置から
導入目標の座標を計算して置いて、早速入力。ちょっとずれたが
概ね良い所に来たので、少しだけ微調整して撮影開始した。
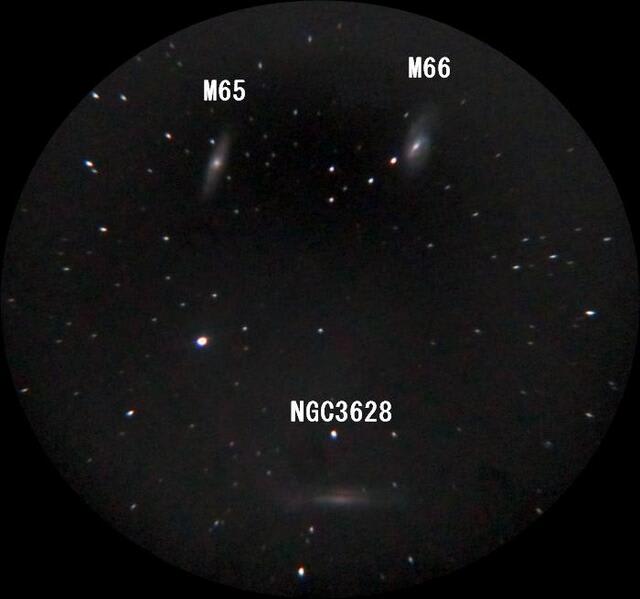
【↑M65/M66/NGC3628 しし座の渦巻き銀河】SM-R125S/D:130 f:720
UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm
7コマ 撮影日:2011/10/29 03:52-04:10 撮影場所:静岡県駿東郡
Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング
・レベル・サイズ調整
確かに、3つ合わせて、笑ったピエロの顔のように見える。微妙に
左右の目の開き具合が異なるのも愛嬌と言った感じか?
実は、この後もう一天体撮りたいと思っていたので、M65/66の撮影は
10枚に留めたので、その中から9枚のコンポジットで少し銀河が
薄れた感じになってしまったか。それにまだ東の低空で東京の光害の
影響も多くだいぶかぶりを受けてる感じだ。それと3天体を一画面に
収める為、画面の端の方を使ったので全体に写りも悪くなっている
感じである。
M65/66を10枚に押さえても、既に薄明は始まり掛けているか?
次なる目標は、しし座からおとめ座に移動している45P/本田・ムルコス
・パイドゥシャーコヴァー彗星だ。先日は、導入に手間取り、
32秒露出しかできなかったので、なんとか64秒露出で、その長い
尻尾を捕らえたいと思っているのだが、近日点を過ぎて1ヶ月も
経つので中々厳しいかも知れない。前の撮影が押してしまい、今回も
薄明の中か。おまけに今日は雲海が出来ていないから東京の街明かりの
影響で、東の低空はかなり条件が厳しい。結局64秒で4コマほど
撮影したが、画面上でどうにも尻尾が余り見えないので、諦めて露出を
40秒に変更して後10枚ほど撮影した。40秒の中から6コマをコンポジット
したのが↓下の絵

【↑45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星】
SM-R125S/D:130 f:720 UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200
F:2.0 f=4.9mm S:40秒 6コマ 撮影日:2011/10/29 04:31-04:43
撮影場所:静岡県駿東郡 Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正
・トリミング・レベル・サイズ調整
近日点を過ぎて丁度一ヶ月が過ぎた事もあり、今回は前回よりも、その
尻尾はかなり短くなってしまっている様だ。本体の光度もだいぶ下がって
いる感じだ。天ガの予報では先日撮影した日より2等級ほど光度が下がる
予測になっている。雲海が出来ていればもう少し良く写った可能性もあるが
残念ながら、今日の結果は、写りも尻尾も先日以下と言った感じか。
もうこの先太陽から遠くなるばかりだから、光度も尻尾も暗くなるばかり
だろうか。
45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星を撮り終えて、東の
空はだいぶ白み掛けてきた。もう、長秒露出をしても背景が明るくなる
ばかりなので、今日は、これにて撤収した。白み掛けた水平線が赤と青の
2色で塗り分けられ始めた空が美しい。↓

この後、朝焼けが始まり日の出を迎えるのだろうが、日の出を見る為に
低い排気音を響かせながら、中年2シーター軍団が10台位現れて
ミラージュの両サイドも含めて、駐車場の端に車を止めた事もあり
日の出を待たずに山を降りた。
時間は5時半を回り、帰りの富士五湖道路の温度計は2度を示していた。
やはりこれだと五合目は零下だっったかな。でも段々五合目の寒さ対策も
充実してきたのと、それ程風が無かったので、思ったほど寒くは感じ
なかったが。
本当は、このまま土曜の夜まで待ってみようかとも思ったが、当初
家内も行く筈だったので、一度帰るつもりで準備した事もあり、朝の
薬を持ってきていない事に気づき、諦めて帰途についた。
結局、その後GPV天気予報は好転しなかったので、土曜の再出撃は
取りやめたが、千葉ではそこそこ晴れたみたいだったから行けば
良かっただろうか、、、、
2011.10.28-29(11/1)
金曜日の夜に出撃したが、時間はどんどん過ぎていく。
M42の撮影に時間をとられてしまい、M42を取り終えた時点で、
既に2時半。あと2時間ほどしか時間が残っていない。
北の空には、再び北斗七星が昇ってきていた。↓

と言う事で、M42オリオン大星雲を撮った後は、バラ星雲に初挑戦
してみる。一旦望遠鏡をオリオン座のα星ベテルギウスに戻して
そこから、NGC2237バラ星雲を自動導入する。初めて写すので、
16秒で位置確認するが、今ひとつ中心が良く判らない。何となく
恒星が集まってる辺りが中心だろうかと、位置を微調整して64秒で
撮影したのが↓下の絵。

【↑NGC2237 バラ星雲】SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍
LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm 20コマ
撮影日:2011/10/29 02:47-03:30 撮影場所:静岡県駿東郡
Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング
・彩度・レベル・サイズ調整
視野一杯に、バラの花びらを映した様な赤い星雲が写った。
中心辺りに見える散開星団NGC2244が、まるでおしべの様に輝き、
その周りに、幾重にも折り重なる赤いはなびらの様な星雲。
なかなか美しい姿である。(但しバラの花でおしべの見えている
物は少ないが、、)処理後の画像は、元の写りのせいか、画像処理の
せいか、多少花びら部分に黒い部分が目立つのは、まあ、露光時間も
多くないので、仕方の無い所だろうか。
(北アメリカ星雲、馬頭星雲の時も似たような感じなのだが、、、)
【2011.11.3再処理画像追加↓】

再処理記事はこちら
撮影しながら、バックモニターを見る限りは、多少光害の光に
埋もれて、淡いながらも、その赤い花びらが大きく写っていて、
液晶上で見ていても、なかなか心躍る物がある。
さて、バラ星雲を映し終えた時点で3時半。急いでアイピースを
変更して、次なるターゲットへ。次のターゲットは、『光害地では
難しい銀河を写したい』の思いと、近くのNGC3628と合わせて、
『笑ったピエロの顔』の様子を見てみたいとの思いから、上り始めた
しし座の足もとのM65/M66を狙う。しし座のα星レグルスを基準星に入れ
導入目標は3天体の中心辺りを狙わないといけないので、『天体指定』
ではなく『赤径・赤緯』で入力できる様、撮影の間に3天体の位置から
導入目標の座標を計算して置いて、早速入力。ちょっとずれたが
概ね良い所に来たので、少しだけ微調整して撮影開始した。
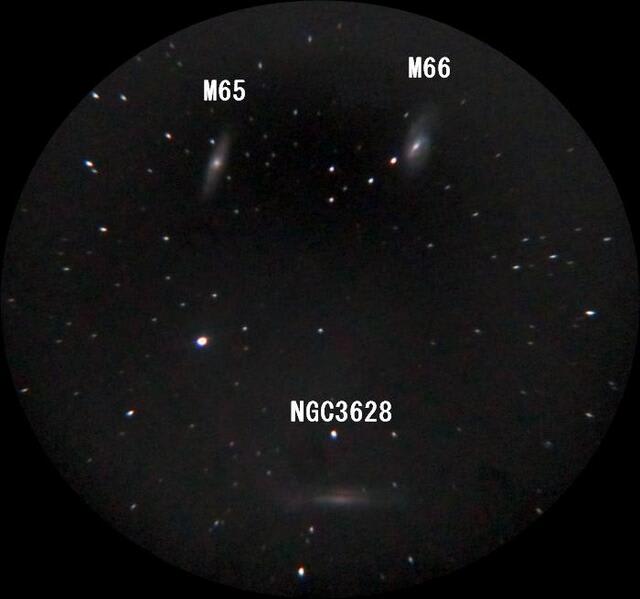
【↑M65/M66/NGC3628 しし座の渦巻き銀河】SM-R125S/D:130 f:720
UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm
7コマ 撮影日:2011/10/29 03:52-04:10 撮影場所:静岡県駿東郡
Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング
・レベル・サイズ調整
確かに、3つ合わせて、笑ったピエロの顔のように見える。微妙に
左右の目の開き具合が異なるのも愛嬌と言った感じか?
実は、この後もう一天体撮りたいと思っていたので、M65/66の撮影は
10枚に留めたので、その中から9枚のコンポジットで少し銀河が
薄れた感じになってしまったか。それにまだ東の低空で東京の光害の
影響も多くだいぶかぶりを受けてる感じだ。それと3天体を一画面に
収める為、画面の端の方を使ったので全体に写りも悪くなっている
感じである。
M65/66を10枚に押さえても、既に薄明は始まり掛けているか?
次なる目標は、しし座からおとめ座に移動している45P/本田・ムルコス
・パイドゥシャーコヴァー彗星だ。先日は、導入に手間取り、
32秒露出しかできなかったので、なんとか64秒露出で、その長い
尻尾を捕らえたいと思っているのだが、近日点を過ぎて1ヶ月も
経つので中々厳しいかも知れない。前の撮影が押してしまい、今回も
薄明の中か。おまけに今日は雲海が出来ていないから東京の街明かりの
影響で、東の低空はかなり条件が厳しい。結局64秒で4コマほど
撮影したが、画面上でどうにも尻尾が余り見えないので、諦めて露出を
40秒に変更して後10枚ほど撮影した。40秒の中から6コマをコンポジット
したのが↓下の絵

【↑45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星】
SM-R125S/D:130 f:720 UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200
F:2.0 f=4.9mm S:40秒 6コマ 撮影日:2011/10/29 04:31-04:43
撮影場所:静岡県駿東郡 Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正
・トリミング・レベル・サイズ調整
近日点を過ぎて丁度一ヶ月が過ぎた事もあり、今回は前回よりも、その
尻尾はかなり短くなってしまっている様だ。本体の光度もだいぶ下がって
いる感じだ。天ガの予報では先日撮影した日より2等級ほど光度が下がる
予測になっている。雲海が出来ていればもう少し良く写った可能性もあるが
残念ながら、今日の結果は、写りも尻尾も先日以下と言った感じか。
もうこの先太陽から遠くなるばかりだから、光度も尻尾も暗くなるばかり
だろうか。
45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星を撮り終えて、東の
空はだいぶ白み掛けてきた。もう、長秒露出をしても背景が明るくなる
ばかりなので、今日は、これにて撤収した。白み掛けた水平線が赤と青の
2色で塗り分けられ始めた空が美しい。↓

この後、朝焼けが始まり日の出を迎えるのだろうが、日の出を見る為に
低い排気音を響かせながら、中年2シーター軍団が10台位現れて
ミラージュの両サイドも含めて、駐車場の端に車を止めた事もあり
日の出を待たずに山を降りた。
時間は5時半を回り、帰りの富士五湖道路の温度計は2度を示していた。
やはりこれだと五合目は零下だっったかな。でも段々五合目の寒さ対策も
充実してきたのと、それ程風が無かったので、思ったほど寒くは感じ
なかったが。
本当は、このまま土曜の夜まで待ってみようかとも思ったが、当初
家内も行く筈だったので、一度帰るつもりで準備した事もあり、朝の
薬を持ってきていない事に気づき、諦めて帰途についた。
結局、その後GPV天気予報は好転しなかったので、土曜の再出撃は
取りやめたが、千葉ではそこそこ晴れたみたいだったから行けば
良かっただろうか、、、、
2011.10.28-29(11/1)