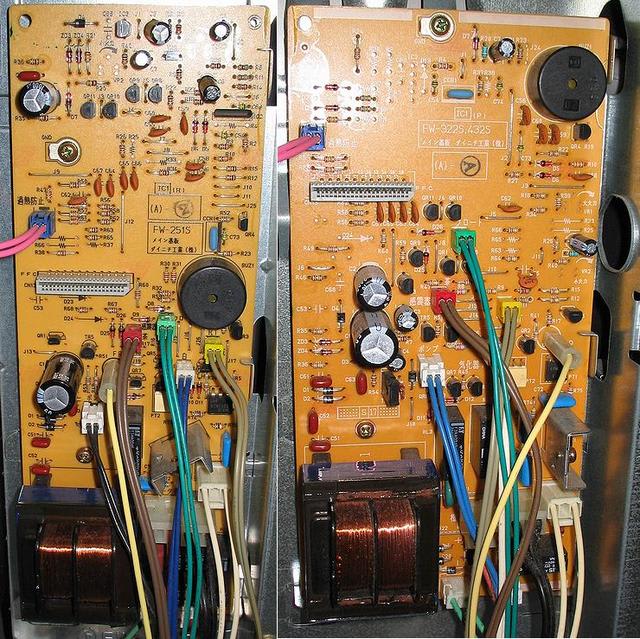どうも余り見え味の良くないTL-750。スコープタウンさんのHPを
見るとSTL-750の自主回収情報が出ていた。これによると、
STL仕様にするに当たって、遮光環を32mm→46mm化と取付位置の
変更を指示したが、間違って従来部品で変更位置に取付、有効径が
使えていないと言う物。うちのTL-750のを覗くと、どう見ても
30mm前後の小さい穴の遮光環が先端から10~15cmの所に付いて
いる!これか!!このせいで有効径が絞られて良く見えないのか!

f=500mm口径70mmに対して、遮光環が32mm、先端から15cmと
しても、単純に計算すると46mm位しか使えない事になる。
これじゃ、見えないはずだ。
既に↓この角度で接眼部側が遮光環で隠れて見えない。

HPでTL-750を買って良く見えると書かれている人のブログに
おじゃまして、色々と情報を貰うと、やはり46mmの遮光環が
11cm位の所?に付いているとの事。私の話を聞いてレンズを
確認すると、まだ少し口径食を起こしてるとの事で、その方は
先端から15cmまで遮光環を移動して、口径食を無くしたとの
情報を頂いた。
これはもうやってみるしかない。
さっそくフードを外し、ネジ3本を外して、レンズセルを
力ずくで外す。ホントはこれで遮光環に手が届くのだが、
レンズが汚れているので、セルを流しに持って行って水洗い。
軽く中性洗剤(ファミリーフレッシュ)を付けて油分も
落とす。いつもは眼鏡はこれで洗っているんだが、望遠鏡は
これで良いのかな??

水を綺麗に切って、こすらない様に軽くティッシュを押し
当てて水滴を取る。う~ん、なんだか変だぞ?表面は綺麗
なのに、レンズが曇っている。良く見ると、何やらレンズに
水が浸み込んでいる様な、、、そうか!対物レンズは確か
組みレンズって聞いたことが有るぞ!ヤバーイ!!
間に水が入ったんだ!!
しょうがないので、セルの前端部を回して対物レンズを外す。
お、なんかまずいぞ!今度はレンズがバラけそう。
対物レンズは2枚のレンズと、樹脂製のワッカのスペーサで
構成されていた。

取りあえず組み合わせが判る様に横にマジックで合わせマーク
を付けて置いた。もう一度レンズを流しに持って行って、一枚
づつ洗い直す。
いざ組み立て様とすると、レンズ同士の組み合わせ方向は
判るが、どっちが天体側で、どっちが接眼側かの印がない。
参ったな、、、何しろ望遠鏡は初心者くっしー。いつもの
ジャンクや修理の電気製品のつもりで始めたが、望遠鏡の
知識が全然ないから、段々深みにはまりつつある、、、

さて、困った。しょうがないので、ミザールさんに電話して
レンズの向きを教えて貰った。ついでに遮光環の話をしたら
46mmの遮光環も部品として分けて頂けるとの事でお願いした。
ちなみに、水洗いしないで、カメラ屋さんで売ってるレンズ
クリーニングキットのアルコールとレンズペーパで掃除して
下さいとの事だった(汗)
そんな訳で教えて貰った方向にレンズをセルに組み付ける。
でもっていよいよ遮光環。部品を分けて貰う事にはしたが
届くまで待ちきれないので、今付いてる奴を先ずは削って
46mmにして試す事にした。ちなみに、オリジナル状態では
何と30mm径の遮光環が、レンズから11.5cmの所に付いて
いる!


これだと単純計算では39mmしか使えない!!!
何とも、ひどい仕様の様な気がする。これじゃ6cmより
見えない訳だ。
早速、先の曲がった鉄棒で引っかけて遮光環を取り外し
電気ドリルの先に砥石を付けて削って穴を広げる。
何とか46mm位に広げたが、だいぶ砥石が滑って、遮光環
の塗装が剥げたので、黒マジックで暫定補修して取り付
ける。

接眼部側から覗いて、先端から12cm位の所でレンズの端が
見えた。

何か計算より前なんだけどとちょっと気になったが
余り知識のないくっしーはスルーしてどんどん組み立て。
組み上がって、夜になり、期待しながら空を覗く。
が、しかし、確かに少し明るくなった気がするけど、
相変わらずコントラストの低い画像。木星の鮮明さも
余り改善していない。6cmと比べると、少し6cmより
明るい気がするが、木星自体のコントラストも解像度も
6cmの方がまだ良く見える感じで、がっかり。
コントラストは、ドローチューブ内の迷光処理しないと
駄目かな、、、それに対物レンズバラしたから、少し
光軸もずれたみたいだ。合掌の前後点でのぼやけが
丸くないし、、、調整しないと駄目なんだろうな、、
今回は、苦労した割に、効果的な改造になっていなくて
今ひとつの成果。相変わらず、良く見えないTL-750で
有った、、、ガッカリ。
望遠鏡ベテランの人が見たら怒りだしそうな記事に
なってしまったか、、、、ベテランの方、初心者の
くっしーに色々アドバイスを、、、、
見るとSTL-750の自主回収情報が出ていた。これによると、
STL仕様にするに当たって、遮光環を32mm→46mm化と取付位置の
変更を指示したが、間違って従来部品で変更位置に取付、有効径が
使えていないと言う物。うちのTL-750のを覗くと、どう見ても
30mm前後の小さい穴の遮光環が先端から10~15cmの所に付いて
いる!これか!!このせいで有効径が絞られて良く見えないのか!

f=500mm口径70mmに対して、遮光環が32mm、先端から15cmと
しても、単純に計算すると46mm位しか使えない事になる。
これじゃ、見えないはずだ。
既に↓この角度で接眼部側が遮光環で隠れて見えない。

HPでTL-750を買って良く見えると書かれている人のブログに
おじゃまして、色々と情報を貰うと、やはり46mmの遮光環が
11cm位の所?に付いているとの事。私の話を聞いてレンズを
確認すると、まだ少し口径食を起こしてるとの事で、その方は
先端から15cmまで遮光環を移動して、口径食を無くしたとの
情報を頂いた。
これはもうやってみるしかない。
さっそくフードを外し、ネジ3本を外して、レンズセルを
力ずくで外す。ホントはこれで遮光環に手が届くのだが、
レンズが汚れているので、セルを流しに持って行って水洗い。
軽く中性洗剤(ファミリーフレッシュ)を付けて油分も
落とす。いつもは眼鏡はこれで洗っているんだが、望遠鏡は
これで良いのかな??

水を綺麗に切って、こすらない様に軽くティッシュを押し
当てて水滴を取る。う~ん、なんだか変だぞ?表面は綺麗
なのに、レンズが曇っている。良く見ると、何やらレンズに
水が浸み込んでいる様な、、、そうか!対物レンズは確か
組みレンズって聞いたことが有るぞ!ヤバーイ!!
間に水が入ったんだ!!
しょうがないので、セルの前端部を回して対物レンズを外す。
お、なんかまずいぞ!今度はレンズがバラけそう。
対物レンズは2枚のレンズと、樹脂製のワッカのスペーサで
構成されていた。

取りあえず組み合わせが判る様に横にマジックで合わせマーク
を付けて置いた。もう一度レンズを流しに持って行って、一枚
づつ洗い直す。
いざ組み立て様とすると、レンズ同士の組み合わせ方向は
判るが、どっちが天体側で、どっちが接眼側かの印がない。
参ったな、、、何しろ望遠鏡は初心者くっしー。いつもの
ジャンクや修理の電気製品のつもりで始めたが、望遠鏡の
知識が全然ないから、段々深みにはまりつつある、、、

さて、困った。しょうがないので、ミザールさんに電話して
レンズの向きを教えて貰った。ついでに遮光環の話をしたら
46mmの遮光環も部品として分けて頂けるとの事でお願いした。
ちなみに、水洗いしないで、カメラ屋さんで売ってるレンズ
クリーニングキットのアルコールとレンズペーパで掃除して
下さいとの事だった(汗)
そんな訳で教えて貰った方向にレンズをセルに組み付ける。
でもっていよいよ遮光環。部品を分けて貰う事にはしたが
届くまで待ちきれないので、今付いてる奴を先ずは削って
46mmにして試す事にした。ちなみに、オリジナル状態では
何と30mm径の遮光環が、レンズから11.5cmの所に付いて
いる!


これだと単純計算では39mmしか使えない!!!
何とも、ひどい仕様の様な気がする。これじゃ6cmより
見えない訳だ。
早速、先の曲がった鉄棒で引っかけて遮光環を取り外し
電気ドリルの先に砥石を付けて削って穴を広げる。
何とか46mm位に広げたが、だいぶ砥石が滑って、遮光環
の塗装が剥げたので、黒マジックで暫定補修して取り付
ける。

接眼部側から覗いて、先端から12cm位の所でレンズの端が
見えた。

何か計算より前なんだけどとちょっと気になったが
余り知識のないくっしーはスルーしてどんどん組み立て。
組み上がって、夜になり、期待しながら空を覗く。
が、しかし、確かに少し明るくなった気がするけど、
相変わらずコントラストの低い画像。木星の鮮明さも
余り改善していない。6cmと比べると、少し6cmより
明るい気がするが、木星自体のコントラストも解像度も
6cmの方がまだ良く見える感じで、がっかり。
コントラストは、ドローチューブ内の迷光処理しないと
駄目かな、、、それに対物レンズバラしたから、少し
光軸もずれたみたいだ。合掌の前後点でのぼやけが
丸くないし、、、調整しないと駄目なんだろうな、、
今回は、苦労した割に、効果的な改造になっていなくて
今ひとつの成果。相変わらず、良く見えないTL-750で
有った、、、ガッカリ。
望遠鏡ベテランの人が見たら怒りだしそうな記事に
なってしまったか、、、、ベテランの方、初心者の
くっしーに色々アドバイスを、、、、