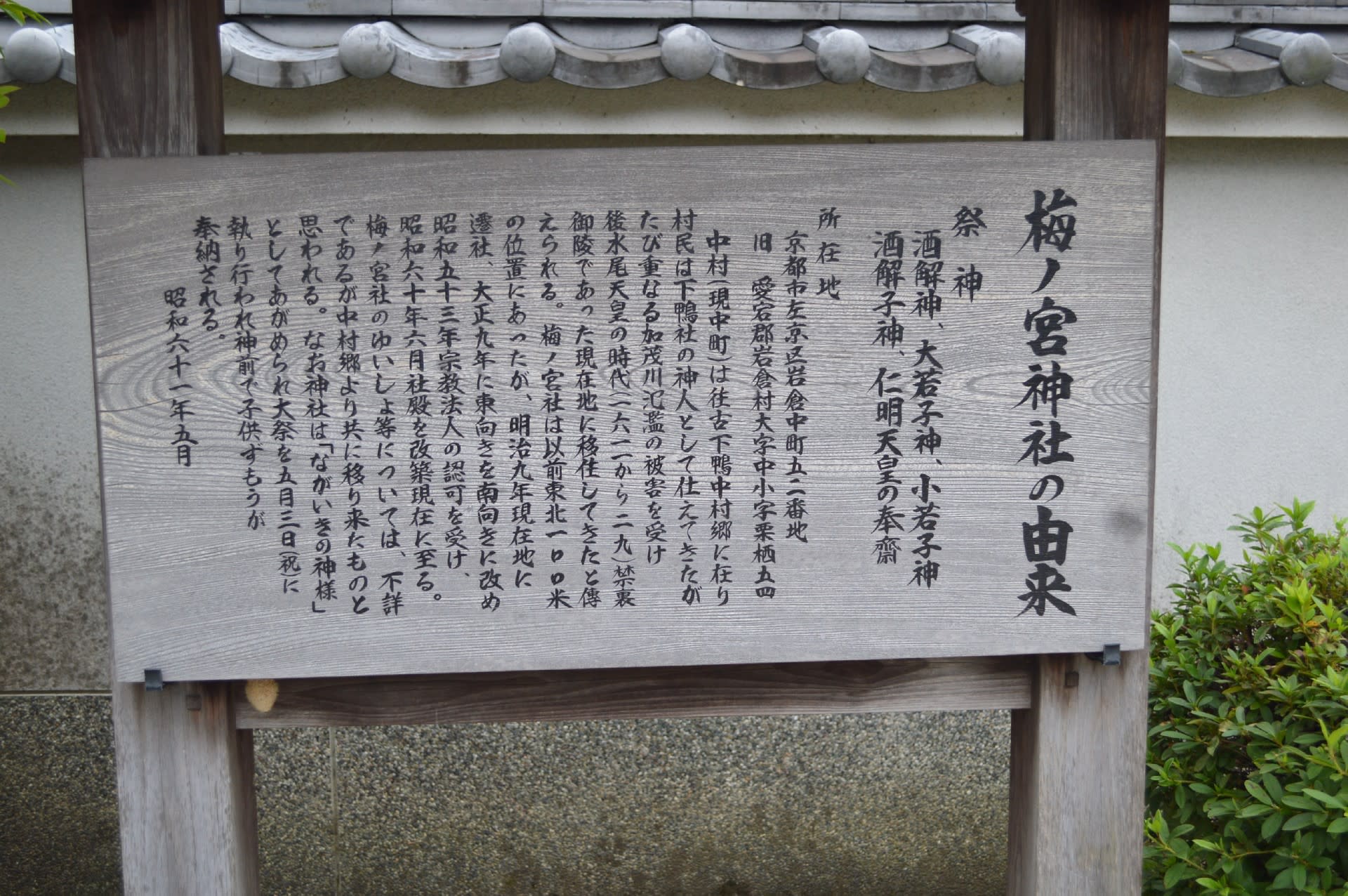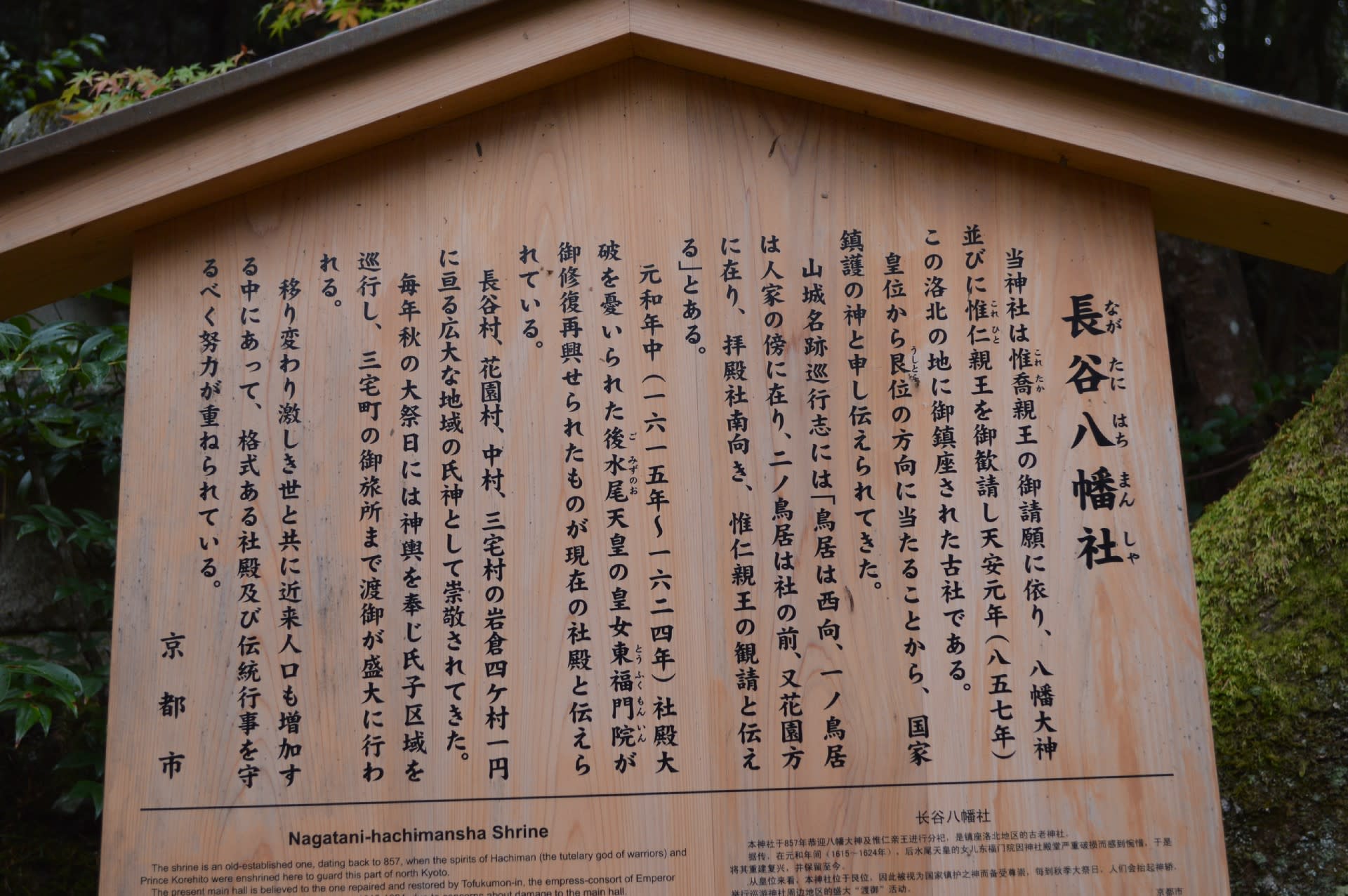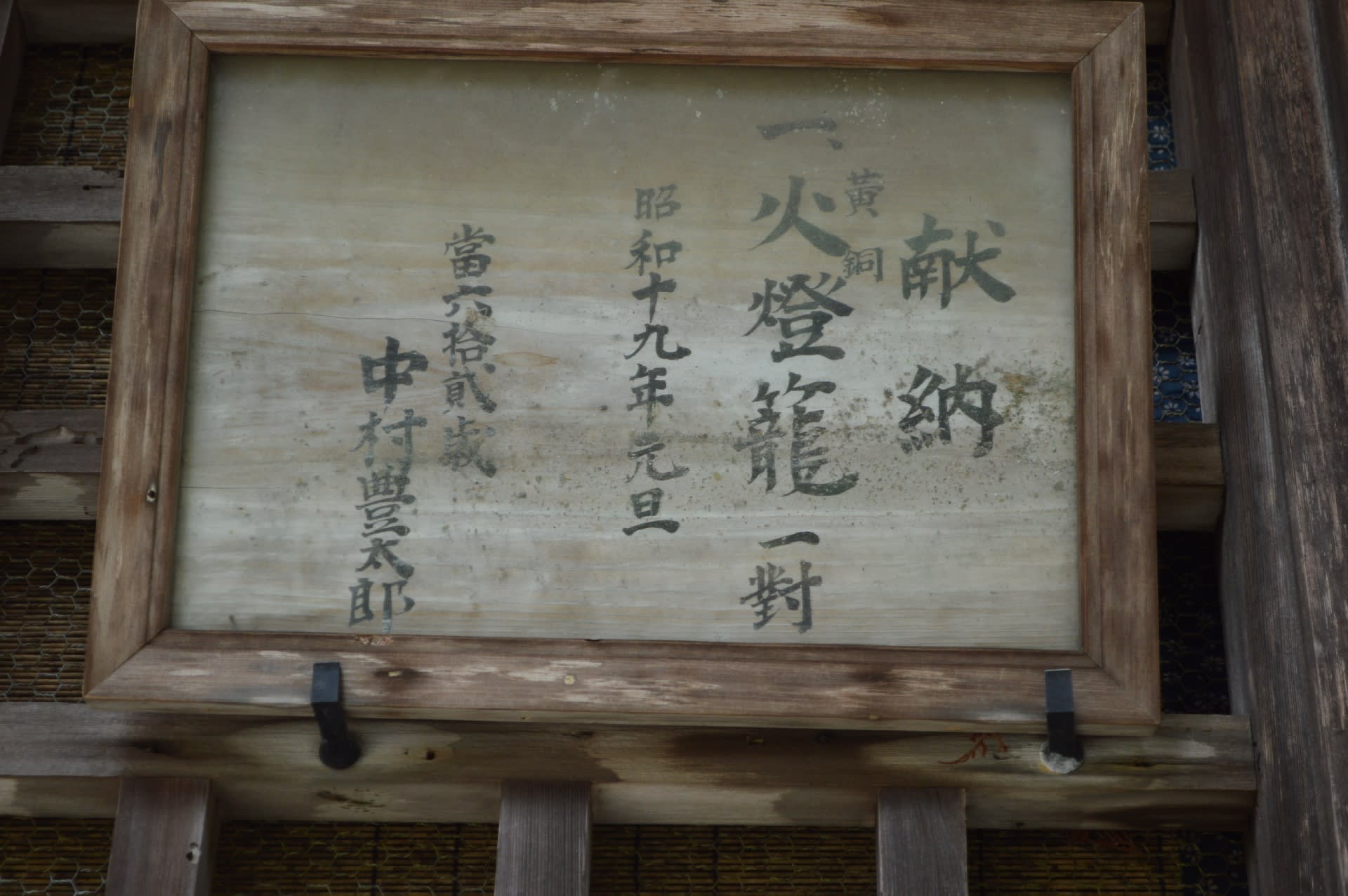久世神社西側の境内地にあたる。
以前からこの辺に布目瓦が散布し、古い寺院跡があることが伝わっていたが、昭和43年、測量が行われた結果、東西に並ぶ2ケ所の土壇があることが確認された。東は塔跡、西は金堂跡と推定され、講堂はこれより北に位置するものと思われたが、今のところ判明していない。
出土遺物は飛鳥様式の軒丸瓦や軒平瓦が多く、南門付近ではまた天平様式の見事な金銅仏(奈良時代)が出土した。寺域はほぼ1町(約108m)を占めるものとみられ、伽藍配置は平川廃寺とは逆に、いわゆる法起寺式であり、奈良時代前期に建立された寺院であることが判明した。寺名については明らかでなく「久世廃寺」と称している。
塔跡は、東西13.7m、南北13.4mの瓦積基壇と推定されています。
金堂跡は、東西26.7m、南北21.3mの瓦積基壇です。
講堂跡は東西23.5m、南北13mの瓦積基壇で、基壇上には7間(21m)×4間(10.5m)の四面庇をもつ建物があったことが確認されています。
南門跡は、南北4.3m、東西8m以上の基底部が確認されています。
南門跡北側の瓦溜まりからは、像高6.9m(頭頂~足裏)の金銅造の誕生釈迦仏立像が出土しています。
また東側の市道沿いでは、補修用瓦を焼いたと考えられる瓦窯跡が見つかっています。
発掘調査により、奈良時代前期に創建され、8世紀中ごろに建物が整備され、11世紀前半に廃絶したと考えられています。
寺域北東側の丘陵上には、6世紀に築造されたと考えられている芝ケ原1~7号墳(前方後円墳2基、円墳5基)があります。

久世神社
旧久世村の産土神で、日本尊命を祭神としている。創祀年代は明らかでない。本殿の建物が室町時代末期の建築であることから、それ以前の鎮座であると思われる。もとは若王社といったが、明治維新のときに今の名に改め。明治7年(1874)郷社に列せられた。









本殿 重要文化財
丹塗りの一間社流造、檜皮葺で、柱上部・組物・庇水引虹梁・庇蟇股などを極彩色に仕上げています。内部は内陣と外陣に分かれ、内陣上部には幣軸付板扉、外陣正面に引違の格子戸を4枚たてています。内陣正面の板扉には扉2枚にわたり大きな松を描き、左右の脇羽目板にも草花を描いています。
内陣正面の欄間中央に巴紋、左右に6弁の花紋を飾っています。
外陣正面には透彫り欄間をいれ、単純化した唐草文様を柱一間分にわたって彫刻した中に、中央に菊、左右に各2個ずつ計4個の桐を配しています。
建立年代は明らかでありませんが、室町時代中期とされています。




関連記事 ⇒ まとめ045 京都府の重要文化財・国宝 建物
神社 前回の記事 ⇒ 神社左0204 出世稲荷神社
下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます