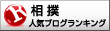バッタ目の、恐らく幼虫の抜け殻。
触角の長さ・太さから言って、キリギリス系ではなさそう。
フキバッタとかイナゴとか、そっちの系統でしょうね。
カマキリ類の抜け殻は結構見るけど、バッタのは滅多に見ないね。
脱皮しているところ、あるいはその直後を襲われたら、ひとたまりもないからね。
普通は、その痕跡すら見せないようにするだろうしね。
長い脚を、後ろにグッと突っ張らせたポーズが印象的ですね。
ここが最 . . . 本文を読む
ヒガシキリギリスの♂。
「ギーッ、チョン」とか「チョン、ギース」とか「チッ、ズリーッ」など、鳴き声について、色々な記述が見られます。
音に最も近いのは、「チッ、ズリーッ」かな?
何か「チェッ、ズルい!」っぽく聞こえますけどね。
実際、「チッ」って音は人間の舌打ちに似ていて、KONASUKEは撮影のため、舌打ちしながらキリギリスに近づきました。
効果の程は?ですけど(笑)
鳴き声は主に、「チッ」 . . . 本文を読む
今朝、今季初めてヒガシキリギリスが鳴いているのを確認しました。
真夏のイメージがありますが、この時期に鳴き出すようですね。
こないだナキイナゴを撮影した時は鳴いていなかったから、最近、鳴き出したのでしょう。
2016年にも、「7月の初めから狙ってた」旨の記事がありますので、例年、6月末~7月初頭から鳴き始めるんでしょうね。
これも時間をかければ撮影出来たと思いますが、中々、全てに時間をかけている . . . 本文を読む
ナキイナゴの♂。
翅と後脚を擦り合わせて鳴きます。
これは薮を突っついて追い出した個体なので、残念ながら鳴いてはくれませんでした。
辺りでは、♂たちが競って鳴いていました。
今年の課題の一つだったナキイナゴが撮れました。
音を頼りに探り当てたカップル。
覗き見感、満載ですね(笑)
♂は交尾中でも鳴いていました。
他の♂に対抗してるのかと思ったら、♀を呼ぶために鳴いている時(コーリング)と、交 . . . 本文を読む
ヤブキリの幼虫。
サクラのひこばえの上にいました。
この時期、花の上で見ることが多いですが。
ミズバショウの葉の上でも。
春にはそこら中で幼虫を見かけるのに、成虫はあまり見ないのは、単に数が減るというばかりではなさそう。
幼虫は草原にいるけど、成虫は樹上性なので、見つけるのが難しいのかもね。
こっちはミズバショウの花。
もう、花粉も出ないと思うんですけどね。
分類:バッタ目キリギリス科キリギ . . . 本文を読む
ウスグモスズのメスの幼虫。
鳴く虫の仲間でありながら、オスも鳴きません。
一体、どうやってオスとメスが出あうのでしょうか?
興味深いところです。
分類:バッタ目ヒバリモドキ科ヒバリモドキ亜科
体長:6~8mm
分布:本州(関東~鳥取)、九州
平地~丘陵
成虫の見られる時期:8~10月
卵で冬越し?
エサ:雑食性?
その他:体色は黄褐色~淡褐色で光沢はない。
頭は . . . 本文を読む
トノサマバッタ。
日本産のバッタ中、最大種。
胸の上は直線的。
前翅の黒斑は細かい。
後翅に黒色帯はない。
褐色型。
クルマバッタ。
胸の上は、アーチ状に盛り上がる。
前翅の黒斑はトノサマバッタより大きい。
後翅に輪状の黒色帯があり、基部は鮮やかな黄色紋。
褐色型はまれ。
クルマバッタモドキ褐色型。
胸に「X」字状の模様がある。
胸の上は直線的。
緑色型。
褐色型に比べてまれ。
トノサ . . . 本文を読む
ヤマトフキバッタのメス。
翅は短いですが、立派にオトナです。
分類:バッタ目バッタ科フキバッタ亜科
体長:♂22.3~26.6mm、♀27.4~33.9mm
分布:本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見られる時期:8~10月(年1化)
卵で冬越し
エサ:フキほか様々な植物
その他:成虫になっても翅は短いが、背面で重なる長さ。
通常、腹節4~6節に達する。
. . . 本文を読む
オンブバッタ。
草の生えた空き地とか、庭とか、割と人工的な環境にもいる昆虫の代表。
褐色の個体も良くみるんだけど。
こんな風に体の一部が黄色っぽいのは、あまり見た覚えがない。
そのうち、色んな体色のパターンを集めてみたいね。
分類:バッタ目オンブバッタ科オンブバッタ亜科
翅の端までの長さ:♂20~25mm、♀40~42mm
分布:全国
平地~山地
成虫の見られる時期:8~11月
. . . 本文を読む
シバスズの長翅型のメス。
2頭が歩きまわっていた。
特徴は、
①後脚腿節に目立った斑紋がないこと(マダラスズでは黒色帯が顕著)
②小アゴヒゲ先端は褐色(マダラスズは黒色、ヤチスズは褐色)
③後脚脛節の外側の刺は3本(マダラスズは3本、ヤチスズは4本)
③については、画像では4本っぽく見えるけど、向こう側にある刺が見えているだけのようです。
分類:バッタ目ヒバリモドキ科ヤチスズ亜科
. . . 本文を読む
複数のカネタタキのオスとメスが集まって、集団見合いのようになっています。
2018年にも同様の様子を観察しています。
→集団お見合い中?カネタタキ20181003・07
やはり、複数のオスとメスが集まって相手を探すことがあるようです。
オスが複数集まるメリットとして考えられるのは、一頭ずつでは小さい鳴き声を集めて大きくして、より確実にメスを集められるかも知れませんね。
メスは、その中から相手を . . . 本文を読む
クルマバッタモドキの緑色型。
褐色型に比べてまれ。
胸の背中は直線的。
クルマバッタでは、アーチ型に盛り上がる。
上から見たところ。
胸に「X」状の模様。
こっちは普通の褐色型。
もうかなり草臥れてるけどね。
分類:バッタ目バッタ科トノサマバッタ亜科
体長:オス32~45mm、メス55~65mm(翅端まで)
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:7~11月 . . . 本文を読む
エントモファーガ・グリリに侵されたオンブバッタ。
頭の尖ったバッタ類で、顔の横に白いイボの列があるのが、オンブバッタの特徴。
エントモファーガ・グリリは、バッタ類に寄生する菌類。
(エントモファ=虫、エントモファーガ=虫に寄生する菌)
バッタをコントロールして、出来るだけ高い所に誘導し、菌糸を効率的にばら撒くという。
怖ッ!
そういえば何年か前に、イネ科の植物の葉の上にショウリョウバッタが死 . . . 本文を読む
コバネイナゴの交尾。
上から。
分類:バッタ目バッタ科イナゴ亜科
体長:♂16~34mm
♀40mm
分布:北海道南部、本州、四国、九州、南西諸島
平地~低山地
成虫の見られる時期:7~12月
卵で冬越し
エサ:イネ科の植物の葉
その他:ハネナガイナゴに似るが、前翅が腹端に届かないことが多く、あまり飛ばない。
ただし長翅型が出現するので、ハネナガイナゴと . . . 本文を読む
クビキリギスの褐色型。
シブイロカヤキリかとも思いましたが。
口が朱色なので、クビキリギスですね。
シブイロカヤキリは褐色型のみが知られ、大あごが黒い。
分類:バッタ目キリギリス科クサキリ亜科
体長:35mm 翅端まで:50~57mm
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:3月中旬~(5月?)7月中旬、(8月?)晩秋~11月
※資料によってバ . . . 本文を読む