史料館新営20周年記念特別展
※土・日・祝日休館
(ただし、10月31日、11月7・8日は開館します。)
開館時間:9時30分~16時30分
場 所:滋賀大学経済学部附属史料館1階展示室
経済学部附属史料館では平成24年度以来、科学研究費助成事業「中・ 近世「菅浦文書」の総合的調査・公開と共同研究-中・近世村落像の再検討」の採択を受けて、当館に寄託されている菅浦文書の再調査を実施してまいりました。今年はその事業の最終年度にあたり、また史料館が独立棟として開館してから20年目にもなります。
そこで、これまでの調査と研究成果の公表を兼ねて、史料館新営20周年記念特別展「重要文化財菅浦文書を読み解く」を開催いたします。当館で菅浦文書を一般公開するのは平成17年以来であり、実に10年ぶりとなります。今回の展示では、「菅浦の生活空間と生業」「菅浦と浅井氏」「菅浦文書の花押・略押」「湖(うみ)と山の権利をめぐって」といったコーナーを設けて、中世菅浦の多彩な世界に迫ります。菅浦文書のうち21点を一挙に公開しますので、お見逃しなきよう、ぜひご観覧にお越し下さい。
 菅浦与大浦下荘堺絵図(菅浦文書722号) 長浜市西浅井町菅浦区寄託 |
 現在の菅浦(遠景) |
特別展関連講演会
10月31日(土)13時30分~ 於 経済学部第2校舎棟第21講義室
講演「中世菅浦の景観」 長浜市長浜城歴史博物館館長 太田浩司氏
シンポジウム「菅浦の歴史と史料を語る」 科研費研究グループ
共催:科研基盤研究B「中・近世「菅浦文書」の総合的調査・公開と共同研究」
課題番号(24320127)グループ
後援:長浜市長浜城歴史博物館・(公財)陵水学術後援会
 講演「中世菅浦の景観」…長浜市長浜城歴史博物館館長 太田浩司氏
講演「中世菅浦の景観」…長浜市長浜城歴史博物館館長 太田浩司氏
 レジュメ
レジュメ
長浜市西浅井町菅浦は、琵琶湖の最北端。深く入り組んだ湖岸沿いに竹生島と葛篭尾崎の先端。標高400mの山々に包まれた菅浦集落。
集落の入口(西側)には「四足門」と言われる茅葺きの門があり、村の出入りを監視する要害の門、今で言う関所の役目を果たしていた門だ(扉も無いため、集落を守る象徴的な役割)。また別名を「四方門」とも呼ばれ近年までは東西南北(現存するのは東西の二箇所のみ)の集落入口に設置され集落内を明確にしていた。この四足門は菅浦に残された文書から中世後期からすでに存在していたる。
西門をくぐると、淳仁天皇を祭神とする須賀神社がある。この地域には淳仁天皇の伝説が残っている。
菅浦の人々は淳仁天皇の氏子として暮らして来きた。 葛篭(かご)に隠れて舟で乗り…葛篭尾となり、葛篭尾崎と地名になっている。交通手段は船が主で陸の孤島だった、隠れ里。
菅浦の地には、奈良時代恵美押勝(えみのおしかつ)の乱で道鏡や孝謙上皇に負け、廃位になった淳仁(じゅんにん)天皇が住んでいたという伝説が残っている。淳仁天皇は、幽閉地で憤死したといわれ、須賀神社の裏山に淳仁天皇の御陵という塚が残っている。菅浦の村に入る東西の道には、四足門と呼ばれる茅葺きの門が残っている。かつては、ここで村に入ってくる外来者の監視にあたった(扉も無いため、集落の団結を象徴的な役割)。
また、鎌倉時代から明治時代初めにかけて作られた村落や漁村生活を記した菅浦文書が残されており、菅浦郷土資料館に保存されている。
<重文>菅浦文書1261点、菅浦与大浦下庄堺絵図(須賀神社)
・中世の村落共同体『惣村』の資料でも著名である。
・村人が朝廷へ食物を納める供御人(くごにん)だったことが分かる誓約書、警察権や裁判権を村が所持していたこと示す『村掟』
・特に、隣村の大浦との二世紀渡る日指(ひさし)・諸河(もろこ)の田畑めぐる闘争は、『菅浦文書』の中に多くの訴状資料を残す原因
菅浦は三方山に囲まれ、前面は湖だったので、集落周辺には田畑は無かった。村人は北側の山を越えて約2.3km離れた日指・諸河の谷まで耕作に行っていた。菅浦の北の集落 大浦が日指・諸河を大浦庄内と主張するのに対し、両村の境界がこれらの田畑より北にあり日指・諸河を菅浦庄内と応戦する。
この対立は、村落間の合戦に発展し、それを村人が記録した『合戦記』が現存する。のも同文書の価値を高める。
菅浦は中世から『惣村』として強固な団結力を持っていた。それを確認できるのが『四足門』である。現在は、西門・東門の2棟のみだが、かつては山から集落に入る2本の道にも、南門・北門にも存在した。






琵琶湖上をゆく【葛籠尾崎湖底遺跡と菅浦】 菅浦 2013.9.21








 波よけの石垣
波よけの石垣


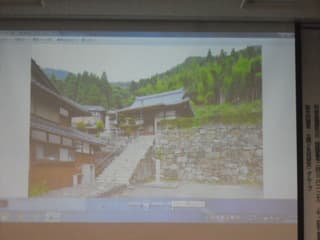 安相寺(長浜市西浅井町菅浦)
安相寺(長浜市西浅井町菅浦)
概略
浅井長政の子、万菊丸(万寿丸、幾丸、虎千代丸とも)が小谷落城の際、織田信長の追手から逃れるためこの安相寺に匿われたと『布施山温古記』に伝わる。安相寺は福田寺の末寺で、後に万菊丸は伝法院正芸と称し、福田寺の十二世を継いだといわれている。
万菊丸の縁のために福田寺と安相寺は毎年七月に進物を送りあうのを欠かさなかったという。
天嶮の要塞に守られた村
万菊丸は存在自体疑問視される声が強く、なかなか話題に上ることもありません。
しかし、同市湖北町二俣には、万菊丸が逃れるときに守護したという中島左近の子孫が現在され、当時の槍が残されているそうです。
上山田には万寿丸の母と思しき女性(お弁の方)の伝承もあります。
もちろん、これだけ伝承があるなら万寿丸が存在したに違いない!という逆説のあり、いなかったとは言い切れない…
安相寺は、万寿丸を匿うためにこれ以上の場所はない。三方を山にもう一方は湖に守られ、他の集落とは隔絶した菅浦という土地。


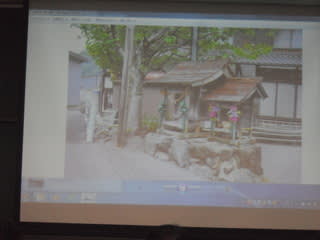


 須賀神社がある。
須賀神社がある。

 鳥居から拝殿までは長い参道が続き、その参道の中ほどから先は神域の清浄保持のため土足で立ち入ることが出来ない。もともとは素足で参拝するという村の決まりであったが、今では観光客のことを思ってか、参道の左手に靴箱とスリッパが用意されている。
鳥居から拝殿までは長い参道が続き、その参道の中ほどから先は神域の清浄保持のため土足で立ち入ることが出来ない。もともとは素足で参拝するという村の決まりであったが、今では観光客のことを思ってか、参道の左手に靴箱とスリッパが用意されている。

 橋板
橋板




















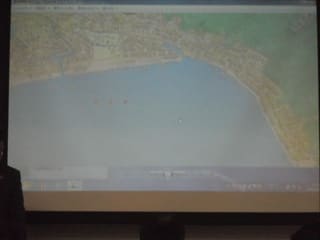

講演終了

 滋賀大学…経済学部キャンパス
滋賀大学…経済学部キャンパス
新営20周年記念特別展「重要文化財菅浦文書を読み解く」を会場



 史料館新営20周年記念特別展(冊子)
史料館新営20周年記念特別展(冊子)













































