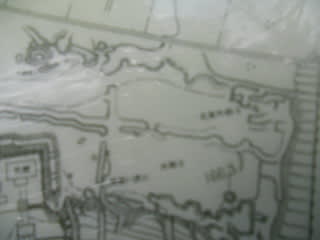お城の歴史
所在地:蒲生郡日野町佐久良 map:http://yahoo.jp/VFi-UQ
別 名:上の城山
築城期:鎌倉時代初頭
初城主:小倉三河守実澄
区 分:山城
遺 構:土塁,石積み,竪堀
標 高:269m 比高差:約150m
目標地:桜谷小学校
駐車場:桜谷小学校
訪城日:2014.3.31

お城の歴史
桜谷小学校の校舎裏手に山道があり、そこから登ります。
尾根まで登る間、大きな沢とも竪堀とも思える箇所に沿って登り、尾根に到達しましたら、左手方向に尾根伝いに進みますと城址に至ります。
視界の利かない山道を歩いて主郭跡に到達すると、ぽっかりと空が見えると感じます。
北側の櫓台跡付近にある石垣、他の小倉氏の城に見られるものではありませんし、戦国時代改修か疑問。
櫓台は古墳を利用したもの、この石積みが城にも利用されたんでしょう。 また、北側斜面・西側斜面には畝状竪堀・竪土塁がある。


長寸城は日野町佐久良の桜小学校の背後の小高い丘に築城されている。桜谷小学校裏のコンクリートの階段から登ると、すぐに山道に変わり、右手に大きな竪堀が山道と平行して走り、竪堀と山道との間には曲輪跡らしき削平地がいくつか見られる。
20分程度で山頂に着く、ここが主曲輪で入口には土塁の虎口が設けられている。
また虎口を右手のなだらかな斜面に竪堀が1本掘られ、、緩斜面を伝って直接本丸跡へ取り付く敵が意識されている。
主曲輪は虎口右手の土塁を最高として、からなだらかに傾斜しており、一段低くなった曲輪奥に石積みが残っている。
石積みは崩れ完全な形ではないが、長さ10m余り、高さは1m程度であろうか。
なお、麓の仲明寺は小倉氏の菩提寺で、小倉実澄・実重・実隆三代の墓だと伝えられる宝篋印塔がある。



お城の歴史
桜谷を領した小倉氏の佐久良城(下の城山)に対して詰の城として別名「上の城山」と呼ばれます。築城年代・築城者は不明ですが至福年間(1384~1386年)頃の築城。
佐久良城は、小倉氏の居館本城であり、長寸城を上の城山・詰め城。
永禄7年3月九居瀬(現永源寺町)に居を構える小倉右近太夫と、佐久良城を本拠とする小倉実隆(実澄の孫・実重が早世したため、蒲生定秀の三男にして賢秀の弟を養子)の間で和南で戦いが始まり、実隆が戦死。この戦いで永源寺も焼失した。
奥津保(愛知郡・蒲生郡辺り)の城を手にした小倉右近太夫を撃つため、兵を進めた蒲生氏は小倉氏との戦いに勝利し、以後この一帯を領内に編入していくことになる。
同時に佐久良城,長寸城を初めとする小倉氏の城郭は廃城となる。


































 近江ノ国_米ちゃん
近江ノ国_米ちゃん
寸城見学ルート図 GPS計測】
総距離:1.45km 総時間:1時間10分


 下山の小学校手前の【獣害柵】・・・奇岩!
下山の小学校手前の【獣害柵】・・・奇岩!
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、蒲生郡志 他
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。感謝!











 集落の鳥居平
集落の鳥居平









 近江ノ国_米ちゃんより
近江ノ国_米ちゃんより











































































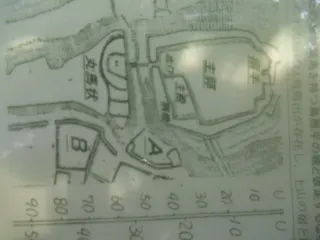



























 2の郭の土塁(切岸)は比差10m、幅20越える堀切
2の郭の土塁(切岸)は比差10m、幅20越える堀切






 長寸城下 桜谷小学校から(遠景)
長寸城下 桜谷小学校から(遠景) 佐久良城から(遠景)
佐久良城から(遠景)  滋賀県中世城郭分布調査より
滋賀県中世城郭分布調査より 1・2の郭
1・2の郭
 線路脇から1の郭へ
線路脇から1の郭へ

 破竹の切株が、郭に侵入を防御か?
破竹の切株が、郭に侵入を防御か?












 トンネルの東側へ下りた。
トンネルの東側へ下りた。
 3・4の郭への侵入口、堀(水路)を渡り、獣害ヘンスの中へ
3・4の郭への侵入口、堀(水路)を渡り、獣害ヘンスの中へ




 4の郭は土塁で囲む(雑木・竹・笹)。
4の郭は土塁で囲む(雑木・竹・笹)。



















 郭群の東裾を北(1の郭)へ・・・その東側はJR草津線
郭群の東裾を北(1の郭)へ・・・その東側はJR草津線 西ノ飼戸池
西ノ飼戸池



 北側(道路)に土塁
北側(道路)に土塁







 虎口
虎口 虎口前に、石仏2体(個人宅の畑)
虎口前に、石仏2体(個人宅の畑) 個人宅の梅
個人宅の梅 南側の竹藪が城址(竹藪と倉庫の間を・・・虎口へ)
南側の竹藪が城址(竹藪と倉庫の間を・・・虎口へ) 「南側の竹藪が城址」の道路の反対北側に石仏が
「南側の竹藪が城址」の道路の反対北側に石仏が 道路脇に空堀・土塁が見える
道路脇に空堀・土塁が見える
 飯道山の登山道を南に進み、
飯道山の登山道を南に進み、 右前方の丘陵林(竹林)が城址
右前方の丘陵林(竹林)が城址
 土橋を渡り、南から攻め込む虎口aに!
土橋を渡り、南から攻め込む虎口aに!

 主郭土塁
主郭土塁
 主郭土塁
主郭土塁
 主郭土塁
主郭土塁
 主郭土塁
主郭土塁
 主郭土塁
主郭土塁


 主郭土塁
主郭土塁





 虎口C
虎口C


 虎口Cの下平削地・・・郭
虎口Cの下平削地・・・郭


 外堀
外堀
 遠景
遠景
 岩坂集落からは中央を通る路地を南方に抜けて、その延長上の畦道から山林内に入る。山裾付近は切岸状の急崖だが、山裾を東に回りこみ、中央付近だけは竪堀状に開け進入できるので、これが大手虎口。
岩坂集落からは中央を通る路地を南方に抜けて、その延長上の畦道から山林内に入る。山裾付近は切岸状の急崖だが、山裾を東に回りこみ、中央付近だけは竪堀状に開け進入できるので、これが大手虎口。
 山裾付近は切岸状の
山裾付近は切岸状の



 山裾を東に回りこみ、中央付近だけは竪堀状に開け進入できるので、これが大手虎口。
山裾を東に回りこみ、中央付近だけは竪堀状に開け進入できるので、これが大手虎口。






























 現地案内板
現地案内板

 鎌刃城遠望・・・中央鉄塔の間
鎌刃城遠望・・・中央鉄塔の間








 連続講座・・・5回皆勤賞(21名)表彰・・・代表者
連続講座・・・5回皆勤賞(21名)表彰・・・代表者 現地探訪・・・班割
現地探訪・・・班割
 行程 大学サテライト・プラザ彦根(講義・昼食)→彦根城跡大手門前→彦根城内(米蔵跡→観音台→西の丸→本丸→天守→鐘の丸)→彦根城跡表門前 全行程約2km(石段あり)
行程 大学サテライト・プラザ彦根(講義・昼食)→彦根城跡大手門前→彦根城内(米蔵跡→観音台→西の丸→本丸→天守→鐘の丸)→彦根城跡表門前 全行程約2km(石段あり)
















 米蔵跡
米蔵跡
 米蔵へ搬入口(内堀から)
米蔵へ搬入口(内堀から)

 西の丸下へ縦掘
西の丸下へ縦掘

 西の丸下へ縦掘
西の丸下へ縦掘










 観音台(寺院跡)
観音台(寺院跡)






 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡
 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡



 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡





 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡 石垣にノミ跡
石垣にノミ跡  石垣にノミ跡
石垣にノミ跡 孕みで崩れた石垣
孕みで崩れた石垣














































































 鳥居前堀
鳥居前堀

 駐車場は出庭公民館の敷地内(出庭蓮池公園)
駐車場は出庭公民館の敷地内(出庭蓮池公園)






 古高城の位置は明確ではないが、周囲に「東屋敷」「西屋敷」「南屋敷」「堂ノ内」の地名がある大将軍神社のあたりに城郭があったと考えられている。
古高城の位置は明確ではないが、周囲に「東屋敷」「西屋敷」「南屋敷」「堂ノ内」の地名がある大将軍神社のあたりに城郭があったと考えられている。






 金森城の下流の堀
金森城の下流の堀
 将軍神社の隣に土塁(古高城のものカ?)
将軍神社の隣に土塁(古高城のものカ?) 鳥居~拝殿まで、神社土塁に堀(今は用水路)
鳥居~拝殿まで、神社土塁に堀(今は用水路) 境内にある土塁の名残カ?
境内にある土塁の名残カ?


 欲賀城址とされる浄光寺。
欲賀城址とされる浄光寺。 『浄光寺案内石板』より
『浄光寺案内石板』より





 境内の土塁
境内の土塁 本堂裏
本堂裏


 浄光寺南西隅の藪。土塁跡
浄光寺南西隅の藪。土塁跡


















 旧城内に覚明寺。
旧城内に覚明寺。




 八尾神社前には説明駒札
八尾神社前には説明駒札






 堀(現状:水路)
堀(現状:水路)








 郭跡カ?
郭跡カ? 社殿南の水堀(庭園カ?)
社殿南の水堀(庭園カ?)


 四足楼門前に土塁
四足楼門前に土塁




 中山道より一の鳥居
中山道より一の鳥居
 中山道より水堀・石橋
中山道より水堀・石橋 滋賀県栗東市の地名 綣(へそ)と読む。
滋賀県栗東市の地名 綣(へそ)と読む。 説明板
説明板
 芭蕉句碑
芭蕉句碑

 綣村城(大宝神社二ノ鳥居前に)
綣村城(大宝神社二ノ鳥居前に)





 水をめぐる争い=井堰の開発。愛知川井関図。(愛東の歴史ダイジエストより)
水をめぐる争い=井堰の開発。愛知川井関図。(愛東の歴史ダイジエストより) 愛知川沿いの村々(元禄期近江国絵図)。(愛東の歴史ダイジエストより)
愛知川沿いの村々(元禄期近江国絵図)。(愛東の歴史ダイジエストより) 井元城跡縄張図
井元城跡縄張図














 城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年)
城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年)

 主郭虎口から馬出しを望む
主郭虎口から馬出しを望む





















 本殿の東西に、佐々木氏の家紋(斜め四ツ目結)が
本殿の東西に、佐々木氏の家紋(斜め四ツ目結)が