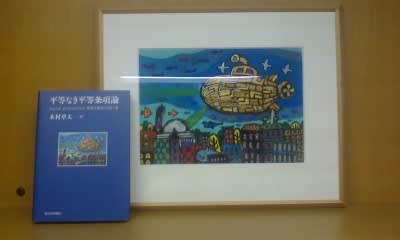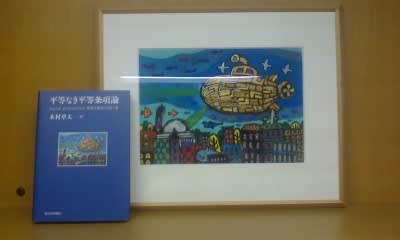というわけで、法令審査全部書くのって、めんどうですよね。
おまけに、適用例が二つしか想定できない条例でこの始末。
なので、法令審査の途中式が全て書かれる判例なんて、めったにお目にかかれません!!
・・・・。それはさておき(おくんかい!)、
途中式みてみると、法令審査って、法文を手掛かりに想定された
個別の処分の合憲性審査を複数回やってるだけなんですよね。
なので、法令審査と処分審査で、違憲審査基準が変わるか、っていうと
基本的な考え方は変わりません。
ただ、ちょっとだけ注意が必要なのは、
法令審査で、この処分は・・・、次の処分は・・・と判断していく中で、
ある処分を審査する基準と、別の処分を審査する基準が変わるケースはあります。
例えば、「デモ行進はしてはならない」っていう条例について
A:他と平等に、修習生給費性を訴えるデモ行進を規制すること
B:原発反対を訴えるデモだけを狙い撃ちして規制すること
という適用例が想定される場合。
Aは内容中立規制、Bは内容規制なので、
Bの審査をするときは、基準がより厳しくなる。
こういうケースもあるはずです。
ええ、まとめると、
法令審査の場合の審査基準っていうのがあるわけではなくて、
法令の文面から想定される処分の種類に応じて、
審査基準は使い分けるはず。
その使い分け方は処分審査の場合と同じ。
こうなるはずです。
PS 二段階審査
因みに、法令審査(じゅうらい文面審査とよばれてきたもの)って、
その法令の全適用例を想定し、審査するものなので、
それをやっちゃうと、処分審査をやる意味がなくなります。
(え、ここよくわからないの方は、
外科手術の比喩を参照して下さい^-^)
ちうことはですね、
よく答案例で見かける法令+処分の二段階審査をするためには、
最初の段階で、今見たような法令全体の審査をしちゃ、
理論的に残念な事態になっちゃいます!
というわけで、二段階審査をする場合、
一段階目の審査は、
典型的な適用例だけ、
あるいはもっとも違憲の疑いの弱い適用例だけ、を審査して、
「典型的用例orもっとも違憲の疑いの弱い適用例ですら違憲なのだから、
法文全体も違憲だろう」
あるいは
「少なくともこの適用例は合憲なので、法文自体は違憲ではない。
では、この処分は?」
と流すしかないのです。
あのですね、これ、理論的に考えると、こうならざるを得ないのに、
ここを理解してくれない人、けっこう、多いのですよ。
昔は、講義のあとに、
「木村先生は、二段階審査のやり方、まちがってますよ。」
とか言われたり(・・・遠い目)。
はい。でも、こうおっしゃられた学生の方と、
きちんとお話しをしたら、わかってくれました(・・・良い思い出です)。