7月25日(月)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
葬儀で和尚様がやたらと木魚を叩くので
木魚が気になった!
少し由来をしらべてみた・・・・

何故”魚”何だろう。?
普通は生臭いものはお寺さんの行事・修行には、不向きなものだが・・・・!
そこで木魚で引いて(検索)してみると
**************************************************************
木魚は、
読経をするときに打ち鳴らすことで、リズムを整える。
また、眠気覚ましの意味もあり、木魚が魚を模しているのは、
眠るときも目を閉じない魚が
かつて眠らないものだと信じられていたことに由来する。
禅宗や天台宗、浄土宗などで用いられる。
浄土宗では木魚の使用が禁じられた時期もあったが、
その後念仏を唱えるときに使用されるようになった。
小さな座布団状の台の上に置かれ、先端を布で巻いたバチで叩くと、
「ぽくぽく」という感じの音が鳴る。

大きさは直径6cm程度から、1m以上のものまである。
自らの尾を食う魚や、
2匹の魚や
龍が珠を争う姿などを図案化した鈴のような形をしている。
表面には魚の鱗が彫刻されている。
クスノキなどの木を材料としてつくられる。
内部は空洞になっている。開口部である「響孔」にあたる部分から刃を入れ、
内部に空洞が作られる。
木魚の原型は禅寺で使われていた「魚板」(魚鼓)である。

これは黄檗宗の本山である黄檗山萬福寺で見る事ができる。
魚板とはその名の通り魚の形をした板であり、
たたき鳴らすことで人を集める合図とした。
魚の形をしているのは、魚は日夜を問わず目を閉じないことから、
修行に精進することの象徴であったためとされる。
そして、魚の腹をたたくことで煩悩を吐き出させる、
という意味合いが有ったともされる。
そして雑学だが、眠気覚ましの為に一定のリズムを刻んでいたとも言われる。
明代には、現代の木魚の形が確立している。
日本では室町時代の木魚は存在するが、
本格的に使用したのが江戸の始めに中国から渡来した隠元禅師。
彼が伝えた黄檗宗では木魚をはじめ、あらゆる楽器を使用する。
黄檗梵唄が有名。
****************************************************************
実際、一定のリズムで”ポクポク”叩かれている音を聞いて
いると、不謹慎だが”私は返って眠気が増してきた。
多分自分で叩けば眠気も飛ぶのだろうが・・・!
聞いているのは眠気を誘う。
*************************************
こんな俳句が思い出される。
”叩かれて 夏の蚊を吐く 木魚かな”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
葬儀で和尚様がやたらと木魚を叩くので
木魚が気になった!
少し由来をしらべてみた・・・・


何故”魚”何だろう。?
普通は生臭いものはお寺さんの行事・修行には、不向きなものだが・・・・!
そこで木魚で引いて(検索)してみると
**************************************************************
木魚は、
読経をするときに打ち鳴らすことで、リズムを整える。
また、眠気覚ましの意味もあり、木魚が魚を模しているのは、
眠るときも目を閉じない魚が
かつて眠らないものだと信じられていたことに由来する。

禅宗や天台宗、浄土宗などで用いられる。
浄土宗では木魚の使用が禁じられた時期もあったが、
その後念仏を唱えるときに使用されるようになった。
小さな座布団状の台の上に置かれ、先端を布で巻いたバチで叩くと、
「ぽくぽく」という感じの音が鳴る。

大きさは直径6cm程度から、1m以上のものまである。
自らの尾を食う魚や、
2匹の魚や
龍が珠を争う姿などを図案化した鈴のような形をしている。
表面には魚の鱗が彫刻されている。
クスノキなどの木を材料としてつくられる。
内部は空洞になっている。開口部である「響孔」にあたる部分から刃を入れ、
内部に空洞が作られる。
木魚の原型は禅寺で使われていた「魚板」(魚鼓)である。

これは黄檗宗の本山である黄檗山萬福寺で見る事ができる。
魚板とはその名の通り魚の形をした板であり、
たたき鳴らすことで人を集める合図とした。
魚の形をしているのは、魚は日夜を問わず目を閉じないことから、
修行に精進することの象徴であったためとされる。
そして、魚の腹をたたくことで煩悩を吐き出させる、
という意味合いが有ったともされる。
そして雑学だが、眠気覚ましの為に一定のリズムを刻んでいたとも言われる。
明代には、現代の木魚の形が確立している。
日本では室町時代の木魚は存在するが、
本格的に使用したのが江戸の始めに中国から渡来した隠元禅師。
彼が伝えた黄檗宗では木魚をはじめ、あらゆる楽器を使用する。
黄檗梵唄が有名。
****************************************************************
実際、一定のリズムで”ポクポク”叩かれている音を聞いて
いると、不謹慎だが”私は返って眠気が増してきた。
多分自分で叩けば眠気も飛ぶのだろうが・・・!
聞いているのは眠気を誘う。
*************************************
こんな俳句が思い出される。
”叩かれて 夏の蚊を吐く 木魚かな”
















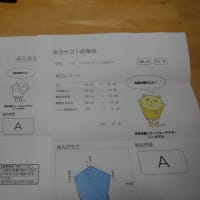



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます